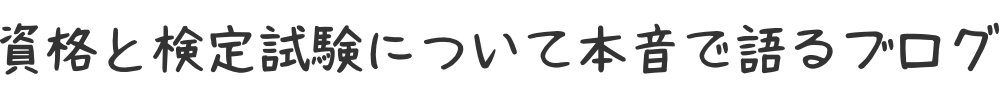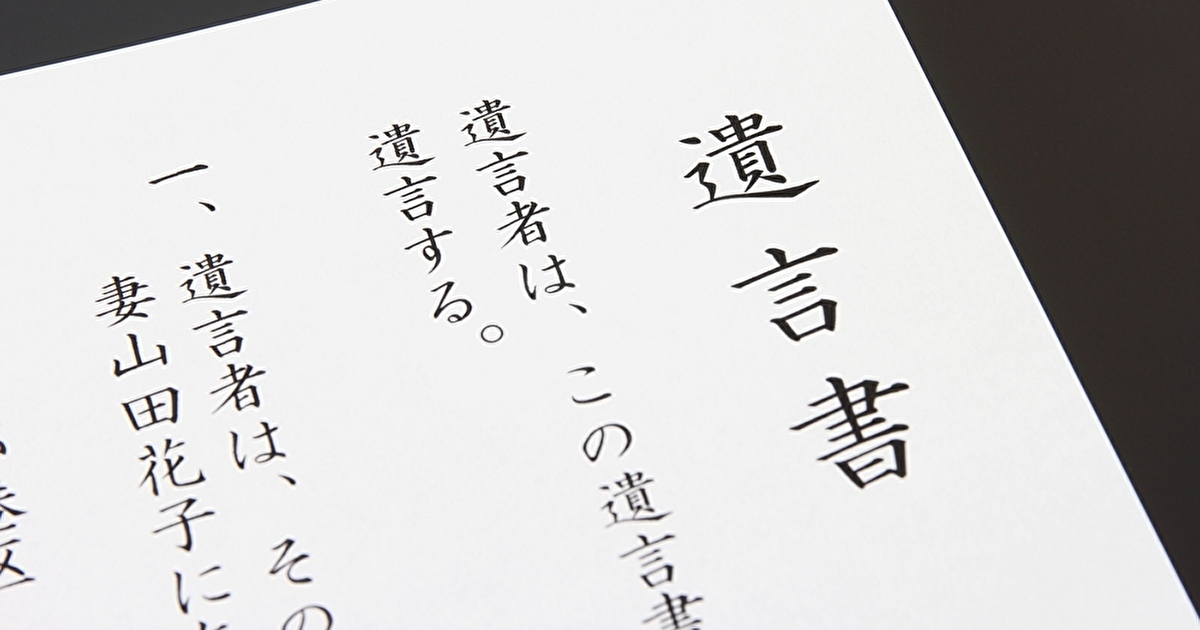相続に関する民間資格(検定試験)ってたくさん存在します。ホントよく目にします。
例えば、相続診断士、相続検定、相続アドバイザー、相続カウンセラー、相続コンサルタントなどです。
探せばまだまだいっぱい出てきます。軽く100種類以上はあります。
なんとなく専門性が高そうなので、取得すれば独立できたり仕事に役に立ちそうな雰囲気がします。
けれど、どれか勉強してみようかな・・・なんて考えない方がいいですよ。
勉強して無駄とまでは言いませんけど、名乗るほどの価値があるのかと言えば大いに疑問です。
講座受講料と受験料、それに登録費用や年会費、更新費用を目的としてる民間資格も多いので要注意です。
それどころか、ヘタに相続業務に関わると場合によっては逮捕される可能性も十分にあります。
大袈裟でもなんでもないですよ!
こういった民間資格を取得して独立しようなんて考える人がマレにいますけど、できることは限定的です。
お金を稼げるほどではないでしょう。
相続の分野には怪しい民間資格がいっぱい!
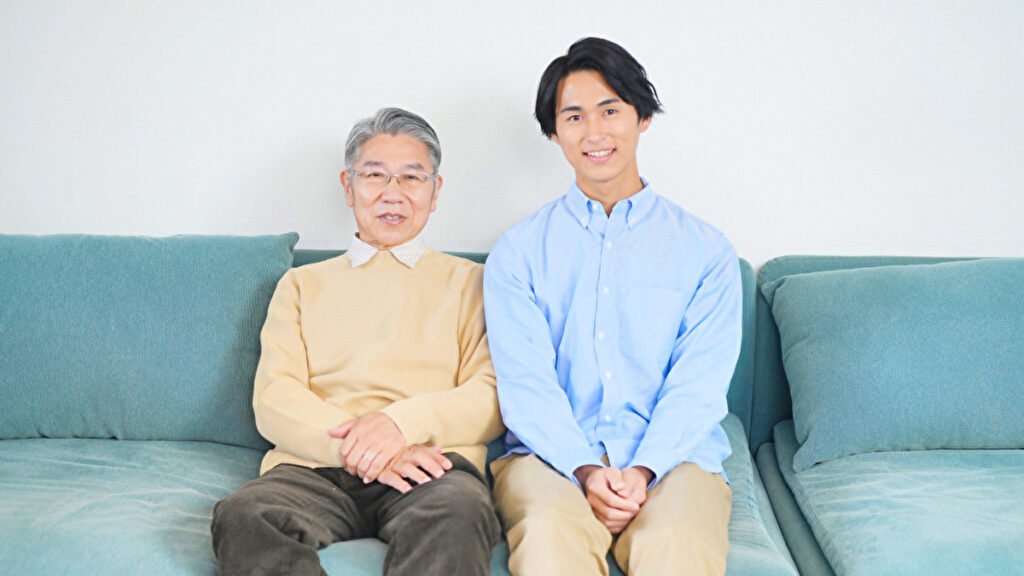
相続士、相続検定、相続対策専門士、相続プランナー、相続コーディネーター、相続カウンセラー、相続コンサルタント、相続支援コンサルタント、相続マイスター、遺言執行士、相続法務指導員、相続知識検定、相続ファシリテーター、相続手続カウンセラー、相続実務士、相続管理士、相続相談士、相続実務検定、相続対策プランナー、相続実務コンサルタント、相続コーディネート実務士、相相続技能士、相続支援士、相続アドバイザー…数え出したらキリがありません。
※相続アドバイザーは銀行業務検定の1つで取得する価値はあります。
「士」という漢字1文字をワザとらしく使って・・・なんか専門家っぽい響きをいっぱい漂わせてますね。
指定の通信講座を受講すれば短期間で合格できるような検定試験が中心で、学習する内容はどれも初歩的です。専門性という面ではいずれもかなり低いようです。
相続の仕事っぽい感じはしますけど、こういった民間資格で一体何ができるのでしょうか???
相続に関する民間資格で一体何ができるのか?

こういった相続に関する民間資格を取得すれば一体何ができるのか?どれくらい踏み込んで相続に関する業務ができるのか?ちょっと気になりますよね。
取得するのもタダじゃないです。結構高い金額が必要です。取得する以上何かに役立たせないといけません。
結論を申し上げますと、民間資格ですから法律上認められた業務は何一つ存在しません。
つまり、合格したところで特別にできる業務はありません。できる業務は一般的な「相続に関する相談」程度です。
あるいは専門家への橋渡し(つまり専門家の紹介)くらいです。
それでお金を稼げるのかと言えばかなり疑問です。
少し踏み込んだ話しをするとほとんど全て違法な行為につながると思った方がいいでしょう。
ADR(裁判外紛争解決手続)をウリにしている民間資格もありますが、こういった「交渉の提案」は資格は不要で、誰でも仲裁人となることができます(一般的にそう解されています)。
ただ単に相続に関する民間資格だけでは、何もできないと思った方がよいでしょう。
もちろん中にはこうした資格を仕事に活かしている人もいますが、他の国家資格を併せ持った人です。例えば、税理士とか司法書士、行政書士などです。
あるいは、銀行窓口担当者であれば、顧客から相談を受けた際に手際良く専門家を紹介するには知識が役に立ちます。
相続には多くの国家資格の有資格者が関わる
相続に関する相談の対象は、多くの場合は亡くなった人の現金・預金や株券、それに土地や建物などの不動産です。
これらに関する相続業務は国家資格を持った法律の専門家にしかできません。専門性の高い国家資格の有資格者のみにしかできない独占業務が数多く存在します。
まず、相続人同士で揉めているようであれば弁護士じゃないと解決できません。
不動産の名義を変更する必要があれば司法書士です。
相続のために土地を分割(文筆)するのであれば土地家屋調査士です。土地を売却する際に境界の確定をするのも土地家屋調査士です。
相続税が発生するようであれば相続税の算出は税理士です。
遺産分割協議書は相続人が作成してもかまわないですが、作成するのが難しい場合は弁護士・司法書士・税理士・行政書士に依頼します。
この場合、それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるので依頼先も異なります。
相続には多くの国家資格を持った専門家が関わります。一人で完結するものではありません。
仮に、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などを全て自分の意思でコントロールできるほどの知識と経験があれば「相続コーディネーター」として活躍することは可能かもしれません。
けれど、民間の検定試験に合格したからと言って、すぐに弁護士・司法書士・税理士・行政書士などと対等に話しあえるほどの知識は身に付かないでしょう。
素人では簡単には手を出せない世界なんです。
相続税の相談業務は税理士にしかできない
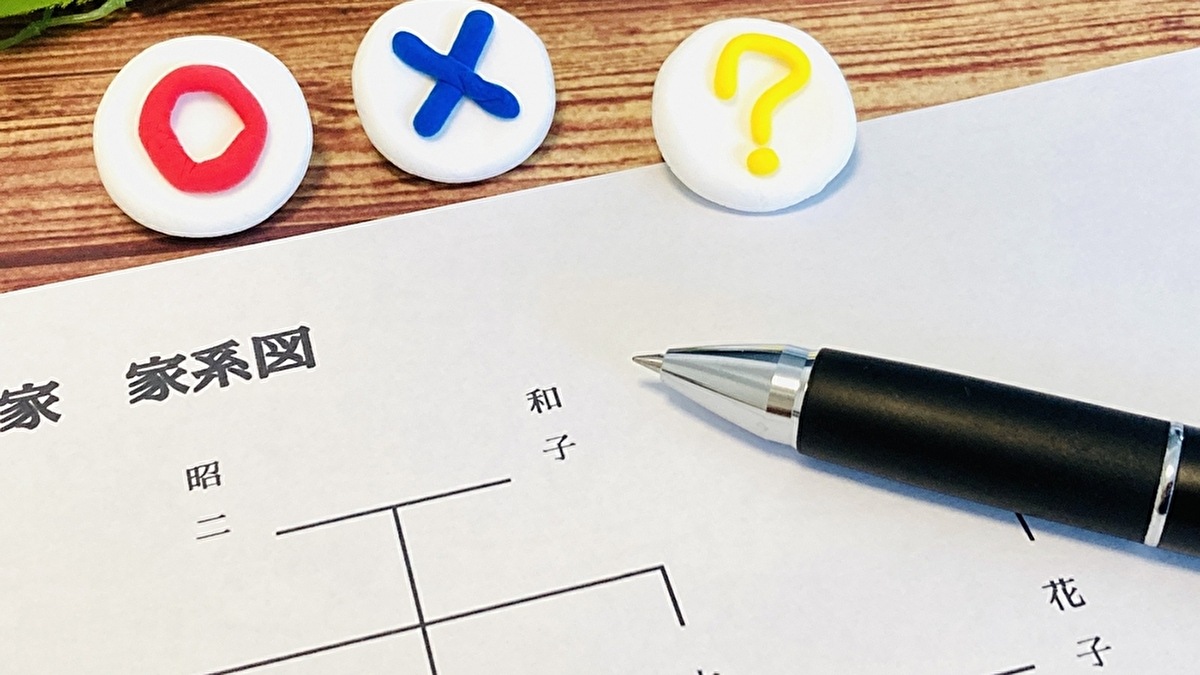
相続に関する相談というと、メインとなるのはやはり相続税や遺産の分割です。
有料相談・無料相談を問わず、税理士以外の者が、他人の税金の試算をしたり、税金に対する助言や判断をすると税理士法違反になります。
例えば、税金に関する相談を受けて、「一般的に、残された財産が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下なら相続税は支払わなくても大丈夫ですよ」と、法律の規定を説明するくらいであれば問題ありません。
個別に財産の額を聞き取って総額を計算し、「あなたの場合、基礎控除額を超えてるから税金を払わないと・・・」などとは言えません。概算であっても税理士じゃないとアドバイスはできません。
相談を受けて、軽い気持ちで「だいたいこれくらいの相続税になりますよ」と言うと、税理士法違反で逮捕される可能性があるんです。
関連資格:税理士とは
マレに税理士法違反で逮捕される行政書士もいる
「そんなことでいちいち逮捕されないよ!」って思うかもしれませんけど、時々yahooニュースに、税理士法違反で逮捕される行政書士の記事なんかが載っています。
「逮捕される」なんて大げさでも何でもないんです。
相談程度だと思って、軽い気持ちで通帳の残高を見せてもらって合計を算出したりすると、それだけで税理士法違反です。
「相続○〇〇」なんて名乗ったはいいものの、資格を活かそうとしたら逮捕された!なんて言ったら一体何のためにお金をかけて取得したのかわかりませんよね。
まれに、こういった民間資格だけで独立して開業する人がいますが、法律違反となる業務に手を出して逮捕されるリスクも十分考えられます。
悪いことは言いません。相続に関わる仕事をしたいのであれば、他の国家資格を目指してください。
なんで相続に関する民間資格がこんなに多いのか?
そもそも、なんでこういった相続に関する民間資格が次から次へと出てくるのか?
理由は簡単です。
誰だっていつかは相続人(残った人)や被相続人(亡くなった人)になります。高齢化社会により今後相続に関する専門家の需要が見込めるからです。
と、まぁ表向きはこんな理由ですが、本音はというと・・・
関心を持っている人が多いので、講座を開けば手っ取り早く受講生を集められるからなんです。
なんとなくそれっぽい民間資格を作って、通信講座を運営すれば生徒は集まります。
つまり主催者にとって、相続は「儲かる分野」なんです。