相続診断士って取得する意味やメリット・活かし方はあるの?
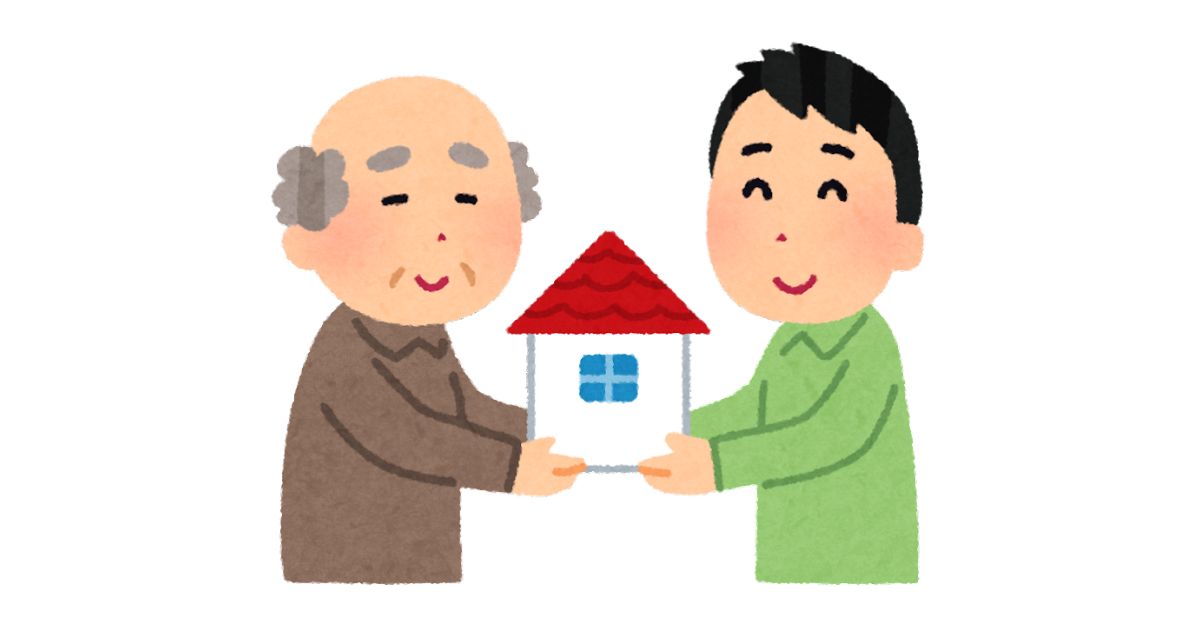
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | 90% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 指定講座受講 | 4~10万円 | 1か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 要再考 | 2件 |
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年5月22日に集計しました。
- 取得に関しては再考をおすすめします。
| 試験の級 | 他に「上級」あり |
| 講座受講料 (必須) | 38,500円(税込) 上級:88,000円(税込) |
| 受験料 | 講座受講料に含みます。 |
| その他費用 | 更新料16,500円/2年毎(税抜) 登録代金:11,000円(税込)※上級相続診断士のみ 月会費:1,018円(税込)※上級相続診断士のみ |
- 上級相続診断士は月会費のみで更新の必要はありません。
- 金額は2024年12月現在です(内容は主催者に確認済み)。
相続診断士は難易度の低い民間資格です。
国家資格とは違い法律上認められた業務などはなく、合格しても特別にできる業務はありません。
指定の講座を受講すれば短期間で合格できます。
身に付くのはおそらく相続に関する基本的な知識のみでしょう。
それで複雑に法律がからむ相続業務に関しどれくらい対応できるのか・・・大いに疑問に感じます。
合格しても、相続に関するトラブルに対して解決方法を提案したり解決のための具体的な相談には乗れません。相続税の個別具体的な相談にも乗れません。
つまり、この民間資格を持っていても持っていなくても同じです。
相続診断士は指定講座受講が必須、2年毎の更新料や維持費も高い!
勉強するなら他の国家資格をおすすめします。
相続診断士とは

相続に関する民間資格
相続診断士とは、相続診断協会(JiDA)という団体が試験を実施する民間の検定試験です。
試験に合格すれば、相続に関する基本的な知識を持っていると相続診断協会から認定されて「相続診断士」と名乗れます。
ただし、試験を受験するには、テキストや講義が収録されたDVDが付いた指定の講座を受講しなければなりません。
相続診断士の民間資格に合格しても、相続に関するトラブルに対して解決方法を提案したり、解決のための具体的な相談には乗れません。
![]() 催者サイト:一般社団法人 相続診断協会
催者サイト:一般社団法人 相続診断協会
相続診断士は何ができるのか?
では一体、相続診断士にできることは何か?
できることはかなり限られています。
相続診断士にできる精一杯の業務としては、正しい遺言書の書き方の指導、誰が遺産の相続人になるのか、相続人によって分割する割合はどれくらいか、そういった一般的な民法の規定に関する説明ができる程度です。
そして、できるだけ早く税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、そして弁護士などの法律の専門家に取り次ぐことです。
つまり専門家の紹介です。
その他の相続診断士の業務は、相続に関する知識をあまり持っていない一般の人への「啓蒙活動」です。
相続診断協会はこれらの業務を「相続診断」と公式ホームページでは明記してますが、こういったニーズが世間であるのかは微妙です。
短期間で誰でも合格できるような民間資格では、合格しても役立つとは言い難いでしょう。
つまり、取得するメリットは少ないということです。
っていうか、民間資格ですからこの資格を持っていても持っていなくてもそもそもこういった業務は誰にでもできます。
民間資格ではほぼ何もできない
相続診断士が法律相談を有料ですれば弁護士法違反(非弁行為)となります。相続トラブルの仲裁などは一切できません。
相続税の試算・概算をしても税理士法違反です。現在の資産(預金、所有する株式等)を聞き取って概算で相続税の計算ができるのは税理士に限られます。
※仮に報酬を得なくても、反復して継続的に法律相談を行えば違法です。
で・・・一体それ以外何をやるの???って感じです。
考えてもみてください。
税理士になるにも、司法書士になるにも、弁護士になるにも、何年もかけて真剣に勉強しなければなりません。合格できるのは一部の人のみです。
つまり、相続に関する業務には豊富な知識に基づく高度な専門知識が求められます。
相続診断士は、全くの知識ゼロでも1か月ほどで合格できます。学習する内容は相続に関する基礎知識のみです。
こういった民間資格がどれほど役に立つのか、世間で求められているのか・・・少し考えれば分かるはずです。
役に立つ民間資格なのか?

相続診断士として開業して食べていけますか?
はたして、相続診断士の民間資格で開業して本当に稼げるのでしょうか???
相続診断士の民間資格だけで稼ぐのは相当難しいと思います。できることが限られているからです。
相続診断協会の公式ホームページを見ると相続診断士として開業した人の成功事例が紹介されています。
ネットで調べると、開業者のブログもあればYouTubeの動画もあってPRは盛んです。
どこまで真実なのかは分かりませんけど・・・
「今後、世間では相続診断士が不足する・・・」なんて書いてあれば、興味を持って読んだ人はその気になってしまいます。合格後は独立して稼げるような雰囲気がいっぱい漂っています。
相続業務で稼げる可能性があるとすれば、既に税理士や行政書士として活躍している人くらいではないでしょうか。
けれど、税理士や行政書士の資格があれば民法の相続の知識は十分持ち合わせているのでそもそも相続診断士の民間資格など必要ないでしょう。
本気で相続について学びたいのであれば国家資格を
本気で相続について学びたいのであれば、民法について深く学習する必要があります。
例えば、相続人の範囲・順位、相続する割合(相続分)などの相続に関わる重要な条文は全て民法で規定しています。
相続の専門家になりたいのであれば、民法の出題がある国家資格を目指しましょう。
司法試験(予備試験)、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士などです。
これらの国家資格であればいずれも民法について学習します。
合格して開業すれば相続業務の一端を担えます。
相続に関する民間資格の多くは講座受講生募集が目的?
世の中には、「相続〇〇」という民間資格が多く存在します。例えば
相続アドバイザー、相続検定、遺言執行士、相続鑑定士、相続士、相続法務指導員、相続知識検定、相続マイスター、相続支援コンサルタント、相続ファシリテーター、相続手続カウンセラー、相続カウンセラー、終活アドバイザー、終活カウンセラー、事業承継アドバイザー、事業承継士、相続財産再鑑定士、相続プランナー、相続対策専門士、相続コーディネーター、相続実務士、相続管理士、相続相談士、相続実務検定、相続ファシリテーター、相続対策プランナー、相続実務コンサルタント、相続コーディネート実務士、相続法務指導員、相続技能士、相続支援士等…
すごい数ですね。
まだまだ調べればたくさん出てきます。一体どんな違いがあるのでしょうか。
結論を申し上げますと、内容に違いはそれほどありません。
それに・・・多くは指定の講座受講が条件です。
それで儲けるのが目的なの?って感じるのは私だけでしょうか・・・
合格後に入会金や月会費が必要となる講座も普通にあります。
全てが怪しいとまでは言いませんが、少なくても権威があるとは言い難いです。
中には講座受講料さえ支払えば講習を2回受講して全員即合格!なんて眉唾ものの怪しい資格商法的な検定試験も存在します。注意しましょう。
こういった短期間で取得できる検定試験がどれくらい役に立つのか・・・前述の通り、少し考えればすぐに分かるはずです。
参考書籍
相続に関する書籍は数多く出ています。良質な本も多いので、自分で購入して読めば相続に関する知識は身に付きます。
相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査のポイントまで学べる一冊です。
相続税の課税のされ方や、相続税が軽減される特例内容などを本書で知ることができます。
あまり専門的な用語を使わず、具体例を出して相続で起こりそうな問題と解決の道筋を平易に解説しているので、抵抗感なく理解が進みます。
筆者は、これまで500件以上の相続税申告をしてきた税理士です。相続税の相談実績は5000人を超え、全国の銀行や証券会社を中心に通算 500回以上の相続税セミナーの講師を務めています。
| 種類 | 評価 |
| 参考書籍 |  |
身近な人が亡くなると、死亡届・火葬許可申請書の提出をはじめ、健康保険・介護保険の資格喪失届の提出、年金受給停止の手続き、通夜・葬儀の手配など、さまざまな手続きが必要になります。
本書は、そのような手続きやお金の工面についての152問に、弁護士・税理士・社会保険労務士がマンガ・図解でわかりやすく解説しています。
お金の工面や相続トラブルの問題、贈与・遺言・エンディングノートなどの生前対策にも対応しています。
| 種類 | 評価 |
| 参考書籍 |  |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
毎日実施
お申し込み
随時、インターネットによる申し込み
受験資格
指定の通信講座を受講するのが条件です。
試験会場
全国260ケ所以上の受験会場(CBT受験)
試験内容
※試験は相続診断士と上級相続診断士の2種類です。下記は相続診断士についての内容です。
- コンプライアンス 10問(20点)
- 民法相続編 15問(15点)
- 相続税 15問(20点)
- 相続税穴埋め 12問(24点)
- 法定相続分 3問(9点)
- 基礎控除 2問(6点)
- 小規模宅地 3問(6点)
問題数:合計60問
試験形式:○×、三肢択一、穴埋め方式
試験時間:60分
合格基準
70点
合格発表
試験終了後、パソコン画面にて合否を表示。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は試験について|一般社団法人 相続診断協会をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は試験について|一般社団法人 相続診断協会をご覧ください。
