品質管理検定(QC検定)は民間資格だが取得するメリットは大きい
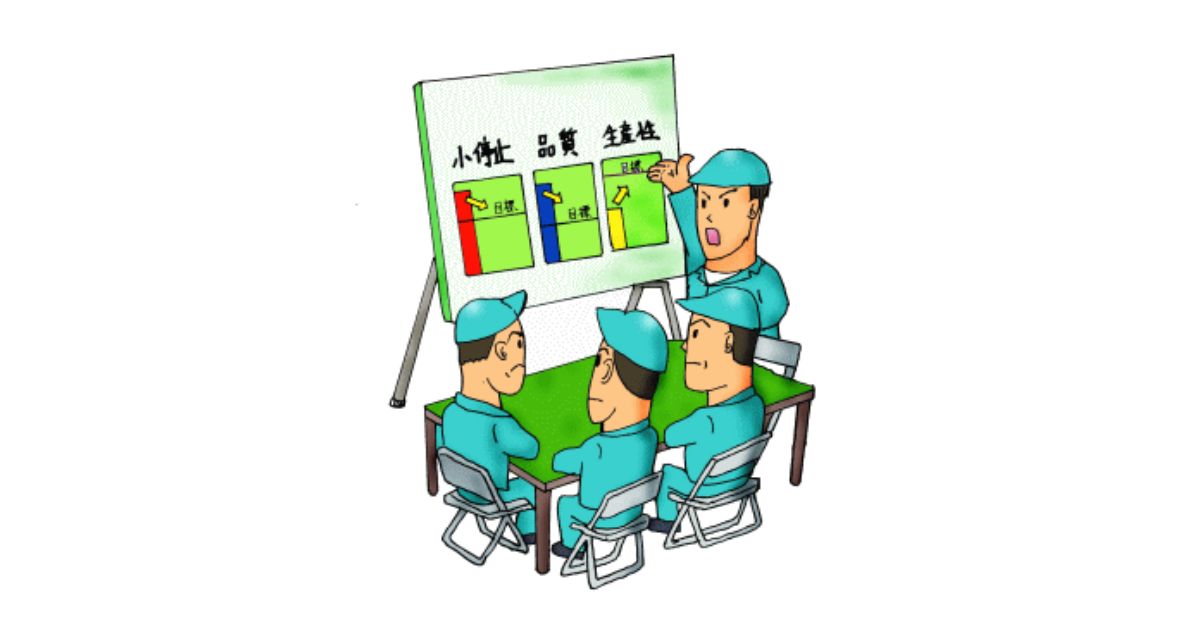
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | 50% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 1か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 評価アップ | 46件 |
- 上記は3級に関する数字です。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年3月12日に集計。
取得を推奨している企業は多く、難易度が高い2級以上合格で就職や転職が有利になるメリットがあります。
民間資格ですが勉強する価値は十分あります。
高い合格率が見込めるおすすめの通信講座
品質管理検定(QC検定)とは

年間6万人以上が受験する人気の検定試験
品質管理検定(QC検定)とは、品質管理・QCに関する知識が、どの程度あるのかを問う民間の検定試験です。
2005年にスタートした比較的新しい試験ですが、年間の受験者数が6万人を超えていて、学生から社会人まで幅広い人が受験します。
品質管理検定の受験生は、機械や食品などの工場で品質管理を専門としている人だけではなく、働く全ての人が対象です。
マーケティング、生産管理、商品企画部門でも品質管理に関する知識が求められます。
物流、倉庫、販売などでも知識が求められる場合があります。
品質管理を厳しく求めるホテルや百貨店などのサービス業も該当します。
基本的に品質管理の知識が必要となるのは業種、業態に特に制限はないと考えてよいでしょう。
![]() 主催者サイト:QC検定|日本規格協会 JSA Group Webdesk
主催者サイト:QC検定|日本規格協会 JSA Group Webdesk
品質管理・QCって一体何?
ところで、このQCという用語、一体なんの略かと言うと、「Quality(:品質) Control(:管理)」の頭文字をとっています。文字通り「品質管理」という意味です。
品質管理(QC)とは「買い手(顧客)の要求に合った品質の品物、またはサービスを経済的に作り出すための手段の体系」と定義されています。
つまり、「品質管理」や「QC」とは、製品やサービスの品質を管理してサービスの質を向上させよう!という企業の一連の取り組みを表しています。
簡単に言うと、漫然とただ商品を作るのではなく、どう工夫すればお客さんが喜んで満足してくれるような製品やサービスを提供できるか?という企業と従業員が一体となった活動です。
無駄を省いて利益を少しでも増やす狙いも
品質管理(QC)の例を上げると、
- パンを買ってくれるお客さんに、無添加で美味しい食パンを安く提供する
- 高齢者でも安全に運転できて、歩行者にも安心なクルマを低コストで作る
- ファミレスに来てくれたお客さんのために、美味しくて安全な料理を安く出す
という品質やサービスの改善に関する内容です。
もちろんキレイ事だけではなく、いかにコストを抑えて高い利益を出すかというのがそもそもの始まりであるのは言うまでもありません。
無駄を省くことで利益を少しでも増やすのも品質管理・QCの狙いです。
品質やサービスを向上を目指しているのは営利を目的とした企業だけにとどまらず、最近では役所などの公共機関、ボランティア団体などもこういった活動に力を入れています。
例えば、市役所や病院などで「住民ファースト」「市民ファースト」「患者ファースト」という活動や考え方は、まさに品質管理・QCの一環だと言えます。
役に立つ資格なのか?

民間資格だが評価は高い
大企業・中小企業、職種・分野に関係なく、ほとんどの企業では広い意味で品質管理を日々行っています。
そのため、品質管理検定を社内で推奨している企業は多く存在します。採用時に合格者を評価する会社もあります。
試験の主催者である品質管理協会のホームページを見ると、品質管理検定を推奨してる「QC検定協賛企業」の一覧が載っています。
![]() 参照:参加企業・団体・学校一覧|日本規格協会 JSA Group Webdesk
参照:参加企業・団体・学校一覧|日本規格協会 JSA Group Webdesk
掲載可と回答した企業のみということですが、計2,104社あり日本を代表するような大手企業ばかりです。
こういった企業(特に製造業)に勤務しているのであれば、合格することで昇格昇進などで役立つメリットもあります。
就職・転職を希望するのであれば履歴書に書けば多少は有利になるでしょう。
品質管理検定とは民間の検定試験にすぎませんが、大企業においては意外と評価は高いようです。
参考:アイシングループにおけるQC検定の導入・活用事例の紹介(pdf)
※アイシングループとはトヨタ自動車の大手自動車部品メーカーで現社名は株式会社アイシンです。
将来性について徹底研究

この資格の活かし方
品質管理検定の学習を通して品質管理に関する幅広い知識を習得できます。
難易度の高い級に上がるに従って知識が広がるため、継続して学習するだけのメリットは十分にあります。
特に製造業で品質管理検定を推奨している会社は多く、中堅社員に品質管理検定の3級か2級の取得を命じる会社もあります。
その場合、一般社員レベルでは3級、リーダーや管理職なら2級以上が求められます。
合格すればもちろん昇格昇進などに影響します。
会社で命じられたら是が非でも合格しましょう。知識は十分に仕事に活かせるはずです。
品質管理の重要さは製造業だけではなく接客業などにも浸透しつつあります。
今後資格を活かせる職場は増加するでしょう。
QC7つ道具を活用して品質改善する
「QC七つ道具」って用語を時々聞きます。品質管理を勉強するのであれば必ず避けて通れません。
品質管理検定においても3級以上では必ず出題されます。
簡単に言うと、品質の改善活動に役立つ手法のことです。道具とは言え、棒グラフ、折れ線グラフ、チャート図、一覧表のようにExcelを使って作成する表のようなモノです。
「QC七つ道具」の種類は以下の通りです。
- 特性要因図
- パレート図
- グラフ・管理図
- チェックシート
- 散布図
- 階層
- ヒストグラム
最近は「新QC七つ道具」が主流ですが、内容は8つに増えています。
品質管理をおこなうために、製造現場ではさまざまなデータが集められています。
代表例は原材料の費用から人件費、光熱費などです。
しかし、データはたくさんあっても、うまく活用しなければ品質管理には活かせません。
そこで、QC七つ道具という手法によりデータをグラフ化することで、問題・課題が誰にでも簡単に分かるようにします。
手法の特徴を理解して、目的により七つ道具を使い分けることで、現場での問題解決を計ります。
意外と高い受験者の平均年齢
下記は、第38回QC検定(2024年9月実施)の受験者平均年齢の統計データです。
- 4級 29.6歳
- 3級 34.7歳
- 2級 37.3歳
- 1級 35.6歳(一次試験免除)
- 1級 42.2歳
![]() 引用元:各級の受検者・合格者の年齢別構成|2024/10/16品質管理検定センター(pdf)
引用元:各級の受検者・合格者の年齢別構成|2024/10/16品質管理検定センター(pdf)
合格者の平均年齢はもう少し下がって、1級は31.9歳、2級は33.7歳です。3級と4級はわずかに下がるかあるいは同程度です。
4級の受験生は新入社員や学生も対象として想定していますが、多くは20代後半のようです。
3級も入門級ですが平均年齢は30代半ばです。
平均年齢は高いです。多くの検定試験はここまで年齢層は高くないと思います。
これは、製造業などの現場で、会社の命令で中堅社員が多く受験しているのが理由ではないでしょうか。
品質管理とは、会社である程度実績を積んだ中堅社員に求められている知識であることがわかります。
![]() 参照:受検者データ、学校申込データ|日本規格協会 JSA Group Webdesk
参照:受検者データ、学校申込データ|日本規格協会 JSA Group Webdesk
合格するには

どの級からでも受験可能
品質管理検定は、難易度の低い順に4級、3級、2級、1級(準1級)の4種類です。
準1級は、1級試験の合格基準の一部を満たした受験生が認定されます。
品質管理検定には受験資格に制限がないため、いきなり1級からでもチャレンジできます。
同時に2つの級の受験も可能ですが、隣接する2つの級に限ります。例えば、3級と2級は同時受験可能ですが、3級と1級は受験できません。
それぞれ各級の想定対象者は以下の通りです。職種やポジションによって必要となる知識レベルは異なります。
- 4級 新入社員、学生(大学生・高専生・高校生)
- 3級 全社員、学生(大学生・高専生・高校生)
- 2級 品質にかかわる部署の管理職・スタッフ
- 1級 指導的立場の管理職
4級であれば基本問題ばかりなので難易度は低い
各級の合格率は以下の通りです。
- 4級 85.25%
- 3級 54.57%
- 2級 28.90%
- 準1級 19.34%
- 1級 9.38%
![]() 引用元:申込者数・受検者数・合格者数・合格率」と「学校申込数・学生受検者数|2024/9/1 品質管理検定センター(pdf)
引用元:申込者数・受検者数・合格者数・合格率」と「学校申込数・学生受検者数|2024/9/1 品質管理検定センター(pdf)
4級は常識の範囲で解答できる出題も多く、内容は比較的簡単です。
2時間程度の勉強で合格できる人もいます。
公式サイトで掲載している4級用テキスト(4級の手引き)を数回読んで理解すれば合格に必要な知識は得られます。
※こちらからダウンロードできます。
4級テキスト|日本規格協会 JSA Group Webdesk
「ダウンロードはこちらから」の箇所です。PDFファイルです。
上記の無料テキストだけでも合格できますが、必要に応じて市販の問題集で学習してください。
中堅社員以上であれば、3級からの受験がおすすめ
会社で管理者ではなく一般社員として働いている人、これまで品質管理に携わっていない人であれば、まずは3級からの受験がおすすめです。
3級は4級よりは若干難しいですが、2級以上と違い数学の知識や計算が必要な問題は少ない(多少ある)ので、問題集中心で学習すれば1か月(1日あたり1~2時間)程度の学習で合格できます。
3級はマークシートでしかも意地悪な選択肢もないので、しっかり学習していれば難しくはありません。高校生も取得の対象となっているレベルなので、短期間の独学でも十分合格できます。
また、品質改善だけではなく、ビジネスで要求される顧客満足や製造物責任、環境配慮といった出題もあるので、日頃から新聞やニュースなどの時事問題に注意をはらうと試験対策になります。
3級の出題範囲である「品質管理の手法」では、主にデータの扱いについてと、QC7つ道具、新QC7つ道具についての知識が重要になります。
2級は統計の知識が必要になりかなり難しい!
品質管理検定の2級と3級の難易度の差はかなりあります。
3級は高校生レベルでも受かりますが、2級は統計をはじめ、高校レベルの数学的素養を問われる計算問題が増え、難易度もずっと上がります。
とは言え、そんなに身構えるほどでもなく、数学の知識がほぼない人でもテキストと問題集で2~3か月程度学習すれば合格できます。
数学的知識は全くなくても統計の初歩の知識だけで合格する人もいます。
2級の想定対象者は管理職ですが、数ある資格や検定試験の中でもそれほど難しくはありません。
おすすめの通信講座
JTEXは40年の実績があります。主に企業単位での受講者が多いのが特徴です。
効率よく学習できるように工夫されたテキストで合格に必要な知識が着実に身に付きます。値段もお手頃です。おすすめの通信講座です。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
知識ゼロの全くの初心者から、ある程度品質管理について理解のある人までおすすめのテキスト&問題集です。
全体的に図やグラフなどで色分けされていて見やすいレイアウトになっています。内容も充実していてボリュームもしっかりあります。
ポイントも明確なので、品質管理検定の基本からぶには最適です。この一冊がしっかりと理解できれば合格できます。
| 種類 | 評価 |
| テキスト&問題集 |
多くの受験生が利用しているテキストです。解説が丁寧で分かりやすく要点がまとめてあるので、これ一冊と問題集があれば十分に合格できます。
ただ、解説は丁寧ですが、詳細説明が不足気味です。もう少し詳しい説明があってもよさそうな箇所も目に付きます。
テキストということで問題がほとんど掲載されていません。問題集も必要になります。
上記で紹介している「この一冊で合格! QC検定3級集中テキスト&問題集」の方が評判は良いようです。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
おすすめ問題集
過去6年分が掲載されている過去問題集です。解説も分かりやすいので、短期間で合格を目指す人にはおすすめの1冊です。
職場である程度品質管理の経験のある人であればこの問題集だけでも十分ですが、全くの初心者であればテキストと合わせて学習するのをおすすめします。
3級を受験する人にとっては必須の一冊です。
| 種類 | 評価 |
| 過去問題集 |
おすすめ参考書
トヨタの成功事例、ノウハウが書かれています。おそらく本書の内容を実践できれば生産性は上がるでしょう。
トヨタで求められるのは、仕事の問題点を見つけ、改善し、日々進歩することです。従業員一人ひとりが自分の頭で考え、やりがいをもって仕事をすることです。
若手からベテランまですぐに実践できるノウハウが詰め込まれています。とても参考になります。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
年2回(3月中旬、9月上旬)
お申し込み
申込期限は主催者発表によります。
受験資格
受験資格の制限はなく、どなたでも受験できます。
試験会場
■1級
宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、長野県、静岡市、名古屋市、大阪府、広島県、香川県、福岡県
■2級・3級・4級
札幌市、苫小牧市、青森県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県千葉県、東京23区、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県静岡市、浜松市、豊橋市、西三河、名古屋市、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県
受験料
1級:11,880円
1級(一次免除):9,460円
2級:7,150円
3級:5,830円
4級:4,400円
1級・2級併願:17,050円
2級・3級併願:11,660円
3級・4級併願:9,130円
※2025年3月より適用、他に団体割引あり
試験内容
※下記は3級に関する内容です。
【認定する知識と能力のレベル】
QC七つ道具については、作り方・使い方をほぼ理解しており、改善の進め方の支援・指導を受ければ職場において発生する問題をQC的問題解決法により解決していくことができ、品質管理の実践についても知識としては理解しているレベル。
基本的な管理・改善活動を必要に応じて支援を受けながら実施できるレベル。
試験では【品質管理の実践】と【品質管理の手法】について問われます。
【品質管理の実践】
- QC 的ものの見方・考え方
- 品質の概念
- 管理の方法
- 品質保証:新製品開発
- 品質保証:プロセス保証
- 品質経営の要素:方針管理
- 品質経営の要素:日常管理
- データの取り方・まとめ方
- QC 七つ道具
- 新 QC 七つ道具
- 統計的方法の基礎
- 管理図
- 工程能力指数
- 相関分析
- 品質経営の要素:標準化
- 品質経営の要素:小集団活動
- 品質経営の要素:人材育成
- 品質経営の要素:品質マネジメントシステム
【品質管理の手法】
- データの取り方・まとめ方
- QC 七つ道具
- 新 QC 七つ道具
- 統計的方法の基礎
- 管理図
- 工程能力指数
- 相関分析
※1~3級の試験では電卓が必要です。
3級の場合、3級に加えて4級の範囲を含んだものが3級の試験範囲になります。
![]() 参考:各級のレベルと内容|日本規格協会 JSA Group Webdesk
参考:各級のレベルと内容|日本規格協会 JSA Group Webdesk
試験時間:90分(13:30~15:00)
試験形式:マークシート
合格基準
各分野の得点が概ね50%以上及び総合得点が概ね70%以上
合格発表
試験のおよそ1か月後にWEB合格発表として掲載されます。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は試験要項|日本規格協会 JSA Group Webdeskをご覧ください。
試験に関する詳しい情報は試験要項|日本規格協会 JSA Group Webdeskをご覧ください。
