資格には国家資格・技能検定・民間資格の3種類

資格は、国家資格、技能検定(国家検定)、民間資格の3種類に分類できます。公的資格の制度は既に廃止されました。
![]() 参考:中央教育審議会生涯学習分科会(第20回)-資料3:資格について
参考:中央教育審議会生涯学習分科会(第20回)-資料3:資格について
なお、公的資格の根拠となっていた民間技能審査事業認定制度は2005年に廃止になりました。
したがって、かつて存在していた公的資格は、現在は存在しません。
※文部科学省後援というように公的な「後援」を受けているような資格もありますが、それについては後ほど詳しく説明します。
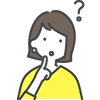
「公的資格」っていう分類があるんじゃないの?
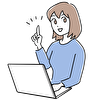
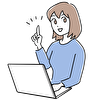
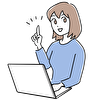
公的資格の制度は2005年に廃止になって今は存在しないのよ!
資格の種類


国家資格
国家資格とは、国の法律に基づいて実施される試験において、知識や技術が一定水準以上に達していると認められた者だけに国が与える資格のことをいいます。
つまり、国家資格には根拠となる法律が必ず存在します。
- 弁護士=弁護士法
- 行政書士=行政書士法
- 電気工事士=電気工事士法
- 基本情報技術者=情報処理の促進に関する法律
- ボイラー技士=労働安全衛生法
国の法律により資格が裏付けられている弁護士、司法書士、宅建士、行政書士、マンション管理士、電気工事士、ケアマネジャー、理学療法士、ボイラー技士などが国家資格に該当します。
介護職員初任者研修などは、厳密に言えば法律で規定されていませんが、法律に準ずる施行規則で規定されているので国家資格の一種と言えます。
現在、国家資格は約305種類あります。
詳しくは下記を参照してください。平成22年12月28日の時点で「303制度」と明記されていますが、それから2種類ほど増えています。。
![]()
![]()
(旧資格一覧はこちら:中央教育審議会生涯学習分科会:国家資格一覧)
※福祉用具専門相談員なども国家資格として掲載されています。
※ファイナンシャルプランナーやキャリアコンサルタントなどは技能検定として扱っているため正確には国家資格ではありません。
国家資格は、天下り団体を創設するための資格制度濫設を防止する観点から、昭和60年度以降、医療・福祉、環境等の分野を除き資格制度の創設は抑制される傾向にありました。
しかし、天下り団体は一向に減らず、国の税制不足を補う目的もあり、平成26年頃から再度国家資格(国家検定)が増えています。
国家資格は一度合格すれば資格は喪失しません。
例えば、行政書士試験に一度合格すれば、その資格は一生涯有効です。
技能検定(国家検定)
技能検定とは、労働者の技能を評価する国の技能検定制度のことを言います。
働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する制度です。
この国家検定に合格しなければ特定の業務に就けないのはなく、その業務に就いている人の技能を判定するという制度です。
簡単に言えば、「あなたはどのくらいその業務に熟練していますか?」という技術力を試す検定試験になります。
試験に合格しても、していなくてもできる仕事は同じです。業務独占資格ではなく名称独占資格です。
技能検定は、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130職種の試験があります。
試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗れます。
国家検定制度は職業能力開発促進法に基づき1959年度より実施されています。国家検定と技能検定は同じです。
民間資格(検定試験)
個人や民間の団体・企業が自由に名称を決めて、受験生を集めて試験を実施しているのが民間資格(検定試験)です。認定資格とも呼ばれます。
特にルールや法律による規制はないので、自由に誰でも資格らしいモノを作れます。
このように法律の根拠のない民間資格は全て検定試験にあたります。
資格と称していますが、厳密にいうと資格でもなんでもないです。
商標登録された固有名詞の使用権の販売にすぎないということです。
民間資格と言っても種類は多く、約4,000以上あると言われています。
代表例は簿記検定、秘書検定、漢字能力検定、英検、TOEICなどです。
さらには、医療事務、調剤薬局事務、心理カウンセラーなどの民間資格も存在します。
単なる趣味の検定試験である場合がほとんどで、多くの民間資格は取得する意味はありません。
民間資格の中には、教材の販売、通信講座受講を目的としたものもあるので要注意です。
広い意味で、お茶やお花といった師範の資格も民間資格に含まれます。
公的資格(旧認定資格)について


省庁が認定する公的な民間資格の制度は廃止されました
「公的資格とは?」って思われる人もきっと多いと思います。
以前は、簿記検定、秘書検定、漢字能力検定のように、関係省庁(国)から認定を受けている公益法人が実施する公的な検定試験制度がありました。
しかし、以前より制度の不備や不適切な会計処理(天下り団体と民間団体の癒着)が問題になっており、その結果、2005年にそれまで公的資格の根拠となっていた民間技能審査事業認定制度は廃止になりました。
2.平成14年3月29日の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革の実施計画」により、民間技能審査事業認定制度の推薦等は、平成17年度末までに一律廃止することとされた。
出典:中央教育審議会生涯学習分科会(第20回)-資料3:資格について
したがって、「国の認定」の制度が廃止された今は「旧公的資格」は存在しますが、現在のところ公的な価値を持つ民間資格は存在しません。
民間団体が実施する検定試験には法的な根拠はなく、公的資格は存在しないということです。
「後援を受けた公的資格」という表現をよく目にしますが・・・
ところが民間の検定試験について、主催者のホームページなどの説明文を読むと、大々的に「公的資格」とうたっているものをよく目にします。
認定資格、省庁後援という表現も同じです。
この公的資格の根拠は何かというと、経済産業省、文部科学省、中小企業庁などの省庁の後援のもとに実施している検定試験だからということです。
中には、総務省後援、文部科学省後援、経済産業省後援、内閣府後援、厚生労働省後援・・・と5省庁から後援を得ている民間資格もあります。
省庁が「認定」する制度はなくなりましたが、省庁が「後援」する制度は現在も存在します。
どうやらこの「省庁の後援」をもって公的資格と主張しているようです。
民間の検定試験の枠を超えた国も認めている公的な試験という権威付けを強調したいんでしょうけど、はたしてどれくらい国が関与しているのか調べてみました。
すると、文部科学省のサイトに「後援」をもらうための説明書きがありました。詳しくは下記をご覧ください。
実はこの「後援」とは、PRするために「省庁の後援名義を使っていいですよ」という程度のもので、省庁に申請すれば明らかなインチキ資格商法でない限り簡単に使用許可がおりるようです。
積極的に省庁が資格として認めて、法律的な根拠を与えているワケではありません。
税金を使って資金的なの援助をしていたり、合格者を優遇しているワケでもありません。
積極的な支援などは一切していません。
それだけのことを大袈裟に公的資格というのは明らかに誇大表示と言えます。
認定資格でもなんでもないんです。
公共性の高い民間資格は存在します
かつての文部科学省の認定制度の名残りで、極めて公共性の高い民間資格は現在も存在します。
例えば、簿記検定や臨床心理士などです。
簿記検定の1級合格者は国家資格である税理士試験の受験資格を得られます。
福祉住環境コーディネーターの2級以上を取得すると、介護保険を利用して住宅改修をおこなう際に提出する住宅改修費支給申請書に添付する理由書の作成ができます。
臨床心理士は文部科学省の任用規程により、全国のスクールカウンセラー(学校カウンセラー)になるための資格要件とされています。
その他、大学・短大で入試の際に評価される民間の検定試験などがいくつかあります。
法令の根拠があるということは、民間資格というよりも国家資格の色合いが強いともいえます。
