認知症ケア専門士は専門性が高く評価する施設もある
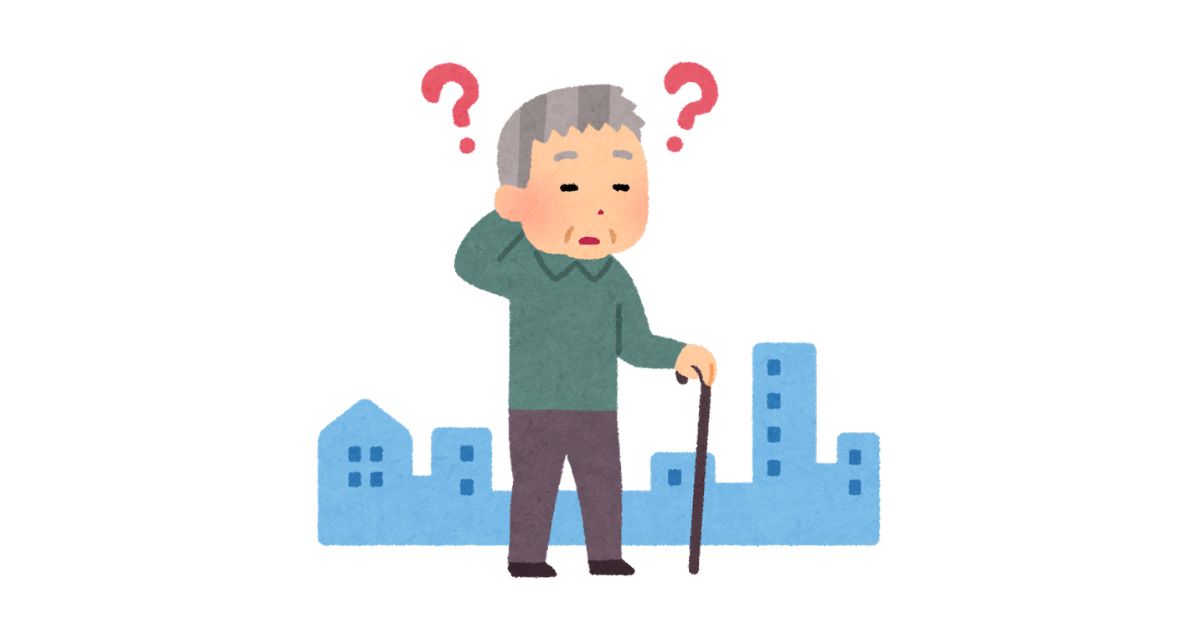
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | やや易 | 50% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 実務経験必要 | ~2万円 | 3か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | 評価 |
| スキルアップ | 29件 |  |
- 受験するには認知症ケアの実務経験が一定年数必要です。
- 全国の求人数は、ハローワークの求人情報を基に2026年1月30日に集計しました。
| 試験の級 | 他に、上級専門士、准専門士 |
| 講座受講料 | 標準テキスト5冊:11,000円(税込) 受験対策講座:15,000円(任意) |
| 受験料 | 一次試験:3,000円×受験分野数(4分野で12,000円) 二次試験:8,000円 |
| その他費用 | 登録申請料:15,000円 更新料/5年: 10,000 円 |
※金額は2026年1月現在です。
認知症ケア専門士とは日本認知症ケア学会が主催する民間資格です。
専門性が高く、合格すれば認知症患者の介護やケアに関してすぐれた技術を有していると認められます。
一部ですが資格手当を支給する介護施設もあります。
ただし、受験料・登録料・更新費が安くないため、目的がはっきりしなければ更新する必要はなさそうです。
認知症ケア専門士とは

認知症に関する民間資格
認知症ケア専門士とは、2005年に始まった一般社団法人日本認知症ケア学会が主催する民間資格です。
専門性が高く、合格すれば介護施設などでは一定の評価を得ます。認知症患者の介護やケアに関してすぐれた技術を有していると認められます。
身内で認知症の疑いのある高齢者がいると、本人はもとよりその家族は今後の日々の生活場面でいろいろな不安を感じることも多いでしょう。どう接していけばよいのか戸惑い悩まれることも多いと思います。
そんなときは、認知症ケア専門士へ相談をして専門的なアドバイスをしてもらい、今後の療養に役立てられます。
![]() 主催者サイト:認知症ケア専門士|公式サイト
主催者サイト:認知症ケア専門士|公式サイト
役に立つ資格なのか?

合格者を高く評価する介護施設も
認知症ケア専門士の受験資格を得るには、概ね過去10年間に3年以上の実務経験が必要となります。
合格者は、同時に現場経験者ですから就職や転職はかなり有利になります。面接で特に問題がなければ速攻で採用になるでしょう。
もっとも超人手不足の業界ですから、資格の有無など関係なく採用になる可能性は高いですが・・・
認知症ケア専門士は民間資格ですから、介護の事業所に必ず有資格者がいなければならないような配置義務はありません。
そのため、資格手当を支給する施設はとても少ないです。
1,000~5,000円ほど支給する施設も見つかりますが、だいたい2,000円ほどです。
管理職になるために必須だったり、あるいは資格手当が支給されるようであれば取得する価値は十分あります。
将来性について徹底研究

知名度が高いため自己PRに使える
認知症ケア専門士を受験する人の多くは施設の管理職候補です。あくまでもスキルアップのための検定試験です。
資格試験の学習を通して得た知識は自分の自信につながります。それが結果的には認知症の患者さんに対する適切なケアに結び付けば勉強するメリットは十分にあります。
資格の更新の際に日本認知症ケア学会が主催する研修や講義などを受講しなければなりませんが、認知症を理解する上でとても役に立ちます。
認知症ケア専門士は知名度は高いです。そのため、履歴書に書けばステップアップするための転職の際に役立ちます。
取得と更新のための費用
認知症ケア専門士は、資格の取得とその後の資格の更新のための費用が必要となります。
例えば、まずは試験を受けるためには「受験の手引き(願書)1,000円」が必要です。
受験のためのテキストが日本認知症ケア学会から公式テキストとして出版されていますが、標準テキスト5冊を全部そろえると10,000円以上します。
受験対策講座を受講すると参加費は2日間で15,000円です
第1次試験の受験料は1分野につき3,000円、4分野で12,000円が必要です。
さらに第2次試験の受験料が8,000円。合格したら今度は登録料で15,000円が必要になります。
登録料って独占業務が伴う国家資格なら分かりますけど、民間資格で登録料って何?って気はしますけど・・・
登録後も資格を更新するためには、資格取得後の5年間で日本認知症ケア学会が主催する講座や認定する他の団体が開催する講座に参加して30単位以上を取得する必要があります。
もちろん講座は有料です。更新料も10,000円必要です。
認知症ケア専門士の資格は、取得するにも維持するにも安くないお金が必要です。
勤めている施設で資格手当が支給されなければ取得するのはよく考えた方がよさそうです。
施設側で負担してくれたらベストです。
※金額は2026年1月現在です。
合格するには
認知症ケア専門士の受験資格を得るためには、3年以上の認知症ケアの実務経験が必要です。
そのため、受験生は現場で直接認知症ケアに携わっている人がほとんどです。
認知症ケア専門士の勉強方法としては、以下2つのパターンがあります。
- 市販のテキストなどを購入し独学で勉強する方法
- テキストの学習+主催者である日本認知症ケア学会が主催する対策講座を受ける
独学での勉強とはいえ、仕事である程度の知識がある人がほとんどですから、市販のテキストでも1か月程度の学習で十分に合格は可能です。
合格率は50%ほどです。
テキストは公式テキストである「認知症ケア標準テキスト」のほか、数種類の問題集やテキストが出版されています。
試験前には、主催者である日本認知症ケア学会と特定非営利活動法人認知症ケア教育機構が主催する受験対策講座が開催されます。
大勢の参加を募るためにかなり本試験の内容に近い解説が聞けるようです。
受験対策講座は5月ごろに2日にわたっておこなわれます。
なんとしても合格したい人にはおすすめです。
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
【1次】7月中旬
【2次】11月下旬~12月初旬
お申し込み
【1次】3月中旬~4月中旬
【2次】8月中旬~9月中旬
受験資格
過去10年において3年以上の認知症ケアの実務経験が必要です。
※ボランティア活動や実習は、実務経験に含まれません。
試験会場
WEB試験(パソコン等を使用しインターネット上で行う試験)
受験料
第1次試験:3,000円×受験分野数(4分野で12,000円)
第2次試験:8,000円
試験内容
【第1次認定試験】:筆記
[試験分野]
- 認知症ケアの基礎
- 認知症ケアの実際Ⅰ:総論
- 認知症ケアの実際Ⅱ:各論
- 認知症ケアにおける社会資源
試験時間:各60分
問題数は各50問ずつで4分野すべてで200問(マーク式・五肢択一)、各分野とも70%以上の正答率で合格です。
第1次認定試験では各分野の合格有効期限が5年間と定められています。5年間のあいだに4分野合格できれば、次の第2次認定試験に進めます。4分野すべての合格をもって第1次試験の合格となります。
受験料:3,000円×受験分野数(4教科で12,000円)
【第2次認定試験】:論述・面接
第1次認定試験の合格者(各分野の合格有効期限は5年間)のみ第2次認定試験に進めます。
- 論述:出題される事例問題に対する論述
- 面接:6人を1グループとした面接(当日発表するテーマに合った個々の1分スピーチと約20分のディスカッション)
[論述・面接の総合評価により、次の5つの要件を満たす者]
- 適切なアセスメントの視点がある
- 認知症を理解している
- 適切な介護計画を立てられる
- 制度および社会資源を理解している
- 認知症の人の倫理的課題を理解している
合格基準
第1次試験:各分野70%以上の正解。4分野全て合格で1次合格。
第2次試験:論述の評価により要件を満たした者。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は試験概要:受験資格|認知症ケア専門士認定試験をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は試験概要:受験資格|認知症ケア専門士認定試験をご覧ください。
