公認会計士とは?独立も可能で転職にも活かせる難関資格
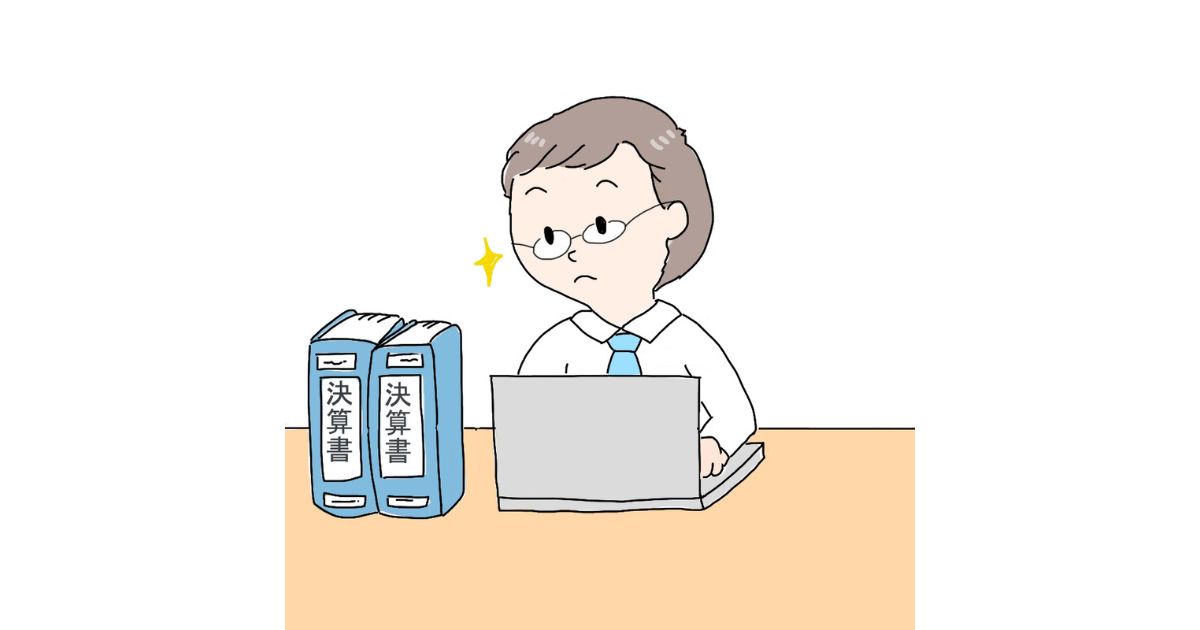
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | 超難関 | 10% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | 50万円~ | 3年以上 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 229件 |  |
- 合格率は(最終合格者数/願書提出者数)です。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月25日に集計。
公認会計士の主な業務は企業の監査です。
企業が作成した収支に関する帳簿(財務諸表)が適正であるかどうかを第三者の立場からチェックします。
難易度は高く、独学での合格は困難です。
合格後の就職先は監査法人か公認会計士事務所などです。
高い合格率が見込めるおすすめの通信講座
公認会計士とは

主な業務は企業の監査
公認会計士と税理士はどう違うの?
多くの人からこんな質問をよくいただきます。
公認会計士と税理士は、どちらも税務や会計などに関する業務が中心という点で共通しているため、はっきりと違いが分からないのは無理もありません。
実は公認会計士と税理士はれぞれに別に独占業務があり、企業から依頼を受ける業務の内容も大きく異なります。
公認会計士の主な業務は企業の監査です。企業が作成した財務諸表(収支に関する帳簿)が適正であるかどうかを第三者の立場からチェックします。
一方、税理士の主な業務は企業の税務です。企業(あるいは個人)の依頼により、企業側の立場に立って節税などの相談にのりながら、税務に関する書類を作成し税務に関する申告を行います。
公認会計士:企業の監査
税理士 :企業や個人の税務
節税や税務に関する相談は税理士の独占業務であり、税理士にしか出来ない業務です。
![]() 関連資格:税理士とは
関連資格:税理士とは
公認会計士は「監査」、税理士は「税務」という根本的な違いがあります。
ただ、公認会計士は必要な手続きをすれば税理士としての業務も行えますので、公認会計士は税理士の業務にプラスして企業監査をおこなう専門家といえます。
![]() 関連団体:公認会計士とは|日本公認会計士協会
関連団体:公認会計士とは|日本公認会計士協会
役に立つ資格なのか?

現在はかなりの売り手市場
公認会計士は、企業の監査業務を独占しておこなうという社会的に重要な意義のある国家資格です。
合格するには難関な国家資格に合格しなければなりません。
公認会計士試験に合格した後の就職先は監査法人か公認会計士事務所がほとんどです。
ある一時期の2~3年間、社会情勢により極端に就職状況が悪かった時期がありました。その頃大手の監査法人では、採用どころか現役の公認会計士をリストラしていたようです。
まぁそんな頃はどこの会社も同じようなことはしていたので、監査法人だけが特別だったわけではありませんけどね。
今現在(2025年)はどちらかというと公認会計士試験合格者は売り手市場です、というかかなりの人手不足です。
監査法人はリストラをしていた頃に比べると慢性的な人手不足に陥っており、公認会計士試験合格者はほぼ受け入れている状況にあります。
大企業の決算書をチェック
公認会計士の主な業務は監査業務だということは既に説明しました。
法律により公認会計士による監査を受ける義務がある企業は、資本金5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の株式会社です。
そのため公認会計士のクライアントは主に大企業となります。
では、この監査業務がどういう意味を持つのかというと、日本の株式市場を支える重要な裏方の仕事といえます。
公認会計士は、上場企業などが作成した決算書などの財務諸表の内容に間違いが無いかをチェックします。
内容に問題がないと判断したらその企業の財務状況が全てわかるので、投資家が決算書の内容に基づいてその会社の株を購入するなどの投資活動を行うことができます。
もし会社の作った決算書を公認会計士がチェックしないとなると、決算情報を会社側で操作することが簡単になります。
数字を書き換えることによって、本当は赤字なのに黒字に見せかけて会社の価値すなわち株価を維持することができます。
かつては東芝のような巨額な粉飾決済が社会問題化しました。オリンパスや少し前のカネボウも粉飾決算で世間を賑わせました。
これは株主や世間を欺くいわば詐欺行為とも言える手段です。
その都度話題になるのが公認会計士の存在です。
公認会計士は企業の監査を行うことで誰もが公平に企業の実態にあった投資を行えるよう、フェアな市場を提供する役割を担っています。
上記の例は、主に上場会社に義務付けられている金融商品取引法監査(金商法監査)といいます。
参考:会計・監査用語かんたん解説集:金融商品取引法監査 | 日本公認会計士協会
将来性について徹底研究

活躍の場が広く独立も可能
公認会計士の資格は、活躍の場が広いのが特徴です。
まず公認会計士試験に合格したら一旦監査法人や公認会計士事務所に就職する場合がほとんどです。
そこで業務補助期間(3年)が終了して、一定の手続きが済めば正式に公認会計士と名乗れるようになります。
名刺に公認会計士と書いてあるだけで相手の態度はそれまでと豹変します。
大企業の役員や監査役と一緒の車に乗って経営について話しをすることができるようになります。
それどころか食事や飲み会の席に招待されるようにもなります。
公認会計士という肩書が最大の武器になり威力を発揮します。
その後は監査法人で実力が認められて高給取りになる人もいれば、会計事務所として独立する人もいます。
公認会計士として一般企業に勤務することもできます。
※業務補助に携わる期間は公認会計士試験合格の前でも後でも時期は問われません。
公認会計士は本当に高収入なのか?!
「公認会計士は独立可能で40代で数千万円といった高収入も可能!」なんて資格を紹介するサイトや予備校のパンフで紹介されていますが、本当にそうなんでしょうか。
まず、公認会計士試験に合格すると、公認会計士事務所や監査法人に就職する場合がほとんどです。
採用時の初任給は400~500万ほどなので確かにその場合の初任給は大企業に新卒で入るよりも高めです。
しかし、その後は資格を持っているだけで給料が順調に上がっていくわけではありません。
当然ですが給料が上がるのは実力次第です。
公務員のように年功序列で給料が上がるわけではありません。
もちろん資格を有していないスタッフと比べると競争は有利です。資格手当てなども支給されます。
しばらくは多くのスタッフの中の1人として働き、その後、実力が認められればマネージャー(責任者)などの管理職に昇格します。
それにともなって給料も上がるということです。
実力がなければ普通の大企業に勤務するサラリーマンと給料が変わらない可能性も十分にあります。
独立するなら税理士としての場合がほとんど
公認会計士の資格を紹介しているサイトを見ると、「独立可能な資格」とよく紹介されていますが、公認会計士とし独立する人はごく少数です。
ご存知の通り公認会計士のメイン業務であり独占業務でもあるは監査は、法律上監査を義務付けられている上場企業や大会社になります。
そんな大企業が、個人で独立したばかりの事務所に監査の依頼をするなんてことはほぼないでしょう。
実情は、監査法人を退職して独立している公認会計士は、税務業務をしている場合がほとんどです。
公認会計士として登録をすれば税理士の資格も取得できるため、公認会計士の名称も名乗りつつ税理士として独立するわけです。
地方へ行くと、公認会計士兼税理士事務所の看板を見かけるのはそのためです。
かつての公認会計士補の制度は廃止
平成18年までは、公認会計士試験に合格しても、その後、公認会計士補として2年以上監査法人等で経験を積まないと正式に公認会計士になれませんでした。
しかし、不況により監査法人が新規で公認会計士試験合格者を採用する余裕がなくなり、また、試験制度の変更により合格者が増えたこともあり、せっかく合格しても公認会計士になれなくて困っている人が増え社会問題化しました。
平成22年から23年にかけて金融庁が公認会計士試験合格者を対象に調査したところによると、監査法人に内定している人の割合が56%という低い数字で、いかに監査法人に就職するのが狭き門であったかがわかります。
これでは合格者数を増やした意味もありません。
せっかく難関の試験に合格しても公認会計士になる道は閉ざされたままです。
そこで、日本公認会計士協会の実施する実務補習を修了すれば晴れて公認会計士になれる制度に改められています。
合格するには
独学では合格は難しい
公認会計士試験は平成18年から年齢や学歴要件などの受験資格がなくなりました。
そのためどなたでも受験が可能です。最近では18歳で合格した人もいます。
公認会計士試験に合格するにはまずはどこかの資格予備校に通うことです。
合格者のほぼ100%は資格予備校のお世話になっています。独学で合格は困難なようです。
通学であれ通信講座であれ、安くない授業料は覚悟しておいた方がいいでしょう。
短答式試験と論文式試験の2種類
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験に分かれています。短答式試験は年2回、12月(第Ⅰ回)と5月(第Ⅱ回)に実施されます。
そのどちらかに合格すれば8月に実施される論文式試験へと進みます。論文式試験を合格すれば公認会計士試験合格となります。
その後、実務補修・修了考査合格・業務補助等の実務経験を経て公認会計士として登録ができるようになります。
短答式試験とは、財務会計論(簿記・財務諸表論)・管理会計論・監査論・企業法の4科目で、解答はマークシートの択一式です。第Ⅱ回よりも第Ⅰ回の方が合格率は高く、合格者の多くは第Ⅰ回の短答式試験で合格します。
論文式試験とは、短答式試験の4科目に租税法と選択科目をくわえた6科目で、記述式です。
短答式試験に一度合格するとその後2年間は短答式試験が免除されます。一度短答式試験に合格すれば論文式試験に3回チャレンジできるということです。
論文式試験においては一部科目免除の制度があります。論文式試験は基本的に6科目の総得点で合否が決まりますが、6科目の合計では合格できなかったとしても、一部の科目で相当の順位を獲得していれば2年間の科目免除を受けることができます。
仮に、2科目の科目免除を受ければ、その後2年間は残りの4科目の勉強に専念できます。
このような短答式試験の2年間の免除も、論文式試験における一部科目の免除も、不合格者の救済措置という意味合いから導入されました。
税理士試験は年数に制限がない永久的な科目合格制度となっていますが、公認会計士試験は年数に制限があるので注意が必要です。
仕事をしながら合格できるのはごく少数
資格予備校の広告では「働きながら公認会計士の試験に合格!」なんて無責任な記載を目にしますが、仕事をしながら合格できる人は少数です。
業務に精通した税理士が朝から晩まで学習して公認会計士の試験を受験しても1~2%しか合格できないというのが現実です。
超難関国立大学に現役合格したような人が朝から夜中まで自宅にこもっても勉強しても多くが落ちる試験です。サラリーマンであれば退職して学習に専念しなければ合格できません。
とはいうものの、公認会計士試験は努力次第で合格できる試験です。
免除制度を利用すれば、以前ほど超難関というわけでもなく、本気で朝から深夜まで学習すれば2年間で合格できる可能性は十分にあります。
論文式の試験があるため、第三者に解答を採点してもらう必要があります。やはり独学では難しいので予備校か通信教育で学習をするのがおすすめです。
まずは無料の資料請求
おすすめの通信講座
資格予備校は多くありますが、それぞれ特徴があり、予備校によって圧倒的に得意な分野があります。公認会計士の講座といえば、東京CPA会計学院です。
東京CPA会計学院はとにかくその実績が素晴らしく、公認会計士の受講生の合格率は毎年40%を超えています。2021年は510名が合格したといいますから驚きの数字です。なかなか合格者を輩出できず撤退する予備校も多い中、長年に渡って高い合格率を維持し続けています。
一般的な資格予備校では、講師への質問は18:00までと時間が限られています。これでは社会人は質問がしたくてもなかなかできません。東京CPA会計学院であれば、公認会計士合格者の専任講師が待機しているので、いつでもどんな質問でも対応してくれます。
他の予備校から東京CPA会計学院へ乗り換える受験生も多くいます。
学習の方法は通学と通信講座があります。まずは資料請求をして詳細をご確認ください。アガルートアカデミーとCPA会計学院が業務提携した講座です。
※こちらから受講申し込みができます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
公認会計士について興味はあるけど、どんな仕事内容なのか、税理士とどう違うのか、などと具体的なイメージがわかない人を対象に書かれています。
また、学習方法についても書かれているので、これから学習をはじめようと考えている方や現在学習中の方にもおすすめです。
一時は合格者が過剰とも言われていた公認会計士ですが、合格後の選択肢や公認会計士の実情が詳細に書かれています。この点においても必読の参考書といえます。
何か漠然と資格を取りたいと思っている人にもおすすめです。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
【短答式】:第Ⅰ回試験:12月、第Ⅱ回試験:5月
【論文式】:8月下旬の金曜~日曜の3日間
お申し込み
短答式試験Ⅰ:9月上旬~中旬
短答式試験Ⅱ:2月中旬~下旬
受験資格
受験資格の制限はありません。どなたでも受験できます。
試験会場
北海道、宮城、東京、石川、愛知、大阪、広島、香川、福岡、熊本、沖縄
受験料
19,500円
試験内容
【短答式試験】
- 会社法
- 管理会計論
- 監査論
- 財務会計論
総点数の70%が基準点です。ただし、一科目40%に満たないと不合格の可能性もあります。
【論文式試験】
必須科目と選択科目があり、合計9科目です。
- 必須科目:財務会計論(簿記・財務諸表論)、管理会計論、監査論、企業法、租税法
- 選択科目:経営学、経済学、民法、統計学 ※この科目から1つ選択
合格基準
52%が基準点です。ただし、一科目40%に満たないと不合格の可能性もあります。
合格発表
短答式試験Ⅰ:1月
短答式試験Ⅱ:6月
論文式試験:11月
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は公認会計士・監査審査会/公認会計士試験をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は公認会計士・監査審査会/公認会計士試験をご覧ください。

