毒物劇物取扱責任者の試験は共通化され難易度の差は少ない
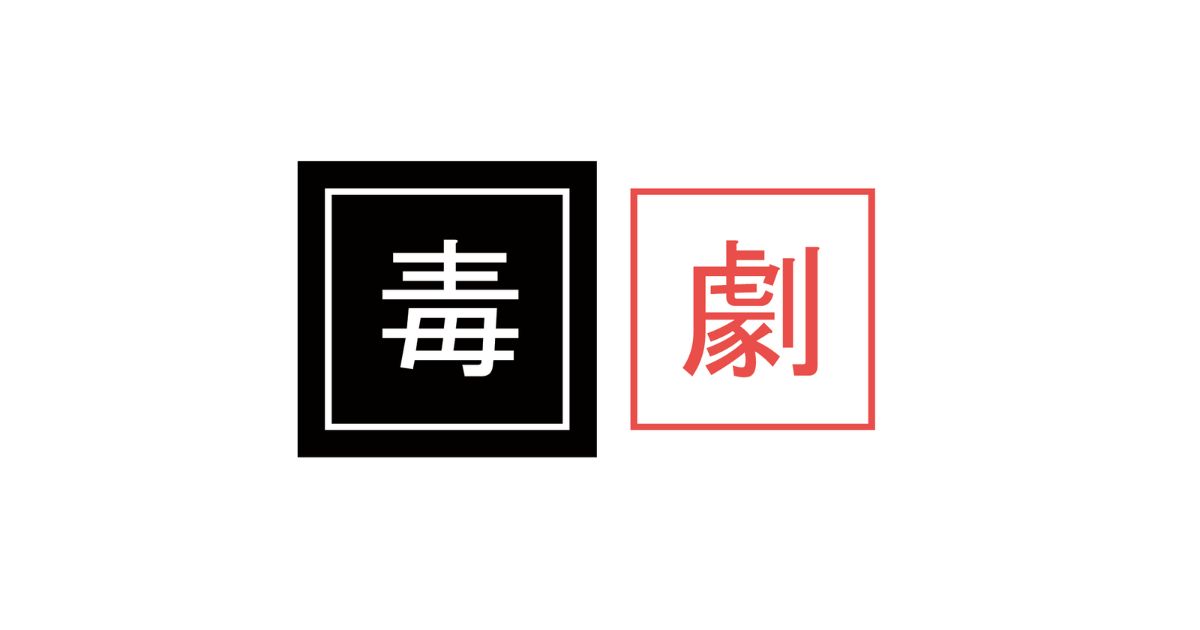
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | やや易 | 40~50% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 3か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 176件 |
- 試験を実施する都道府県ごとに合格率は異なります。
- 種別によって合格率は違います。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年4月15日に集計。
毒物劇物取扱者試験は、都道府県によって試験の内容や難易度が違っていましたが、最近は地域で共通化をしており差はほぼなくなっています。
試験には種別が3種類ありますが、どれも問題の難易度は変わらないので全品目を扱える「一般」を受験するのがおすすめです。
求人数は全国的にも少なく、就職や転職が有利になる資格ではありません。
高い合格率が見込めるおすすめの通信講座
毒物劇物取扱責任者(毒物劇物取扱者試験)とは

毒物劇物を扱う事業所には必須
日常的に、毒物劇物を原材料として使用したり、運送したり、自分で使用する会社や事業所は、その旨を保健所に届け出なければなりません。
このような事業者は、営業所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を1人選んで、その者を届け出ることを義務づけられています(※専任:常時その施設に勤務している社員、他社との掛け持ちはダメということ)。
毒物劇物取扱責任者は、事業所で取り扱っている毒物劇物の種類・量・取扱方法を把握し、保管管理・取り扱いについては法律に基づき適正に行わなければなりません。
毒物劇物取扱責任者は、安全面の管理や保健衛生上の危害の発生を防止します。
一部出典:毒物・劇物取り扱いのしおり(pdf)
(※良くまとまった資料です、参考にしてください)
毒物劇物とは何か?
では、毒物劇物とは一体何か?
「毒物及び劇物取締法」という法律では、人や動物が飲んだり、吸い込んだり、あるいは皮膚や粘膜に付着した際に生理的機能に害を与える化学物質等について「毒物及び劇物」として保健衛生上の観点から取扱いを規制しています。
そして、毒物及び劇物を、毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類しています。
例えば毒物は、毒物及び劇物取締法別表第一で掲げられる物質で、シアン化ナトリウム・黄リン・水銀・ヒ素などがあげられます。
劇物は、同法別表第二で掲げられる物質で、メタノール、二硫化炭素、発煙硫酸などです。
聞いただけで少し怖いイメージのある毒物や劇物ですが、実は私達の身近に普通に存在します。
よく利用される代表例はなんと言っても農薬です。
殺虫剤や肥料などの農薬には毒物や劇物が含まれています。農薬を利用するのは一般的で、利用しないとまともに収穫ができません。
農薬以外では、塗装にも多くの毒物や劇物が含まれています。
選任されてはじめて毒物劇物取扱責任者と名乗れる
毒物や劇物の取扱いには細心の注意が必要です。
盗難などにより犯罪に悪用されるケースにも警戒しなければならないことから、その取扱等について「毒物及び劇物取締法」で規定しています。
この毒物劇物取扱責任者には誰でもなれるワケではありません。
毒物劇物取扱責任者に選ばれるための条件の1つが「毒物劇物取扱者試験に合格した者」です。
つまり、毒物劇物取扱者試験に合格すれば無条件で毒物劇物取扱責任者になれるのではなく、事業者に選任されてはじめて毒物劇物取扱責任者と名乗れます。
毒物劇物取扱者試験に合格しただけでは、単に「毒物劇物取扱責任者の有資格者」あるいは「毒物劇物取扱者試験の合格者」にすぎません。
試験合格を目指す人はその点注意が必要です。
役に立つ資格なのか?

就職や転職が有利になるとまでは言えない
実は、毒物劇物取扱者試験の合格者の求人は、就職・転職サイト、ハローワークなどを探してもほとんど見つかりません。
しかも募集しているのがほとんど地方で、都会ではめったに見つかりません。
毒物劇物の製造・輸入・販売を行う会社や事業所では毒物劇物取扱責任者は必要です。
農薬の販売店などでも需要がありますが「責任者」として店舗に1名いれば足ります。
難易度もそれほど高い試験ではないので、いざとなれば社員に取得させればすみます。
社内に要件を満たす社員がいれば選任できます。
毒物劇物取扱者試験に合格しても就職や転職に役立つとまでは言えません。
履歴書に書いてもそれほど有利にはならないでしょう。
化学系学科の卒業生が毒物劇物取扱責任者になる資格を有していることは企業側は充分理解しているので、新卒者でも特に就活する上でのメリットはありません。
資格だけ持っていても現場ではやはり実務経験が必要です。
応用化学に関する学課のある大学か高校を卒業しているだけで毒物劇物取扱責任者になるための要件を満たしています。
意外と有資格者が多いのが現実です。
将来性について徹底研究
この資格の活かし方
毒物劇物取扱責任者の有資格者が活躍できる場所は、化学薬品の製造業、製薬業、塗料の工場などです。
電気鍍金(メッキ)工場、金属熱処理工場、農薬や肥料等を扱う専門店など、毒物劇物を扱う会社や工場は意外と多く、資格を活かせます。
薬品類を輸入する会社でも毒物劇物取扱責任者は必要とされています。
毒物劇物取扱者試験の勉強を通して「法規面」の知識が身に付きます。
学校卒業の有資格者は「法規面」についての知識がどうしても少ないので、その点は試験の勉強をするメリットがあります。
また、化学系の工場などで働く場合は、毒物劇物の性質などを理解しておくといざという時に対処できます。
毒物劇物取扱者試験に合格すれば「有資格者」として履歴書にも書けます。試験に合格すればそれなりに活かせる資格です。
一部の者は無試験で毒物劇物取扱責任者になれる
毒物劇物取扱責任者になるには国家試験に合格するのが一般的な方法ですが、次の者は既に「毒物劇物取扱責任者」の資格があるので受験する必要はありません。
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
![]() 参考:応用化学に関する学課を修了した者とは 東京都福祉保健局
参考:応用化学に関する学課を修了した者とは 東京都福祉保健局
薬剤師であれば毒物劇物取扱責任者になる資格を有します。
大学で応用化学に関する学課を修了した者であれば毒物劇物取扱責任者になる資格を有します。
高等専門学校、工業高校で主に化学を専攻する学科を卒業した者であれば毒物劇物取扱責任者になる資格を有します。
薬剤師は薬剤師免許証、大学・高校卒業者は、卒業証明書、成績証明書、単位取得証明書などを提出して証明します。
上記の有資格者は、毒物劇物取扱責任者の免許が交付されるワケではありません。あくまでも毒物劇物取扱責任者に選任される要件を満たしているということです。
受験するなら「一般」がおすすめ
毒物劇物取扱者試験には種別が3種類ありますが、それぞれ扱える毒物及び劇物が違います。
- 一般・・・全ての毒物・劇物
- 農業用品目・・・農業に関する品目限定
- 特定品目・・・特定の一部毒物・劇物
一般に合格すれば、毒物又は劇物の全品目を扱う責任者になれますが、他は扱える毒物及び劇物が限定されます。
どれを受験すればよいのか・・・もちろん全品目を扱える一般を受験するのがおすすめです。
理由としては、どれも問題の難易度が変わらないからです。
過去問を見れば分かりますが、農業用品目と特定品目は扱える毒物劇物が限定されるので若干出題範囲は狭くなりますが、だからといって問題は簡単にはなってません。
わけのわからない農薬が出題されて、かえって難しくなるケースもあります。
実際に多くの受験生が一般を受験します。
「簡単な県(地域連合)」で受験すれば合格しやすい?
毒物劇物取扱者試験の最も大きな特徴は、都道府県によって試験全般が異なる点です。
試験の実施日も違えば、試験の内容や難易度、出題傾向も違います。
都道府県によって出題数も違います。4択の問題もあれば5択も、○×方式、多肢選択式もあります。
長文の文章問題もあれば、単純な知識問題程度の出題もあります。
つまり、試験が簡単な県で受験すれば、合格できる可能性が高いということです。
毒物劇物取扱者試験は、どこの都道府県でも受験できますし、合格すれば全国で有効です。
過去問を調べて自分が合格できそうな地域を選んで受験するのも良いでしょう。
ただし、地域で試験問題を共通化する動きが顕著で、以前のような難易度の差は近年なくなりつつあります。
※関西であれば、毎年のように京都府が最も難易度が低い「簡単な県」という評判でした。
しかし、残念ながら令和元年度から滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の毒物劇物取扱者試験に関する業務は関西広域連合で実施する運びとなりました。
上記6府県は統一の試験となって難易度の差はなくなりました。
危険物取扱者乙4とどちらがおすすめ?
毒物劇物とよく似た国家資格が危険物取扱者です。
取得するならどちらがおすすめか、という点について考えてみます。
まず、毒劇物取扱責任者と危険物取扱者乙4、どちらが難易度が高いのか?
一般的に毒物劇物取扱者試験の方が難易度は高いと言われています。
化学に関しては、毒物劇物取扱者試験の方が一歩踏み込んだ知識が求められます。
対象物質が非常に多いというのが毒物劇物取扱者試験の方が難易度が高いと言われる理由です。
合格率に関しては、毒物劇物取扱者試験は都道府県で差はあるもののどちらも合格率は大差ないです。
試験の難易度という点では危険物取扱者の方が取得しやすいようです。
ちなみに、甲種危険物と毒劇物を比較すると、甲種危険物の方が圧倒的に難しいと言われています。
どちらが就職や転職に役立つかというと、それは危険物取扱者の方が圧倒的に役立つようです。
例えば乙4に限っても、求人数は毒物劇物取扱者の比ではなく圧倒的な数です。
どちらか挑戦してみたいのであれば危険物取扱者の方がおすすめです。
余談ですが、危険物取扱者試験に合格すれば、申請によって都道府県知事から危険物取扱者免状が交付されます。
免状は運転免許証と同じサイズで持っているとカッコいいです。
一方、毒物劇物取扱者試験に合格すると、合格証は交付されますが免状などは発行されません。
合格するには

難易度としては、知識ゼロなら3か月の勉強で合格
毒物劇物取扱者試験に合格するには化学の知識が要求されますが、ほとんど知識ゼロであったとしても1日2時間の学習で3か月~6か月ほどで合格できます。
もちろん化学の知識があれば、さらに短期間で合格は可能です。
高校レベルの化学の知識があれば基礎化学に関しては理解が早いでしょう。
知識がなかったとしても市販のテキストでコツコツと学習すれば理解できます。
自信がない人は、高校化学のわかりやすい参考書を1冊読み込むのもおすすめです。
学習方法のポイント
毒物劇物は、医薬品以外のもので毒性の強い順に分類すると以下の通りになります。
特定毒物 > 毒物 > 劇物
毒性に関して基本は、毒物>劇物であって、特に毒性の強いものを「特定毒物」に指定し、特定毒物はその取扱いを厳重に定めているという前提をよく理解して学習をすすめてください。
これを理解しないと混乱します。
ただ、一旦頭に刷り込んでしまえば、そのあとは難しく感じないはずです。
毒物劇物取扱者試験は覚える内容がかなり多いです。
聞いたこともないような物質やとても長いカタカナの物質名も出てくるので根気よく繰り返し読んで覚えましょう。
受験予定地の過去問を必ず解きましょう
前述の通り、毒物劇物取扱者試験は都道府県によって試験問題が違います。
そのため、西日本編・東日本編でまとめた過去問題集はありますが、全国統一の過去問題集は本屋さんに置いてません。
まずは受験予定地の過去問を用意しましょう。
解いてみると、都道府県ごとに出題傾向やよく出る物質が分かります。出題形式も把握できます。
ほとんどの都道府県ではネット上で過去問を公開しています。
yahooやgoogleで「都道府県名 毒劇物 過去問」と入力して検索すれば、ほぼ各都道府県分が表示されるはずです。
例えば、東京都なら東京都福祉保健局のホームページで閲覧できます(下記参照)。
都庁第一本庁舎3階北側の都民情報ルームに行けば、閲覧及びコピーも可能です。
![]() 参考:毒物劇物取扱者試験 東京都福祉保健局
参考:毒物劇物取扱者試験 東京都福祉保健局
※「5 試験問題及び正答」をご覧ください。
こちらは関西広域連合の過去問題及び解答です。
受験する都道府県以外の過去問をやっても全然的外れになる可能性もあるので注意してください。
おすすめの通信講座
JTEX(ジェイテックス)とは40年の歴史があり、受講者も200万人を超える技術系の通信講座の会社です。
この講座は、毒物劇物取扱者試験について、3つの科目(法規、基礎化学、性質と貯蔵・取扱方法)ごとに基礎を学び要点をおさえ、合格に必要な実力を養成することをねらいとします。
新講座として登場してまだ日は浅いのですが、既に人気の講座です。
※こちらから受講申し込みができます。
![]() 毒物劇物取扱者受験講座|JTEX 職業訓練法人日本技能教育開発センター
毒物劇物取扱者受験講座|JTEX 職業訓練法人日本技能教育開発センター
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
利用者が多いテキストです。とてもわかりやすく書いてあります。
本試験で出題されるキーワードや特徴で分類・整理されているので、他の毒物劇物と関連づけて覚えられます。
同じ薬品名が複数ページにわたって出てくるので自然に繰り返し学習ができます。各章に章末問題があり、学習の進み具合も確認できます。
分かりにくい説明や表現もあるので、化学や薬に関する基礎知識がある程度必要です。
初学者であれば、これ一冊での短期間学習は厳しいと思います。じっくりと時間をかけて学習しましょう。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
おすすめ問題集
各都道府県が毎年1回実施している毒物劇物取扱者試験の解説付き問題集です。
毒物劇物取扱者試験は受験する都道府県により、出題数、傾向が違います。どの様な問題が出題されるのか、雰囲気をつかむのに良い本です。
収録している試験の内容は、北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県…2回分(令和5年度、令和4年度)の合計10回分です。
※各地域ごとに問題集が出ています。購入する際は受験する都道府県がどちらに属するのか確認してください。
| 種類 | 評価 |
| 問題集 |  |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
例年1~2回
都道府県によって異なります。
お申し込み
都道府県によって異なります。
受験資格
年齢、学歴等に関係なくどなたでも受験できます。
試験会場
各都道府県
受験料
各都道府県により異なりますが、概ね10,000~13,000円。
試験内容
※試験内容は各都道府県により異なります。必ず受験地の試験概要を確認してください。
【筆記試験】四肢択一式
- 毒物および劇物に関する法規
- 基礎化学
- 毒物および劇物の性質、および貯蔵その他取扱方法
【実地試験】
- 毒物および劇物の識別、および取扱方法
実地試験:実地を想定した筆記試験として実施されることが多くなっています。実態は実技試験という名の筆記試験です。
合格基準
総得点で満点の60%以上かつ各課目とも40%以上の得点
