文書情報管理士とは?公共性があり就職で役立つ可能性もある
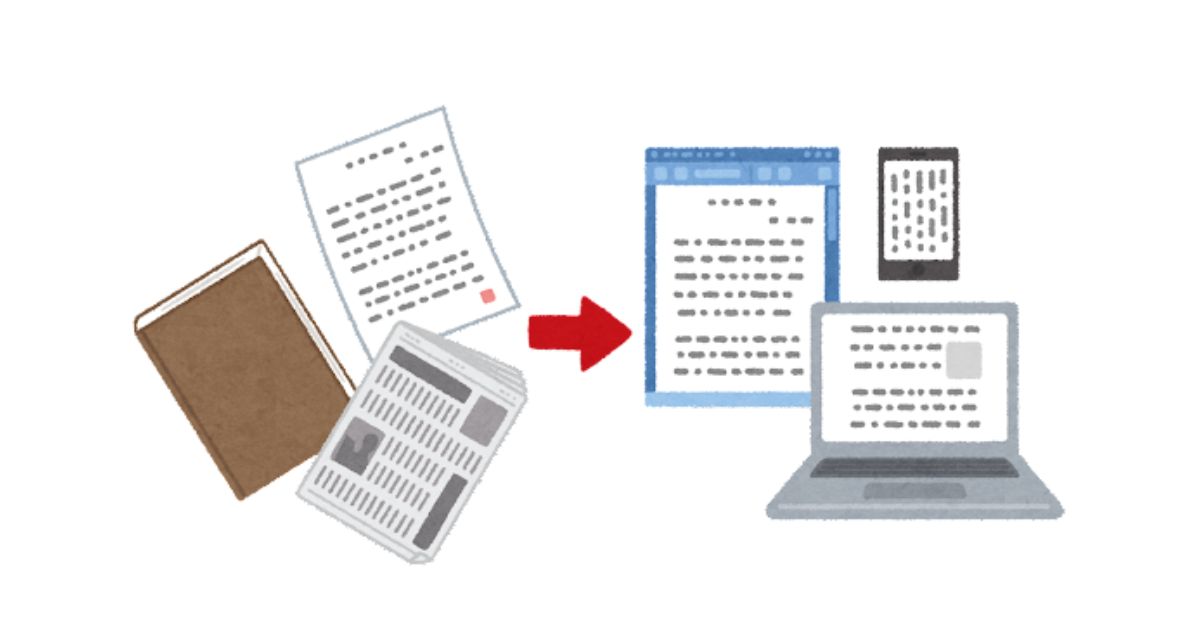
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | やや易 | 80% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 2か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 2件 |  |
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年5月12日に集計。
会社内に2級以上の合格者がいれば、自治体が実施する「電子化の業務」の入札に参加できるメリットがあります。
ただし、2級の合格率は80%前後で難易度は比較的低いため、社員に取得させれば済みます。
そのため全国的にも文書情報管理士の求人数は少なく、取得しても就職や転職が有利になるとまでは言えません。
文書情報管理士とは
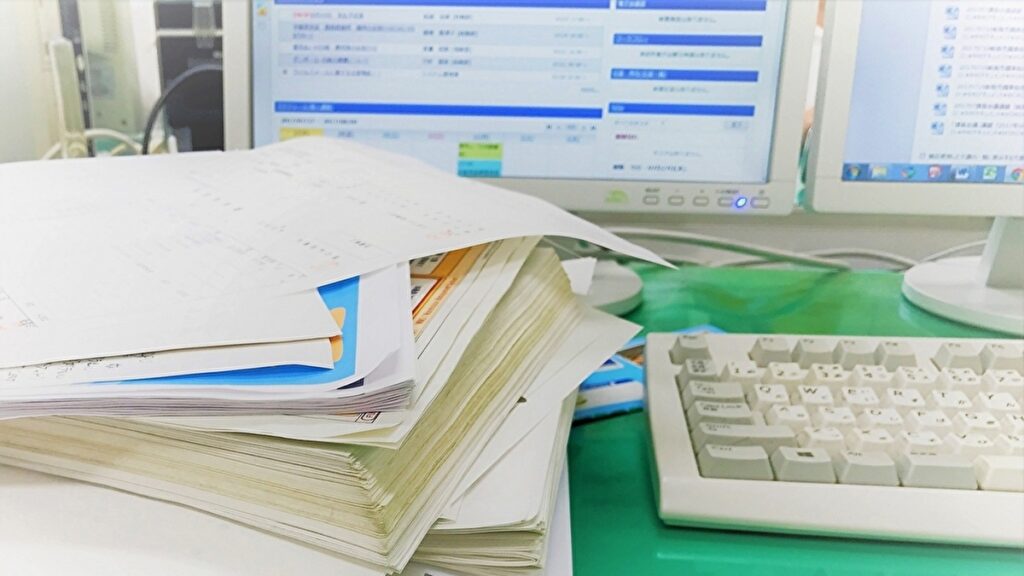
紙のデータを電子化する専門家
文書情報管理士とは、主に会社で取り扱う紙の文書全般(帳票類、伝票類、資料、図面)について、パソコンの画面などで見られるようにスキャナで読み込んだり、マイクロフィルムとして保存するための技術を学ぶ検定試験です。
さらに、試験の学習を通して書類保存に関連する法律・規格などの知識を身に付けます。
つまり、文書情報管理士とは、従来の紙ベースの書類を電子化して、データをパソコンやネットワーク上の安全な場所に保存するための専門家ということです。
スキャナで読み込んだデータやマイクロフィルムであれば、大量のデータを効率よく安全に長期間保管できます。
しかも、場所をほとんどとりません。読みたいときに過去のデータから探し出すのも容易です。
文書情報管理士とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が2001年から実施している民間の検定試験です。
難易度の低い順に、2級、1級、上級の3種類があります。
年間の受験生は約700名(2024年は752名)程度ですからまだまだマイナーな資格試験ですが、受験生は年々増加しています。
※マイクロフィルムとは、文書や写真などの資料を通常の1/10~1/30に縮小撮影して保存する写真技法です。
![]() 主催者サイト:文書情報管理士|JIIMA認定の資格|JIIMA 公式サイト
主催者サイト:文書情報管理士|JIIMA認定の資格|JIIMA 公式サイト
書類を電子化すれば、長期間保管できて場所もとらない
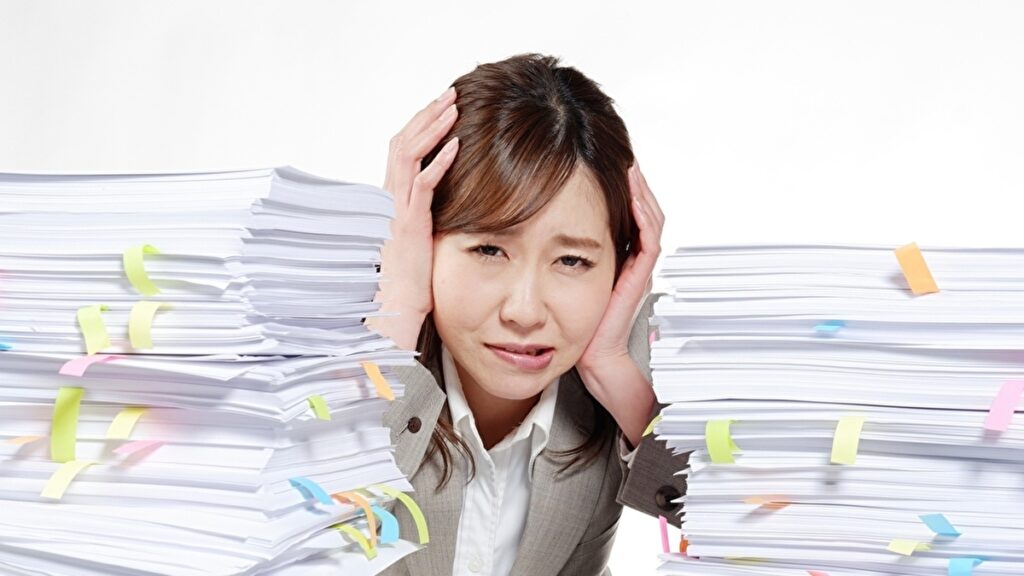
電子化つまりペーパーレスという言葉は以前から言われ続けています。
しかし、多くの会社ではまだ紙文書が中心でペーパーレス化は進んでいないのが現状です。
今でも、紐でとじた書類をダンボールに詰め込んで倉庫に保管している会社は多いのではないでしょうか?
会社で書類を長年保管するのって想像以上に経費がかさみます。大型のキャビネットをいくつも置くと部屋が狭くなります。
会社が保存しなければならない文書関係の書類は様々です。
税務上の書類から、請求書、領収書、契約書、見積書、労働契約書、誓約書・・・等々。
そして、その多くが税法、商法、民法、労働基準法などの企業法務と密接に関わっています。
税務上の書類は保存年数が法律によって明確に定められているので簡単には捨てられません。
どれを捨ててどれを残しておかなければならないのかよく分からない、万が一の場合に備えて紙で残っている方が安心、というのがペーパーレス化が進まない理由のようです。
ナント!多くの官公庁・自治体で入札の条件になっている
国が書類の電子化を推進するために、音頭を取ってe-文書法や電子帳簿保存法などを制定した以上、書類の電子化やマイクロフィルム化は、官公庁・自治体にとっても重要な仕事になっています。
国や自治体は、民間企業に率先しなければなりません。
官公庁や自治体、公共の施設では電子化する際に、民間企業に業務を委託していますが、その際入札参加資格要件として「文書情報管理士の有資格者が在籍する企業」であることを求めています。
つまり、文書情報管理士(2級以上)が社内にいないと、外部に委託する「電子化の業務」の入札に参加できないんです。
内閣府、国土交通省、財務省、防衛省、文部科学省、厚生労働省などのほぼ全ての官公庁、都道府県や市町村などの自治体ほぼ全て、年金機構、日本銀行、国立国会図書館などほとんどの公共の施設で、電子化業務の入札参加資格要件として「文書情報管理士」資格を求めています。
文書情報管理士は、民間資格であるにも関わらず公共性の高い民間資格なんです。
ただし、オイシい仕事じゃない
電子化業務の入札には文書情報管理士が必要と説明しましたが、これらの入札業務は全ての入札案件のごく一部にすぎません。
発注金額は小さく、概ね300万円以下といったところです。しかも比較的短期の軽作業の請負業務ばかりです。
どうやらあまり美味しい仕事ではないようです。
入札の結果、「落札者なし」というケースもあります。
役に立つ資格なのか?
文書情報管理士の求人は少なく、求人誌、求人サイト、ハローワークで検索してもほとんど見つかりません。
マレに1級取得者を優遇する情報が見つかる程度ですが、それでもほぼ派遣や契約社員など非正規の雇用です。
しかも、電子化の入札案件の条件として、例えば公文書管理検定、ファイリング・デザイナー検定、電子化ファイリング検定などの他の民間検定試験合格者でもよい場合も多いので、あえて文書情報管理士だけにこだわる理由はないんです。
文書情報管理士は比較的短期間で取得できる簡単な試験なので、入札に参加するのであればいざとなったら社員に取得させればすみます。
わざわざ文書情報管理士2級取得者を新たに外部から採用する必要もありません。
文書情報管理士は公共性の高い一面もありますが、就職や転職には大きなメリットまではなさそうです。
将来性について徹底研究

この資格の活かし方
紙ベースの情報を電子化する際に必要になるのは法令の知識です。
企業内で扱う文書は多種多様です。どの書類を捨ててよいのか、捨ててはいけないのかを判断するには法令の知識が必要になります。
文書情報管理士の学習を通して、例えばe-文書法と電子帳簿保存法の違いについての知識が身に付きます。
企業内の文書をペーパーレス化する際にその知識が活かせるはずです。
最近は、スキャニング代行サービス、書類スキャニング専門の会社が増えていますが、そういった会社へ就職・転職する際には文書情報管理士の資格が役立つかもしれません。
ごく一部ですが、合格者に資格手当や合格手当を支給している会社もあるようです。
そういった会社に在籍しているのであれば取得するメリットは大いにあります。
取得後の有効期限は5年間、更新は有料
文書情報管理士は、資格取得後5年ごとに資格の更新が必要になります。
その際は簡単な課題も提出します。
その費用は3,190円(税込、2025年12月現在)です。
更新費用が10,000円以上する検定試験が多い中、良心的な値段設定です。
![]() 参照:文書情報管理士の資格更新について|JIIMA認定の資格|JIIMA 公式サイト
参照:文書情報管理士の資格更新について|JIIMA認定の資格|JIIMA 公式サイト
実はこの3,190円という金額が微妙な設定なんです。
10,000円くらいなら更新しない人も多いと思いますが、まぁ3,000円くらいならいいや!って感じで更新するのではないでしょうか。
更新をしないともちろんですが文書情報管理士の資格を喪失します。
入札で利用しているようであれば忘れずに更新しましょう。
合格するには
2級の合格率は80%前後
文書情報管理士検定試験は、難易度の低い順に、2級、1級、上級の3種類に別れています。
2級は誰でも受験できます。1級は2級取得者のみ、上級は1級取得者のみ受験できます。
全ての級においてマークシート式の解答です。
試験は簡単なので、1日2時間の学習であれば1~2か月程度で十分合格できます。
2級の合格率は80%前後なので、ほぼ全員が合格できる難易度です。
e-文書法や電子帳簿保存法関係の出題が多いので、協会が出版している「e-文書法入門」をしっかり勉強するのが重要です。すべてこのテキストが出題範囲です。
ただ、残念なことに、市販のテキストや問題集が販売されていません。
主催者サイトより直接購入してください。一部Amazonなどで購入できるテキストは下記で紹介しています。
どうしても合格したい人であれば、日本文書情報マネジメント協会主催の受験対策セミナーに出席するのもよいでしょう。
検定試験委員が試験の重要なポイントを教えてくれるので、かなり有利になるはずです。
![]() 参考:JIIMA 公式サイト 文書情報管理士検定試験について
参考:JIIMA 公式サイト 文書情報管理士検定試験について
もちろん独学でも十分合格できます。セミナーは参考書の購入を斡旋している面もあるので安くないです。あまりおすすめできません。
2016年の2月度の試験からは、コンピュータの画面で出題するCBT方式になったので、全国各地で試験を受けられます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の検定試験委員会の編集によるテキストです。
文書情報マネジメント用語。2017改正に対応した、文書情報管理士検定用テキスト。文書情報マネジメントに必要最小限の規格を網羅し、適用範囲や概要を示す。
※テキストは基本的に市販されていません。出版物・販売物|JIIMAの活動|JIIMA 公式サイトから直接購入してください。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
おすすめ参考書
日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の検定試験委員会の編集による参考書です。
文書情報管理士合格に必要な内容が多く記述されていて、この参考書から多くの問題が出題されます。
これまでの紙文書の情報だけではなく、パソコンなどで保存・利用する電子文書や、メール、最近利用する会社が増えているSNS、スマートフォンの写真などの、データの管理方法や、利便性とそれに反するリスクまで記述しています。
試験の学習以外でも日常の業務でも役立つ内容です。
※テキストは基本的に市販されていません。出版物・販売物|JIIMAの活動|JIIMA 公式サイトから直接購入してください。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
【年2回】
7月中旬~8月末、12月中旬~2月中旬
お申し込み
主催者発表によります
(インターネット受付のみ)
受験資格
2級はどなたでも受験可能です。
試験会場
全国のCBT試験会場
受験料
11,000円(税込)
試験内容
【試験範囲】
2級、1級の出題範囲は同じです。1級はより高度な知識が求められます。上級は文書情報に関わる規格、法律、マイクロフィルム、プロジェクトマネジメントに関する知識などに重点が置かれています。
【試験内容】
《2級》
- 電子化文書関連、マイクロ写真関連の基礎知識及び実技能力
- 文書情報マネジメントに関わるハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク関連の基礎知識
- 文書情報マネジメントに関する日本特有の法令、標準規格の基礎知識
《1級》
- 2級の能力に加えその専門知識及び実技応用能力
- 文書情報マネジメントの作業に従事する作業者に対する指導力
《上級》
- 1級の能力に加え以下の能力
- 顧客の問題点や課題の本質を明確化できる課題分析能力と、システム構築能力
- 保存性、原本性など文書情報管理の専門的知識および提案能力
- 高い費用対効果を発揮できるコスト意識及び能力
【出題形式】
2級:CBT択一選択式80問90分
1級・上級:CBT多肢選択式80問90分
合格基準
原則として正答率70%以上
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報はJIIMA 公式サイト 文書情報管理士検定試験についてをご覧ください。
試験に関する詳しい情報はJIIMA 公式サイト 文書情報管理士検定試験についてをご覧ください。
