一般計量士とは?合格率や難易度・資格の活かし方は
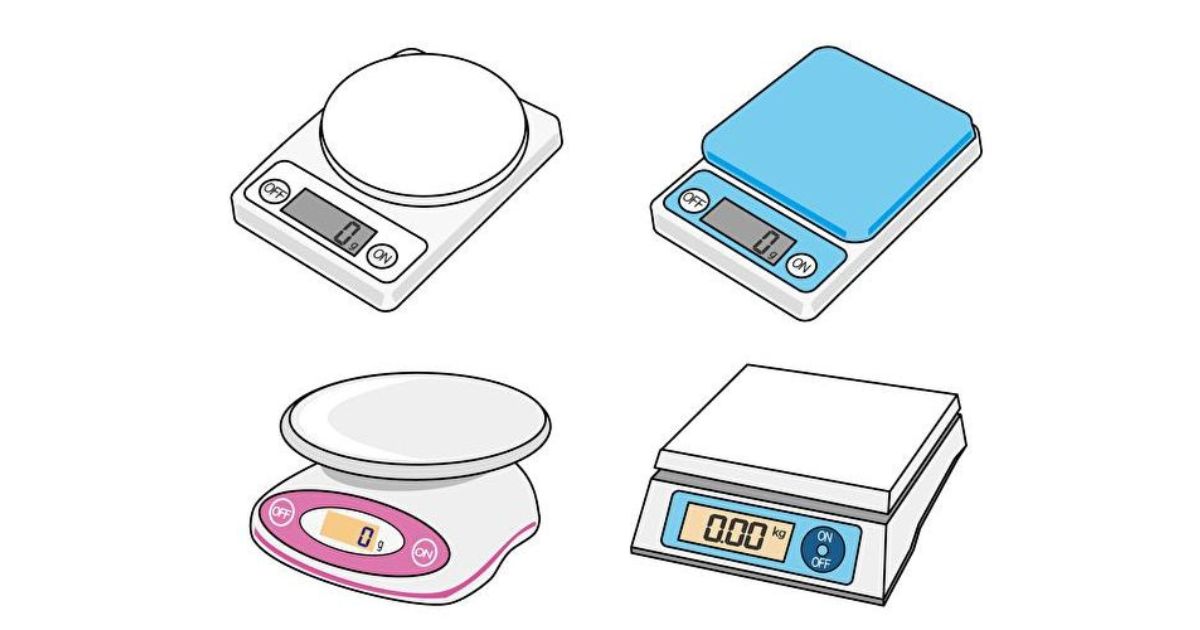
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | 難しい | 15~25% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~2万円 | 1年程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 評価アップ | 9件 |
- 難易度や合格率は、濃度/騒音・振動関係によって違います。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2026年1月5日に集計しました。
長さ計、温度計、体積計、質量計といった計量機器が正確に動いているかどうかを確認するために器具の保守・点検を行う専門家です。
社内で管理業務をしている社員が、スキルアップのために取得します。
試験の難易度は高く1年程度の勉強時間は必要ですが、所定の研修課程(計量教習)を修了して取得する方法もあります。
求人数は全国的にも少なく、就職や転職に活かせる資格ではありません。
一般計量士とは

計量器具の保守・点検を行う専門家
一般計量士とは、「物の長さや重さなどを正確に計量」するために「器具の保守・点検」を行う専門家です。
長さ計、温度計、体積計、質量計といった計量機器が正確に動いているかどうかを確認するのが一般計量士の主な仕事です。
具体的には、工場や百貨店・スーパーなどの小売業で使われる長さ計、質量計、体積計、温度計等の計量機器の点検・精度管理などを日々行います。
つまり、一般計量士は、質量、長さ、体積などの計量のプロフェッショナルです。
環境計量士と一般計量士の違いは?
一般計量士とは別で環境計量士という国家資格があります。
![]() 関連資格:環境計量士とは
関連資格:環境計量士とは
こちらは、環境保護のために「環境の汚れ具合を正確に計量」して、調査・分析するのが仕事です。
大気や水中の汚染物質の濃度、騒音や振動の大きさなどを適正に計量することを目的としています。
一般計量士も環境計量士と同様に「正しい計量」が目的ですが、そもそも一般計量士は計量するための「器具の保守・点検」を目的としているという点で違います。
メーターなどの計量機器には正確性が求められる

私たち達の身のまわりには『はかり』と呼ばれる様々な「モノの量や大きさ」を計る道具や器械があります。
一般的に「メーター」などとも呼ばています。
例えば、ガスメーター、水道メーター、ガソリンスタンドの給油メーター、タクシーメーター、スーパーや肉屋さんで使われる『はかり』などです。血圧計や温度計、体重計もそうです。
これらが正確でないと、過大に料金を請求されたり、極端に安くなったりして、売る側や買う側に著しい不利益が生じます。
ひいては経済活動に支障をきたす可能性があります。
『はかり』を用いて取引や証明を行う場合、計量法の検定に合格した正確な計量機器(特定計量器)を利用しなければなりません。
検定に合格した『はかり』には、必ず「検定証印」または「基準適合証印」のどちらかが表示または刻印されています。
こういった、量や面積、体積といった物の長さや単位を統一するのは歴史的にも重要な政策でした。
相当古い話しですが、豊臣秀吉が田畑を測量しつつ長さや量の単位を統一た太閤検地と言われる「度量衡の統一」は有名な話しです。
計量士という国家資格の制度は、計量法という国の法律に基づき、取引や証明のために正しい計量を行う目的で1953年に始まりました。
計量法とは、計量の基準を定め、正しい計量を確保するための法律です。
その後、1993年(平成5年)に計量法が改正され、計量士の資格は、一般計量士と新たに誕生した環境計量士に現在は区分されています。
※ここでは主に、一般計量士について紹介いたします。環境計量士については別ベージにて紹介していますので、そちらもご覧ください。
![]() 参考:くらしを守る計量法|東京くらしWEB(pdf)
参考:くらしを守る計量法|東京くらしWEB(pdf)
※計量法について分かりやすくまとめられています。
役に立つ資格なのか?
求人は全国的にも少ない
一般計量士の主な業務は、工場・百貨店・スーパーなどで使われる計量器が正しく動いているかどうかを管理することです。
主な活躍の場は、国又は都道府県知事が商品販売の際に使用する計量器などを自主的に計量管理していると認めた適正計量管理事業者、計量機器メーカーなどです。
計量機器メーカーの工場が適正計量管理事業所になっていれば、そこで一般計量士として計器類一般の校正や管理を任されます。
校正とは、計測器・計量器の表す値が、標準となる値に比べ、どれくらい誤差(器差)があるのかを確認する非常に重要な作業です。
スーパー、百貨店のように、例えば食料品を量り売りしているような場所でも、品質管理の一旦として一般計量士の資格は役立ちます。
ただし、一般計量士としての求人は少ないです。
求人情報やハローワークで探してもほとんど見つかりません。
それは、一般計量士は1つの事業所に1名必要な必置資格なので、多くの会社では有資格者が1名いれば足りるからです。
いざとなったら、品質管理・検査部署の社員に取得させればすみます。
一般計量士は難関の国家資格なので、合格すれば社内で評価されます。
合格すればすぐに就職や転職に役立つとまでは言えませんが、スキルアップに役立ちます。
将来性について徹底研究
この資格の活かし方
「はかり」「メーター」と言われるモノは、一度購入したらあまり買い替えませんが、私たちの身近に確実に存在します。
一般計量士が資格を活かせる場所としては、例えば、質量や物質の長さを測定する重量計、湿度計、体温計から、水道メーター、ガスメーター、タクシーメーターなどを製造するの計測機器メーカーです。
その他では、スーパーや百貨店などの流通業、肉製品や乳製品や製粉などを扱う食料品製造業、錠剤などを製造する医薬品製造業などです。
最近はデジタル機器で正確に計量できますが、いずれも「重さ」は正確に計る必要があります。
こういった会社であれば就職や転職は有利です。入社して一般計量士の資格を計量機器の管理業務に活かせます。
さらに品質管理の経験もあれば転職は有利です。
しかし、元々求人数が少ない分野なので、取得すればすぐに就職・転職に活かせるものでもありません。
難易度のワリにはメリットが少ない資格です。
どちらかと言えば社内で管理業務をしている社員が、スキルアップのために取得する資格です。
実務経験を積むのが一番の難関
国家試験に合格しても、その後に実務経験を積まないと正式に一般計量士として登録できません。
一般計量士として正式に経済産業大臣へ登録をするには、国家試験合格者で1年、国家試験を受けない資格認定コースでは2年間(平成29年度以前は5年)計量管理の実務の経験が必要です。
実は、この実務経験をクリアするのがかなり大変です。
一般計量証明事業として登録を受けている会社、あるいは適正計量管理事業所の指定を受けている会社で計量管理の実務を経験しなければなりません。
登録を申請すると、書類審査だけでなく実際に事業所に来て実務経験内容を細かくチェックをする計量検定所もあるようです。
環境計量士であれば、計量研修センターが開催する1週間程度の講習を受講すれば登録できますが、一般計量士にはそれに相当する講習がありません。
そのため、試験に合格することよりも実務経験を積む方が大変なようです。
合格しただけで登録できずにいる人が大勢います。
数学・物理は高校レベル以上は必要
一般計量士の試験科目の中に、専門科目として、計量に関する基礎知識(一基)があります。
こちらの物理・数学の問題は、高校レベルでも十分合格点をとれます。
高校レベルは確実におさえておきましょう。自信のある人なら、数日間の復習でも問題ないでしょう。
一基の勉強は、過去問題を解きながら、分からない部分を高校の参考書で補います。
数学の参考書としておすすめは「チャート式数学」です。大学受験で利用した人も多いと思います。
黄色が一般的ですが、白チャートと呼ばれるもので十分です。Ⅰ+A、Ⅱ+B、Ⅲ+Cが必要です。
数学は簡単には実力はつきません。何度も繰り返し勉強してください。
物理に関しては、高校物理+αの知識と幅広い計測に対する正確な知識が必要になります。
同じくチャート式物理、Ⅰ、Ⅱをやり込めば必要な知識は身に付くはずです。
合格するには

取得方法は2パターン
一般計量士の資格を取得するには、以下の2通りの方法があります。
※以下、ほぼ環境計量士と同じです。
- 国家試験コース:環境計量士の国家資格に合格する
- 資格認定コース:所定の研修課程(計量教習)を修了する
環境計量士(濃度、騒音振動)に合格すれば、他の試験区分を受験するときに法規と管理の2科目が免除されます。登録していなくても大丈夫です。
資格認定コースとは、計量研修センターで行う一般計量教習(共通)を受講後に、特別教習(一般、環境/濃度関係、環境/騒音・振動関係)を受講し計量士を目指す研修課程です。
修了すれば国家試験を受ける必要はありません。
計量士資格認定コースは、国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターが開催しています。
受講するには、まず入所試験に合格しなければなりません。
研修を受講して取得する方が、国家試験を受験するより圧倒的に簡単です。
入所試験の合格率などは公表されていませんが、難易度としては高校卒業レベルです。
試験科目は、数学、物理、時事常識を含む一般常識の3科目です。
定員数(40名)が決まっているため、受検者数が少ない年は入所しやすいようです。
入所定員を超える時は不合格者が出ます。
ちなみに、受講者の合格率・修了率はともほぼ100%だと言われています。
費用などは下記に詳しく載っています。
マイナーな国家資格なので問題集も限られる
一般計量士は難関の国家資格です。簡単には取得できません。
元々の基礎学力で違いますが、やはり1年程度は勉強する必要があります。
数学・物理の基礎ができていないなら、高校の参考書で勉強しなおしましょう。
数学などは中学まで戻って勉強した方がよいかもしれません。
本試験は、毎年繰り返して出題される内容が多く、難易度の高い問題が多いのも特徴です。
過去問題集を繰り返し解いて、分からない点は参考書に戻って理解する、その繰り返しです。
ちなみに、環境計量士と比べると一般計量士の方が難易度は低いです。
一般計量士は受験生も少ないマイナーな試験なので参考書は限られています。
4種類の試験科目に応じて、日本計量振興会編からテキスト・問題集(コロナ社版)が出てますから、そちらでお買い求めください。
※Amazonでも販売してますが中古品です。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ問題集
2019年12月まで過去6回分の試験問題を、試験科目ごとに分類・整理し、頻出・重要問題を丁寧に解説しています。わかりやすい問題集&参考書といった内容です。
一問ごとに過去問が列挙されているので、出題傾向がつかみやすく、反復練習がしやすい構成になっています。
価格は安くありませんが、4科目すべてが1冊にまとまっていて効率よく学習ができるのでコスパは悪くないです。
これ一冊だけで合格する人も少なくないようです。
| 種類 | 評価 |
| 問題集 |
おすすめ参考書
数学が非常に苦手、数学初学者でも十分理解できる(はず)の超入門書です。
基本的には黄チャートで学習してもいいと思いますが、難しく感じる方はこちらの白チャートがいいでしょう。白チャートは教科書の例題レベルから掲載されています。
とにかく、何度も繰り返し解けば確実に実力は付きます。それを信じて勉強しましょう。
量が多いので、数学嫌いな人が見ると挫折する可能性はありそうです。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
12月中旬の日曜日(予定)
お申し込み
例年7月上旬~8月上旬
受験資格
受験資格の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
試験会場
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄
受験料
8,500円
試験内容
【試験科目】
- 計量に関する基礎知識(専門科目)25問
- 計量器概論及び質量の計量(専門科目)25問
- 計量関係法規(共通科目)25問
- 計量管理概論(共通科目)25問
一部科目免除の制度あり。
合格基準
- 専門2科目の合計が、120点以上(30/50問)
- 共通2科目の合計が、120点以上(30/50問)
※「免除あり」の場合は、1の基準を満たすものとします。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は資格・試験 (METI/経済産業省)をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は資格・試験 (METI/経済産業省)をご覧ください。
※こちらに随時最新の試験情報が掲載されます。
