手話通訳士になるには?難易度は高いけど活躍の場は限られる
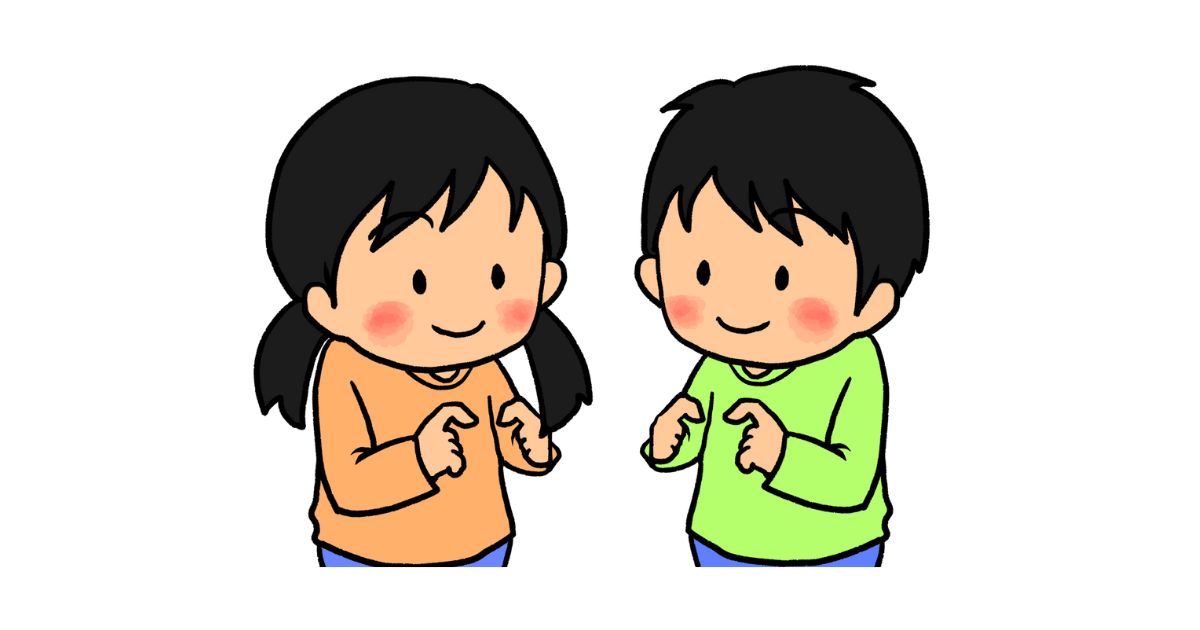
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | 難関 | 9.6% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 20歳以上 | — | 4年以上 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 83件 |
- 当サイトでは厚生労働省認定の国家資格として紹介します。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月26日に集計。
手話通訳士の社会的な意義は大きいですが難易度は高く合格しても就職や転職は有利にはなりません。
手話を学ぶには、まずは自治体が開催する格安の講座を受講して手話奉仕員になり、その後手話通訳者へステップアップするのが一般的です。
プロレベルになるには、国家資格でもある手話通訳士の資格が必須です。
手話に関する民間の検定試験がいくつか存在し、通信講座などもありますが、あまり効率よく学習ができるとは言えません。
手話通訳士(手話通訳技能認定試験)とは

手話を通して意思疎通を仲介
手話を駆使して、障害がある人とその他の人との意思疎通を仲介するのが手話通訳士です。
手話通訳士は、学校、病院、福祉施設、官公庁、裁判、企業、テレビ局(政見放送、ニュースや天気予報の報道)などで手話通訳を行い、聴覚障害者に正確な情報を伝えるために活動します。
最近テレビなどでニュース番組、政見放送、天気予報などを放送する際、手話を使って聴覚障害者の人への同時通訳をしている光景をよく見ます。
政治家や自治体の首長が重要な発表をする際に、横で大きな身振り手振りで手話をしている女性を見るのも今や日常的な光景です。
このように、耳の不自由な人や言葉を話せない人とのコミュニケーション手段として「手話」はポピュラーな方法となっています。
![]() 公式サイト:社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
公式サイト:社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
![]() 参考:日本手話通訳士協会
参考:日本手話通訳士協会
厚生労働省の省令で規定するれっきとした国家資格
「手話通訳技能認定試験」(手話通訳士試験)は1989年(平成元年)から始まりました。
かつての合格率は約20%ほどでしたが、ここ数年は10%を切っており難易度は高くなっています。
国内で手話通訳士として登録している人数は2025年11月28日現在で4,259人です。
手話通訳士は、国の法律の定めるところによる国家資格ではなく「公的資格」とよく紹介されます。
しかし、その根拠となっているのは厚生労働省が定めた「平成二十一年厚生労働省令第九十六号 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」です。
この省令は「身体障害者福祉法第四十五条」が根拠となっています。つまり、国会で定めた法律がそもそもの根拠となっています。
「公的資格」の制度が2005年に廃止になっているため、やはり手話通訳士は厚生労働省が定める国家資格と言うべきでしょう。
一般的に、手話通訳を行う人達全般を手話通訳士と呼ぶようですが、正式には手話通訳技能認定試験に合格し、聴力障害者情報文化センターに手話通訳士として登録を受けなければ手話通訳士とは名乗れません。名刺などにも「手話通訳士」と印刷できません。
![]() 参照:手話通訳士名簿 2024.10.21更新|社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
参照:手話通訳士名簿 2024.10.21更新|社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
手話通訳士と手話通訳者と手話奉仕員の違い
手話に関する公共性の高い資格をまとめると以下の3種類が存在します。
公共性の高い手話に関する資格3種
- 手話通訳士(国家資格)
- 手話通訳者(全国統一の公共性の高い資格)
- 手話奉仕員(各市町村が認定)
一般的に、手話通訳を行う人達全般を手話通訳士と呼びます。
では、手話通訳士と手話通訳者の違いは?と疑問を持たれる方も多いようです。
どう違うのかと言うと・・・
手話通訳士は国家資格だという点が大きな違いです。
正式には手話通訳技能認定試験という国家試験に合格し、聴力障害者情報文化センターに手話通訳士として登録を受けなければ手話通訳士とは名乗れません。名刺などにも「手話通訳士」と印刷できません。
手話通訳士の国家資格を持つメリットは何かというと、例えば裁判や警察関係、選挙の政見放送などの公的な場面で手話通訳士と名乗って仕事ができます。
手話通訳士の資格以外にも、都道府県・政令市などが実施する「手話通訳者養成講座(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)」を修了した後、「手話通訳者全国統一試験」に合格し登録すれば手話通訳者としてその地域で働けるようになります。
全国手話通訳者統一試験に合格して自治体の登録手話通訳者として活動、その後手話通訳士試験を受けて最終的に手話通訳士になります。
これが手話通訳者と手話通訳士の違いです。
また、市町村などの自治体が実施する「手話奉仕員養成講座(初級・中級・上級)」を修了し登録すれば「手話奉仕員」として手話に関する様々な活動ができます。
奉仕員とはボランティアと同じ意味です。奉仕員は、聴覚障害者の生命や権利に関わる公的な通訳はできません。
その他、手話技能検定、全国手話検定、手話検定などの民間資格がありますが、あまりおすすめしません。
中には講座受講料を目的としただけの怪しい講座もあるので注意してください。
自治体が主催する講座であれば格安で受講できます。通信講座と違って実際に対面での練習もできます。
わざわざ高い受講料を払って民間の検定試験を受ける意味はないでしょう。
手話通訳士になるには
まずは「手話通訳者」を目指すのが一般的
では、手話通訳士になるにはどうしたらよいのでしょうか?
実際に多いパターンとして、前述の「公共性の高い手話に関する資格」を下から順に、手話奉仕員→手話通訳者→手話通訳士とステップアップするケースです。
手話通訳士は国家資格ですが、手話を使って仕事をするために国家資格は特にいりません。
無資格者であっても手話通訳を行うことはできます。
もちろんお金をもらって日常的に業務をこなしても問題ありません。
手話通訳の仕事をするには、まず各都道府県や政令市などが実施する「手話通訳者試験」を受けるのが一般的です。
この試験に合格して自治体に登録すれば、手話通訳者としてその自治体で働けます。
都道府県庁や市町村役場や社会福祉協議会などから依頼を受けて手話通訳を行います。
現在、手話を使って収入を得ている人のほとんどはこういった自治体に登録している手話通訳者です。手話通訳士ではありません。
手話通訳士の資格を持っていても持っていなくても収入にあまり差がないというのも理由のひとつです。わざわざ国家試験を受ける意味はないということです。
自治体の通訳者として働く場合、給料・報酬は、一件の依頼につき5000円前後です。
実績があってたくさん依頼を受ける人であっても月7~8万円程度しか稼げません。やはり副業程度の収入です。
ちなみに、ボランティアの手話通訳者としてなら資格など一切なくても任せてもらえる自治体や団体も多いです。
この場合でも手話奉仕員養成講座くらいは受講しておいた方がいいでしょう。
これから手話を勉強してみたい、あるいは手話通訳として仕事をしたいのであれば、まずは住んでいる自治体の役所に講座開催の有無を問い合わせてみましょう。
役に立つ資格なのか?

就職や転職には役に立たない
手話通訳は手話を必要とする人、特に聴覚障害を持った人の生活や人生を左右する仕事です。社会的な存在意義は非常に大きいです。
しかし、手話通訳士の資格は難易度が高いワリには求められる頻度はあまり多くありません。
通常の手話通訳であれば特に手話通訳士の資格は不要であるため、「有資格者でなければできないこと」は限られています。
資格を活かせる仕事といえば、例えば裁判での通訳、選挙の政見放送くらいです。
そのため、求人なども少なく、就職や転職にはほとんど役立ちません。
手話通訳士を専業にしている人はごく少ないのが現状です。
資格の取得がそのまま仕事と収入につながらないので、金銭的な利益はあまり期待しないほうがよいでしょう。
手話通訳士のほとんどは他に仕事を持っています。
いつもは公共機関に属してフリーランスとして手話通訳者として活動する人、聴覚障害者協会や通訳者派遣センターなどに登録し、要請があったら会議や研修の場に派遣される人もいます。
ただし、これらは登録制です。必要になった時に「お呼びがかかる」ようなシステムなので、それだけで生計を立てるのは難しいです。
将来性について徹底研究
難関だけど活動の場は少ない
手話通訳士として専任で資格を活かせる職場は、残念ながら現時点ではあまり多くありません。
しかし、他の仕事と兼務であれば、そのスキルを十分に活かして働くことは可能です。
例えば、介護福祉士のように福祉関係の仕事に就いている人であれば職場で必要に応じて手話は役立ちます。
看護師のような医療従事者、病院の窓口業務担当者も手話は仕事に活かせます。
サービス業であれば、聴覚障害者とコミュニケーションを提供することができ、新たな顧客の確保やレベルの向上にもつながります。
まだまだボランティアとしての活動が中心ですが民間施設、医療施設、窓口接客などで手話の必要性は増しています。十分な経験を積めば関連施設などに採用される可能性もあります。
手話通訳ができる人は決して多くありません。そのため、聴覚に障害のある人と関わる会社であれば重宝されます。
難しく感じて途中で飽きる人が多い
手話通訳士の資格をとるために必要なのは「人の言ってること(書いてること)をしっかり聞いて(読んで)理解する能力」です。これができなければ相手に伝わる手話はできません。
手話通訳は日本語をたくさん知っている方がスムーズにできます。
多くの本を読んで、たくさん国語に触れ、豊かな日本語語彙力を身に付けなければなりません。
手話も言語の一種です。日本語と手話は別の言語です。共通点はもちろん多いですが文法は違います。
しっかり習得しようと思えば、他の音声言語を学ぶのと同様に難しいです。
ボランティア気分で手話サークルに入って、なんとなく流行で勉強することについて否定はしませんが、ほとんどの人は難しさを実感してやがて飽きて手話通訳するレベルまで達しません。
手話通訳士になるには

想像以上にハイレベルな国家資格
手話通訳士の試験は難易度が高く、合格までに長い道のりを要します。
合格率は毎回10%を下回ります。
手話を習いたての初心者はほとんど受験せず、多くは何年も手話をしているベテラン揃いです。
そんな受験生の中での10%ですから想像以上にハイレベルな試験です。
通常は合格までに4年以上、合格者の多くは手話通訳経験が10年以上です。
手話通訳士になるには、まずは手話奉仕員養成講座を受講後、手話通訳者養成講座に通い、県で実施している手話通訳者統一試験を受けます。
それに合格して手話通訳者として3年ほど実務経験をした後、手話通訳士の国家試験を受験します。
実際に手話を実践してみること
手話は独学で学ぶよりも、まずは市や県が主催する手話の講座に通い、地域の手話サークルに通うのが効率的な学習法です。
手話講習会はどこも人気ですぐにいっぱいになります。すぐには参加できず待たされる場合がほとんどです。。
自治体が主催する手話奉仕員養成講座を受講して真面目に勉強すれば、簡単な会話程度はできるようになります。それからボランティアを始めるといいです。
あるいは、NHK教育テレビ、youtube等で手話の動画を繰り返し見て覚えます。
手話は動きのある言語なので、実際に繰り返し体を動かして覚えます。
奥深く覚えようとすると難しいですが、日常会話なら独学でもある程度までは覚えられます。
日本人の悪い癖でついついノートに書いて覚えようとしますが、それはあまり意味がないです。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ問題集
手話通訳士技能認定試験(手話通訳士試験)の筆記試験対策書です。
第1回から第30回までの出題項目や出題実績を分析し、厳選した過去問と模擬問題を収載しています。
4択のうちの正解以外の項目についても、なぜそれが正解ではないかとの説明があり、解説が細かく書かれているので理解しやすいです。
手話通訳士試験の参考書として必携の一冊です。
| 種類 | 評価 |
| 問題集 |
おすすめ参考書
手話はどんな言葉なのか、手話通訳者になるにはどんな方法があるのか、どんな場面で必要とされるのかを詳しく紹介しています。
さらに、教育、医療、スポーツや国際会議、手話のニュースキャスターなど、さまざまな分野で活躍する第一線の手話通訳者たちの声を通して、手話、そして手話通訳の魅力をお届けします。
手話通訳者として、教育、医療、スポーツや国際会議、手話のニュースキャスターなどの分野で活躍している人達の貴重な体験談が紹介されています。
手話通訳者を目指すために必要な心構えや具体的な話が参考になります。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
学科:7月下旬の日曜
実技:10月初旬の日曜
お申し込み
概ね5月中
受験資格
受験日のある年度末までに20歳以上の者
試験会場
宮城、埼玉、東京、大阪、熊本
受験料
22,000円(税込、2025年7月15日現在)
試験内容
【学科試験】四肢択一式:3時間30分
- 障害者福祉の基礎知識 20問
- 聴覚障害者に関する基礎知識 20問
- 手話通訳のあり方 20問
- 国語 20問
【実技試験】
- 聞取り通訳試験(音声による出題を手話で解答する方法) 2問
- 読取り通訳試験(手話による出題を音声で解答する方法) 2問
免除科目:学科試験の合格者は、翌年に限り学科試験が免除されます。
合格基準
【学科試験】
- 全ての科目において得点があり、4科目の総得点のおおよそ60%以上の得点率で合格(問題の難易度により補正される)。
【実技試験】
- 採点は、出題の内容が正確に通訳されているか否かの「正確さ」の評価と、手話表現の「技能」の評価を併用して行います。「正確さ」の評価は、試験問題文(音声)の展開がつかめていて、適切な翻訳が出来ているかを評価します。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)について|厚生労働省をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)について|厚生労働省をご覧ください。
