弁理士とは転職が有利になり年収アップも期待できる国家資格
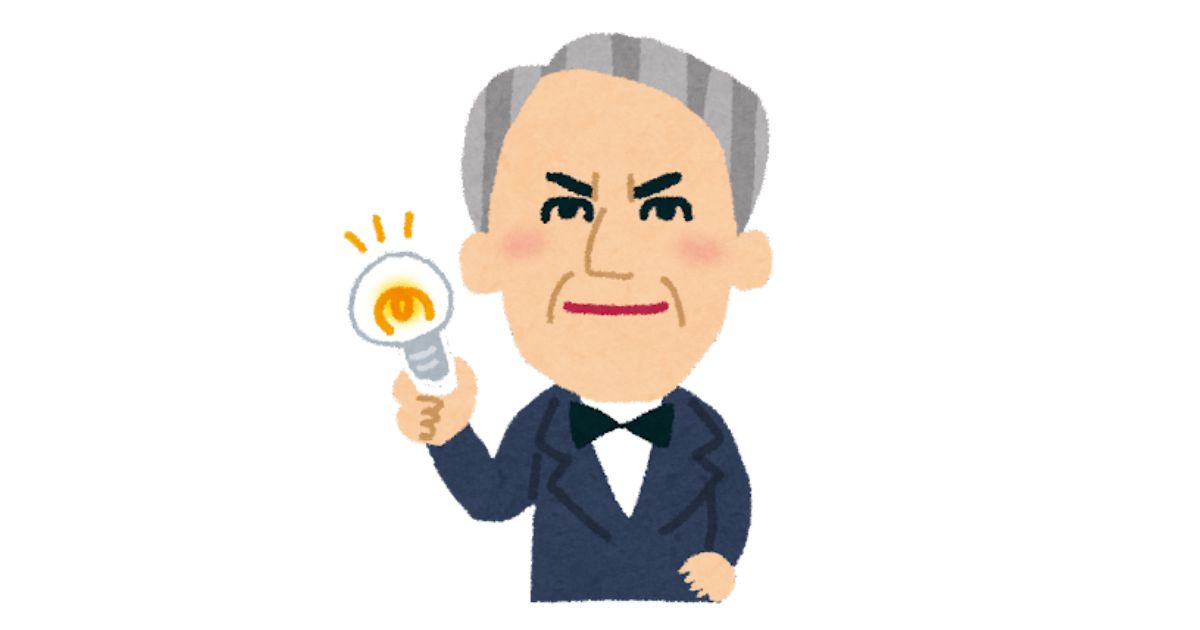
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | 超難関 | 6% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | 50万円以上 | 3年以上 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 評価アップ | 35件 |
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年5月2日に集計しました。
弁理士とは、個人や企業の代理人として特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権について特許庁に申請する専門家です。
大手企業での評価が高く、取得して転職すれば大幅な給料アップも期待できます。
実力があればもちろん独立して事務所を構えることも可能です。
特許取得にしのぎを削る企業が多い中、将来性もあってかなり有望な国家資格です。
合格しても弁理士として登録しない人も多いようですが、この場合弁理士と名乗ることはできません。
弁理士とは
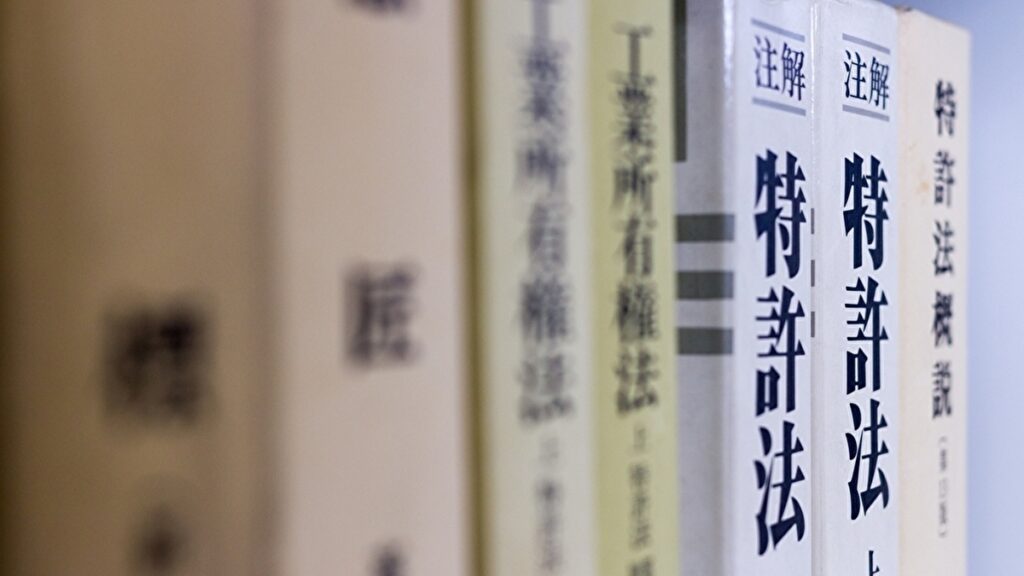
知的財産権を守る専門家
弁理士とは、個人や企業の代理人として、特許、実用新案、意匠、商標に関し(これらを知的財産権といいます)、特許庁に対し申請する専門家です。
知的財産権の代表といえば何と言っても「特許権」です。大企業は、新たな技術を他社に先駆けて開発するよう日々多くの研究費を投じています。
特許権とは、発明を公開した会社のみが独占的にその技術を利用して、他社が勝手に技術を利用することを排除する権利です。
![]() 関連団体:日本弁理士会
関連団体:日本弁理士会
![]() 所轄省庁:弁理士 (METI/経済産業省)
所轄省庁:弁理士 (METI/経済産業省)
知的財産の管理は会社の存続に関わる
例えば、今後主流となるであろう燃料電池自動車などは、細かい部品の1つ1つにいたるまで大手自動車メーカー同士の特許合戦になっています。
最も多いトヨタ自動車が、燃料電池自動車に関する特許だけで約5,680件も持っているといいますから驚きです。
余談ですがトヨタ自動車はその特許を2030年末までを目処に無料で開放しています。
次に馴染みのある知的財産権といえば、「意匠」や「商標」です。
意匠権とは、デザインに関する権利であり、商標権とは社名や商品・サービス名に関する権利のことをいいます。
例えば「ガリガリ君」のアイスが売れているからといって、あのイガグリ頭の男の子のイラストやガリガリ君の名前を勝手に使ってはいけません。
アディダスのロゴやデザインを勝手に使うこともできません。
企業が意匠・商標登録する意味は、ブランド名等を他社が使えないようにして独占することで企業の利益や消費者を守ることにあります。
特許、意匠、商標登録の手続きは企業や個人でもできますが、業務として依頼を受けて代理人として手続きができるのは弁理士だけです。
それらは法律で定められた弁理士の独占業務です。
役に立つ資格なのか?

転職の際は技術者としての経験が重要
弁理士として活躍するには、知的財産部門(以下:知財部門)の事務経験よりも、開発技術系の実務経験が重要になります。
実際、弁理士のほとんどが企業内で開発業務などに携わってきた人ばかりです。
そのため企業への転職の際は、開発技術系の実務経験があれば特に有利です。
実務未経験であれば、メーカーで技術者としての経験が5年程度あることが重要になります。
逆に、特許事務所への就職・転職は知財部門での実務経験があれば比較的容易にできます。
弁理士資格を取得して就職・転職となると、企業の知財部門あるいは特許事務所に限定されますから選択肢は狭いです。
もちろん、実力がつけば独立して事務所を構えるという選択肢もあります。
大企業であれば企業内弁理士がいる
一時期、大企業が弁理士資格保持者を「企業内弁理士」として中途で採用することが流行りました。
社内に弁理士がいれば、特許事務所に依頼せずに自社で特許出願が可能です。
特許事務所の担当者と何度も打ち合わせをすることもなく迅速により確実に特許申請の業務を進められます。
とは言うものの、企業内弁理士は1社に1人いれば十分です。
難関な弁理士試験合格者とはいえ大企業への転職は狭き門でした。
![]() 関連資格:知的財産管理技能士とは
関連資格:知的財産管理技能士とは
将来性について徹底研究

この資格の活かし方
弁理士の仕事は年収が高いとも言われていますが、勤務スタイルや勤務先企業の条件、経験年数によって違います。
実際には、年収としては700万円くらいから1000万円を軽くオーバーするような人まで様々です。
弁理士として独立した人の中には、2000万円、3000万円以上の年収を稼ぐような人もいます。
その場合、当然ですが弁理士としての実力だけではなく経営力や営業力も必要になります。
給料は弁理士の働き方次第です。
特許出願をおこなうには発明の詳細な説明を記した明細書を添付しなければなりませんが、弁理士の技術知識と明細書を作成する能力により完成度が違います。
特許事務所に勤務していたとしても明細書を作成する能力次第です。
ただ資格があるだけで高給取りにはなれません。やはり実力がものを言う世界です。
資格を持っているだけでメリット十分とはいかないようです。
資格手当を月に10万円支給する会社も
弁理士が会社の知財部門で仕事をする場合は、弁理士の資格手当てが支払われるケースが多いようです。
資格手当は大手の会社の方が高い傾向にあり、給料に5万円~10万円ほど上乗せになる場合もあります。
一方で企業によっては弁理士の資格を評価しないところも多くあり、全く資格手当が支給されない会社もあります。
企業が申請する場合は代理人は不要なので、弁理士だからといって特別な扱いをしないというのがその理由です。
そういう会社に在籍して弁理士登録すると月々の弁理士会の会費(20,000円ほど)も自腹となりますから、合格したけど弁理士未登録の人もかなり多くいます。これは意外です。
ただし、手当として直接支給されなくても弁理士の資格を取ることによって昇進につながる可能性は大きく、その結果年収もアップします。
弁理士の代表的な業務は特許の申請です。申請自体より、その技術がすでに他社で特許取得済かどうかを膨大な資料の中から調べるのが実は大変です。
当然、その依頼の内容が理解できる技術力と知識が無いと仕事になりません。
一言で技術や開発といっても電気、電子、機械と分野は多岐にわたりますからかなりハードな仕事内容です。
弁理士になるには
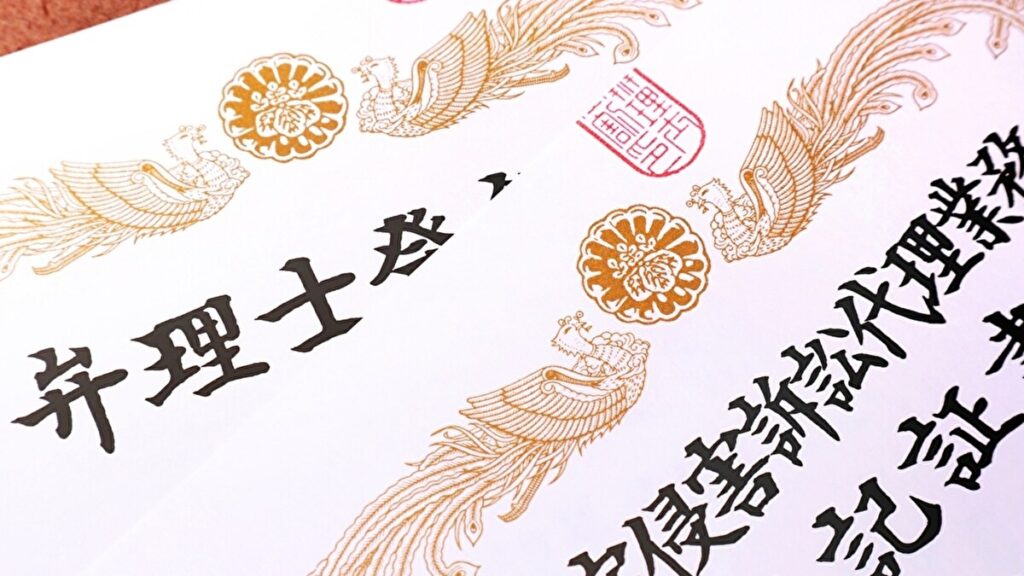
合格するには理工系の学力がかなり必要
特許庁から、過去の弁理士試験に関する統計が発表されていますが、見てみるとその内容に驚きます。
※各年度別に志願者から最終合格者までの細かな情報が掲載されています。
弁理士試験の志願者・合格者ともに出身大学を調べるとそのレベルの高さが際立っている事がすぐ分かると思います。
例年、東大や京大などの有名国立大学出身者が最も多く、他も難関大学出身者ばかりです。
そもそも理工系の大学院を出ている受験者が80%近くを占めています。
それでも合格率が6%程度ですから、一体どんな人が合格できるの?って感じです。
その難易度の高さはおそらく想像以上でしょう。
合格者のうち、ほとんどが超難関大学の理系出身者で占められています。
弁理士試験には論文もありますが、理工系の最高水準の知識と最近の技術動向の知識が十分ないと、おそらく満足に論文も書けないでしょう。
文系出身者で知識ゼロだけど弁理士試験に挑戦してみたい…というレベルではないようです。
働きながら勉強して4回以上の受験で合格
弁理士は、理系の司法試験と言われるくらい難関国家資格となっています。
役に立ちそうだからというい安易な理由で挑戦する資格ではありません。
試験は、弁護士や司法書士ほどの難易度ではありませんが、それに近いくらい難関です。
試験は筆記試験、論文、口述と半年近くの期間で行われます。
先程の特許庁の統計からもわかる通り、ほぼ90%の人が働きながら受験しているのも大きな特徴です。
弁理士試験だけに備えて仕事を辞めて学習に専念している人はごく少数です。
働きながら学習して、平均4年から5年ぐらいで合格している人が多いようです。
もちろん途中で挫折した人はその何倍もいて統計には入っていません。
「短期で一発合格!」なんて人は一部の例外です。
合格するには、数年かけて勉強を続けなければなりません。
最近の合格者数は以前よりも抑え気味
弁理士試験は難関資格と何度も説明しましたが、「知財立国」を目指す国の政策で弁理士を1万人確保するという大義名分の下、合格者数を大幅に増やしていた時期があります。
平成13年くらいまでは毎年の合格者数は300人以下、合格率は5%以下でした。
それが平成15年~平成25年くらいまでは毎年600人から800人を輩出し、合格率も10%弱ぐらいで推移していました。
当然弁理士の数は比例して増え続け、平成25年には1万人の目標を達成しました。
しかし、その後数年間、弁理士試験に合格したけれども弁理士として登録しない人の割合が30%前後ぐらいまで増加しました。
つまり合格しても弁理士として働く職場が見つからない人が急増したんです。それを如実に表しているのが志願者数の急激な減少です。
これはマズい、合格者を増やしすぎた、という理由で、平成26年より試験のハードルをぐっと上げて合格者数を減らし、以前の2~4%ぐらいの合格率に戻っています。
まずは無料の資料請求
おすすめの通信講座
弁理士の受験においては、市販のテキストや参考書だけではまず合格できません。
資格予備校か通信講座を利用するのが一般的です。試験では論文もあるので第三者に内容をチェックして評価してもらう必要があります。
資格スクエア
数ある弁理士受験講座の中でも高い合格実績を誇るのが資格スクエアです。
講義視聴から問題演習までオンラインですべて完結するので、いつでもどこでもマホやPCを使ってテキストや問題集の勉強ができます。
資格スクエア弁理士講座は、基礎固め、論文対策、短答対策と、3フェーズで構成されています。
1つの科目を基礎から実践(応用)へと徐々にステップアップしていくことで確実に理解が深まり合格するための実力が付きます。
Web問題集は、なんと25年分の肢別過去問を収録しているので、スキマ時間でも効率的に学習できます。
さらに、フィルター機能で覚えていないものを中心に効率的に繰り返し学習ができます。実はこの機能が大変すぐれています。
レジュメ集(テキスト)はオプションとなりますが、やはり製本されたテキストを利用するのがおすすめです。
※こちらから資料請求、無料講義体験、受講申し込みができます。
アガルートアカデミー
弁理士試験業界で最低水準の低価格な受講料であるにもかかわらず、合格に必要十分なカリキュラムです。
オンラインで講義を受講しますが、1単元あたりの講義時間が5分~15分とコンパクで、時間のない社会人でも無理なく何度でも受講できます。
STUDYing(スタディング)旧通勤講座
パソコン、スマホ、タブレットを使い、スキマ時間を使って効率的に学習できるのが特徴です。
最適な順番で学習できる学習システムにより、論文式試験に初めて挑戦される方や論文が苦手な方でも無理なく着実に合格できる実力を身につけられます。
※こちらから受講申し込みができます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
弁理士について漠然としたイメージしか持っていない人、弁理士ってどんな仕事してるの?と思っている人におすすめの1冊です。
読み終わった時点で仕事内容について具体的なイメージを抱けていると思います。
最近企業で引っ張りだこになっている知的財産コンサルタントの弁理士の活躍ぶりは、今までにない弁理士の一面を見せてくれます。
※試験対策本ではありません。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
短答式筆記試験:5月中旬~下旬
論文式筆記試験:(必須科目):6月下旬~7月上旬、(選択科目):7月下旬~8月上旬
口述試験:10月中旬~下旬
お申し込み
3月下旬~4月上旬
受験資格
受験資格の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
試験会場
- 短答式筆記試験:仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
- 論文式筆記試験:東京、大阪
- 口述試験:東京
受験料
12,000円
試験内容
弁理士試験は短答式筆記試験、論文式筆記試験(必須科目と選択科目)、口述試験の3段階です。そのつど合格発表がおこなわれ、不合格になると次の段階へ進めません。
【短答式筆記試験】工業所有権に関する法令:全60題(五枝択一:マークシート方式)
- 特許・実用新案に関する法令:20題
- 意匠に関する法令:10題
- 商標に関する法令:10題
- 工業所有権に関する条約:10題
- 著作権法及び不正競争防止法:10題
【論文式筆記試験(必須科目)】工業所有権に関する法令
- 特許・実用新案に関する法令
- 意匠に関する法令
- 商標に関する法令
【 論文式筆記試験(選択科目)】
※下記の表に記載する技術又は法律に関する科目から、受験願書提出時に選択問題を1つ選択。
- 理工I(機械・応用力学):材料力学、流体力学、熱力学、土質工学
- 理工II(数学・物理):基礎物理学、電磁気学、回路理論
- 理工III(化学):物理化学、有機化学、無機化学
- 理工IV(生物):生物学一般、生物化学
- 理工V(情報):情報理論、計算機工学
- 法律(弁理士の業務に関する法律):民法
【口述試験】工業所有権に関する法令
- 特許・実用新案に関する法令
- 意匠に関する法令
- 商標に関する法令
合格発表
11月中旬
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は弁理士試験|経済産業省 特許庁をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は弁理士試験|経済産業省 特許庁をご覧ください。

