色彩検定とは?色に関する知識を得られるメリットがある

| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | やや易 | 75% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~2万円 | 2か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 知識習得 | 22件 |
- 上記は3級についての内容です。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年6月24日に集計。
あくまでも自己啓発の勉強です。身に付いた「色の知識」を仕事に活かせばメリットも期待できます。大いに役に立つでしょう。
受験生の多くは、デザインや服飾などの専門学校の生徒です。勉強した成果を何かの形として残すために受験します。
大学生や社会人が取得して履歴書に書いても就職・転職が有利になるとは期待しない方がよいでしょう。
高い合格率が見込めるおすすめの通信講座
色彩検定とは

色について学ぶ検定試験
色彩検定とは色に関する幅広い知識や技能を問う民間の検定試験です。
歴史もあって知名度も高く毎年3万人近くが受験します。
試験の学習を通して、色に関する基本的な知識や配色の方法(色の組み合わせ)などの専門的知識を身に付けます。
色彩検定を通して色について学習すれば、今まで自分では気付かなかった色の使い方ができるようになります。
服装の色合いや部屋のインテリアなど、日常生活においてきっとセンスの良い商品を選ぶことができるでしょう。
販売業の商品ディスプレイや照明技法、季節ごとの配色、食品などを照明を使い分けることで、美味しそうに見せる方法など、多くの場面で知識を活用できます。
色相環の理解が基本
私たちの生活は多くの色であふれ、日常的にいろんな色と接しています。
例えば、色は光の波長の違いによって、赤・橙・黄・緑・青・紫というように連続的に変化して知覚されます。
この色の変化をつなげてひとつの輪にしたものが色相環です。
この色相環を理解して、正しく使うことで配色技法が身に付きます。理論立てて配色ができるようになります。
これまで、なんとなく配色が良い、センスが良い、見た感じが良い、あるいは色合いが悪い、センスが悪いと感じていたことを、「色彩検定」の学習を通して、感性や経験によらないで理論的に判断や理解ができるようになります。
![]() 主催者サイト:色彩検定協会/カラーコーディネーター
主催者サイト:色彩検定協会/カラーコーディネーター
役に立つ民間資格なのか?

あくまでも自己啓発の検定試験
色彩検定は、専門学校・大学・短大の学生が多く受験します。
中でも多いのが、デザイン、ヘアメイク、美容、ファッション、デザイン系の専門学校の生徒です。
学校で勉強した結果を何か形として残すために受験します。
合格すれば就活の際に履歴書に書いてアピール材料にします。
とは言え3級であれば短期間で合格できます。
民間資格なので合格しても特別にできる業務はありません。
大勢の生徒が合格するので、色彩検定を持っているからといって就職・転職が有利になったり、採用の決定打になる可能性は低いでしょう。
一番難しい「色彩検定1級合格」に合格すれば、他の学生と差別化がはかれて多少なりとも評価されるかもしれません。
社会人などが転職のために取得しても転職の際の強力な武器にはならないでしょう。
就職・転職するために何か役立つ資格を・・・と考えるのであれば、もっと違う資格を取得すべきです。
あるいは、デザインのセンスを磨いて、自分の作品をアピールする方が就職・転職に直結します。
色彩検定はあくまでも自己啓発のための検定試験です。
色に関する基本から応用までの知識を得るという意味では役に立ちます。
身につけた色に関する知識を日常生活や仕事の上でどう活かすかは本人次第です。
将来性について徹底研究

この民間資格の活かし方
デザインやインテリア関係の仕事をしている人であれば、それまでは漠然とした直感で選んでいた色を理論立てて選択することでより精度の高いデザインに仕上げることができるようになります。
例えば、アパレル関係の仕事をしているのであれば、売りたい商品の対象が子供なのか大人なのか、売る時季が夏なのか冬なのかといった要件を考えれば、短時間で色彩の調和から配色まで理論立てて決められるようになります。
色の理論を知っているのは配色を考える上で有効です。
プロ意識を高める手段として色彩検定の資格を活かすことができます。
デザインの現場ではセンスや実績を重視する
デザインの現場では、「デザインはセンスです。知識や資格ではありません」というのが定説的な意見のようです。
特に色は理論と同時にセンスが問われます。
色彩検定の資格を活かして、ゲーム制作会社、デザイン事務所、広告会社、Web制作会社などへ就職・転職に役立てたいと考える人が多いようですが、実際は資格の有無はほとんど採用に影響しません。
それよりも、どういうデザインが描けるかということが大切です。
デザインの実力を磨いて、自分の作品を用意してアピールする方が良いでしょう。
最近は、パソコンを使って配色する機会が多いので、3Dや2Dのソフトをどれくらい使いこなせるかということも重要です。
色彩検定1級を持っていても、デザインのセンスが悪ければどうしようもありません。
資格で仕事をするのではなく、資格は業務を補足する手段にすぎません。
デザインのセンスは一朝一夕で身につくものではありません。
1か月から2か月程度で取得できる民間資格よりも、もっと大切なことがたくさんあります。
色彩検定とカラーコーディネーター検定の違い
色彩検定と同じような検定試験でカラーコーディネーター検定試験があります。
どちらを学習しようかと迷っている人も多いと思います。
![]() 関連資格:カラーコーディネーター検定試験とは
関連資格:カラーコーディネーター検定試験とは
両者とも色に関する試験なので色彩理論など共通項目は多いのですが、色彩検定はファッションなどの服飾系の分野を主に勉強します。
一方、カラーコーディネーターはどちらかというと商工業系です。
色彩理論以外に商品ディスプ レイや照明の技法、商工業製品や建築、バリアフリーやユニバーサルデザイン等の知識や歴史、コンセプトなどを勉強します。
カラーコーディネーター試験は学術的要素が強いため、勉強用テキストも色彩検定に比べて理論的な記述が多く難しくなっています。
初学者にとっては勉強がツラいと感じるかもしれません。
試験の内容も、色彩検定に比べてカラーコーディネーターは覚えることが多く、幅広い分野から出題されるため難易度は若干高めです。
どちらから受験するのがおすすめかというと・・・やはり知名度や歴史の古さ、受検者数の多さ、 学習する内容なども考えると色彩検定がおすすめです。
色彩検定は、美術系の大学生、専門学校生、デザイン系の社会人、趣味で受検する人、多くの人が受験します。
なお、パーソナルカラリスト検定は、「人と色」に着目して、「その人に合う色を提案する」といった視点から色彩に関する知識を学ぼうという民間資格です。
美容やアパレル関係の仕事に就いている人向けです
![]() 参考:パーソナルカラリスト検定|一般社団法人日本カラリスト協会
参考:パーソナルカラリスト検定|一般社団法人日本カラリスト協会
合格するには
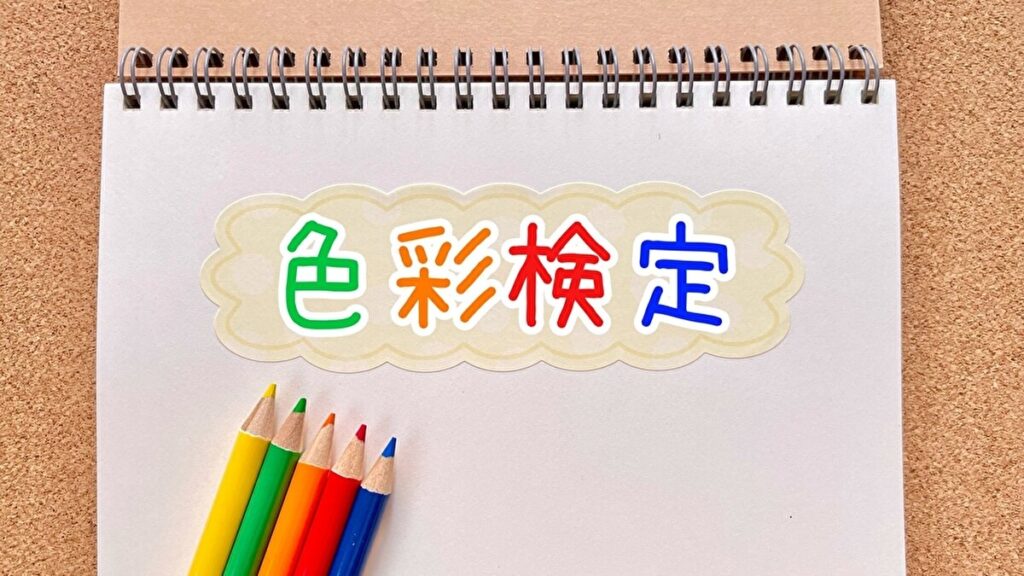
3級と2級は短期間で合格可能
色彩検定には3級、2級、1級があります。
入門者向けで難易度が低い3級に合格するのが目的であれば市販の安いテキストでも十分です。
3級と2級なら、とりあえずテキストを読み、問題集を解けば知識ゼロからでも毎日1~2時間、1~2か月ほどで合格できます。
3級と2級の難易度はそれほど変わりません。2級がやや難しい程度です。
ともに色に興味があるという趣味のレベルでも、十分に勉強時間を確保して集中して勉強すれば1か月ほどで合格できます。
勉強する内容も違うので、2級から受験しても問題ありません。
色についてしっかり勉強したいのであれば、並行して勉強して両方受験するのがおすすめです。
仮に1級までチャレンジするのであれば3級と2級の知識が必要です。
予備知識などが全くなく、初めて勉強するのでしたら3級から勉強を始め、ある程度基礎を積み重ねてから2級の勉強に入った方がよいでしょう。
2級までなら、やる気さえあれば独学で十分合できます。
毎年多くの人が色やデザインの仕事と無関係の人が多く合格しています。
市販の参考書や問題集だけで十分です。
2級と3級の同時受験も可能
試験は午前と午後の部にわかれているので、2級と3級は同時受験が可能です。
午前の試験後に、午後に残りの級を受験します。
申し込む際は同じ願書で申し込まないと、試験会場が別々になる場合があるので注意してください。
まずは無料の資料請求
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
ほとんどの受験生が利用する公式テキストです。
公式テキストだけでも、あまり内容を深く考えず、何度も読んでありのまま暗記すれば合格できますが、過去問題集と合わせて学習するのがおすすめです。
さすが公式テキストだけあって、全く同じ文面で試験に出題されます。
写真やイラストもそのまま出題されるので、テキストの太線部分と重要な図や表を理解できれば大丈夫です。
ページ数は多くありませんが、中身が濃いので、じっくり勉強する必要があります。就職後に仕事で使えます。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
わかりやすく見やすいので、全く予備知識もなく色彩検定初心者の人はこのテキストからはじめるのがおすすめです。
公式テキストは当然ですけど出題範囲のカバー率では最強です。しかし網羅的、詰込み的に書かれているため重要ポイントが不明確です。
公式テキストとは比較にならないほど分かりやく説明されています。重要で試験に頻出のポイントが明確です。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
おすすめ問題集
問題集は、やはり公式の過去問題集がおすすめです。
解説がとても丁寧な過去問ベースの解説がある確実なものを使用した方が試験対策的には有効です。
この公式過去問題集は1年分あるので、3級夏冬+2級夏冬の4回分の試験問題が掲載されています。
試験前に満点がとれるまで何度も繰り返して解けば2級3級ともに合格できます。
過去問題集は、試験の傾向をつかむ上でやはり必要です。本試験へ向けての練習になります。
| 種類 | 評価 |
| 過去問題集 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
【2級】夏期(6月下旬)と冬期(11月中旬)
【3級】夏期(6月下旬)と冬期(11月中旬)
【1級】冬期(11月中旬)2次は12月中旬
お申し込み
3月下旬~5月中旬
8月下旬~9月下旬
受験資格
誰でも何級からでも受験できます。
試験会場
全国各地
※1級2次試験は札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、福岡市
受験料
- 1級:15,000円
- 2級:10,000円
- 3級:7,000円
- UC級:6,000円
(2025年7月11日現在、各税込)
試験内容
【3級】:筆記試験(マークシート方式)
・以下のような色彩に関する基本的な事柄を理解している。
光と色、色の分類と三属性、色彩心理、色彩調和、色彩効果、ファッション、インテリアなど。
【2級】:筆記試験(マークシート方式と用語レベルの記述式)
・3級の内容に加え、以下のような基本的な事柄を理解し、技能を持っている。
照明、色名、表色系、配色技能、配色イメージ、ビジュアルデザイン、ファッション、プロダクト、インテリア、エクステリアなど。
【1級】1次:筆記試験(マークシート方式と記述式)、1級2次:実技試験(記述式)
・2級と3級の内容に加え、以下のような事柄を十分に理解し、技能を持っている。
色彩と文化、色彩調和論、色の知覚、ファッションビジネス、プロダクトデザイン、インテリアカラーコディネーション、環境色彩、ユニバーサルデザインなど。
※色彩検定は複数の級を同時受験できます。申し込む際は同じ願書で申し込まないと、試験会場が別々になる場合があるので注意してください。
※1級1次試験に合格し、2次試験に不合格になった場合、その後2年間に限り1次試験が免除になります。
合格基準
各級とも満点の70%前後、問題の難易度により多少変動。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は受検案内 合格への道|色彩検定協会/カラーコーディネーターをご覧ください。
試験に関する詳しい情報は受検案内 合格への道|色彩検定協会/カラーコーディネーターをご覧ください。

