法学検定とは?難易度や合格後のメリットや活かし方など

| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | 60% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 1か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 知識習得 | 0件 |
- 上記は主にベーシックコース〈基礎〉についてです。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月30日に集計しました。
法学検定とは、法律・法学に関する知識がどれくらい身についているのかを客観的に評価する民間の検定試験です。
難易度が高い「アドバンスト」に合格すれば法科大学院の入試で考慮される可能性はあります。
あくまでも法律の知識を確認するための大学生向けの検定試験です。
履歴書に書いて就職や転職を有利にするための「資格」ではありません。
法学検定とは

法律・法学の知識を試す検定試験
法学検定とは、法律・法学に関する知識がどれくらい身についているのかを客観的に評価する民間の検定試験です。
法学とは、ひとことで言えば法律について考える学問です。
法律とは「社会のルール」で、基本となるのは日本国憲法からはじまり民法、刑法に刑事・民事の両訴訟法などの法律が載っているいわゆる「六法全書」です。
法学検定の学習を通して、法律の条文ごとに制定された経緯や意味、解釈方法を具体的に考え、さまざまな事件や問題を法の理念に照らし合わせて法律をどう適用するかについて学びます。
大学生から社会人、中学生や高校生まで幅広く受験
法律は、実はとっても身近な存在です。私達の身の回りで生じるほとんどの事象はなんらかの形で法律と関わっています。
それだけに法学で学ぶべき範囲は極めて広いと言えます。
法学検定は誰でも受験できるので、法学部に在籍する大学生から一般の社会人、中学生や高校生まで幅広く受験します。
将来法曹関係の仕事(弁護士・裁判官・検事)に就くことを夢見て受験する高校生も少なからずいます。
法学検定を主催する公益財団法人日弁連法務研究財団とは、日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)が中心となって設立した団体で、弁護士や税理士・司法書士などによって構成されています。
民間の検定試験ですが、公共性が高い一面も有しています。
![]() 主催者サイト:公益社団法人 商事法務研究会
主催者サイト:公益社団法人 商事法務研究会
役に立つ資格なのか?
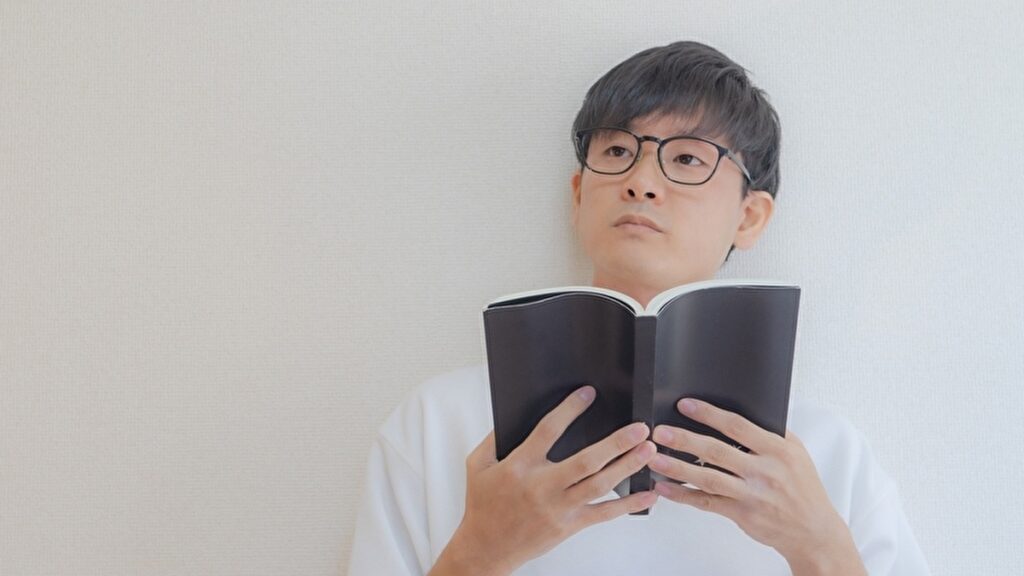
法科大学院を目指すのであればメリットはある
法学検定に合格しても、就職・転職が有利になるとか、社内での評価が上がるといった効果はあまり期待できません。
しかし、一部の大学生や、法科大学院を目指す人にとっては役立つ可能性があります。
現在の日本では、司法試験を受験するには法科大学院を卒業するか司法試験予備試験に合格しなければなりません。
法科大学院は、そのレベルを客観的に評価するために、5年に1回、文部科学省が認定する認証評価機関により評価を受けることが義務づけられています。
その認証評価機関として2004年から文部科学大臣より認証されているのが法学検定を主催する日弁連法務研究財団です。
つまり、法学検定は非常に公共性の高い民間団体が主催する検定試験なんです。
法学検定には、ベーシック(基礎)、スタンダード(中級)、アドバンスト(上級)の3つの級がありますが、スタンダード以上に合格すると単位として認定する大学もあります。
最上位のアドバンストの合格者を、法学既修者の選抜(入試)の際に明確に考慮する法科大学院もあります。例えば、早稲田大学大学院法務研究科です。
日弁連法務研究財団が主催(公益社団法人商事法務研究会と共同)している以上、他の法科大学院においても何らかのメリットはあるでしょう。
将来性について徹底研究
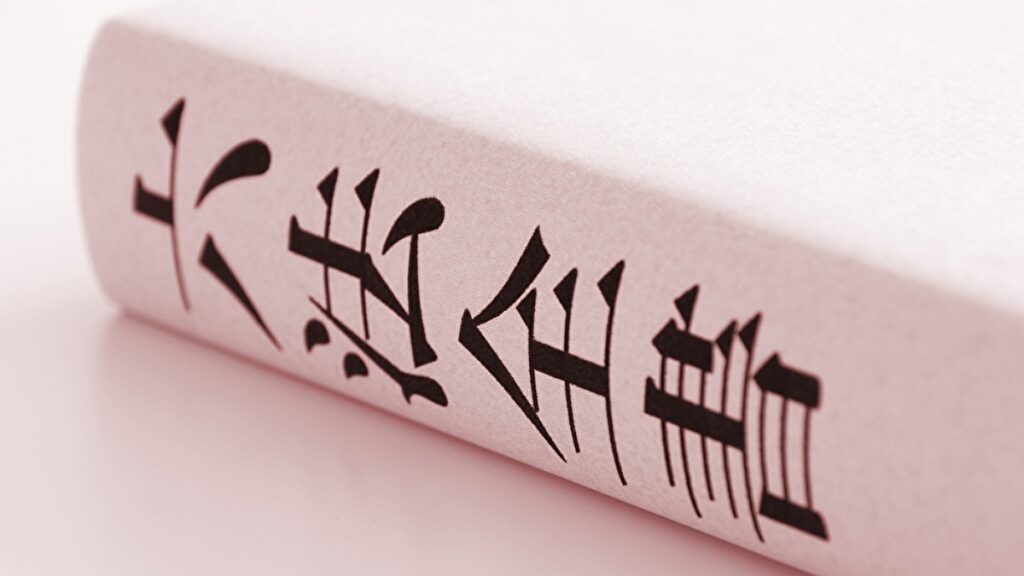
この資格の活かし方
初学者にとって法律の学習というのは範囲が広すぎて漠然としています。何から手を付けてよいのか分かりません。
そこで、初学者が法律を理解するための手段として法学検定を目標とすれば、学習をはじめるためのキッカケ作りとして活かせます。
法学検定試験に合格すれば、法律の知識が一定レベル以上あることを客観的に示せます。
例えば公務員試験や行政書士試験その他の国家試験に、法学検定で得た知識を活かせます。
中高生が受験する意味はあるのか?
将来弁護士になりたくて法学検定を受験する中学生や高校生もいますが、果たしてどれくらい意味があるのか・・・
![]() 参考:司法試験(予備試験)とは
参考:司法試験(予備試験)とは
確かに中高生のうちから法律を勉強すれば、理解も早まって多少法律の知識が身に付くかもしれません。
将来法学部へ進めばスタートラインでは少しリードしている可能性が高いでしょう。
しかし、しかしですね・・・法律の学習は中高生には早すぎます。
法律の勉強をするのと英語や数学の勉強をするのとはワケが違います。英語や数学は基礎からの積み上げですから若いうちから学習します。
中高生のうちに学習した法律の知識など、大学1年の5月で周囲の学生にすぐ追いつかれます。
中学生であれば、まずは進学校へ進むようできるだけ学校の勉強や定期試験に励んでください。
そして高校生になったら司法試験合格の実績のある大学の法学部へ進学できるよう日々学校の勉強に励んでください。
医者になるには医学部へ進学しなければなりません。医学部へ行くにために中高生が何を勉強するのかというと、数学、英語、物理、化学などであって医学の勉強ではありません。
それと同じです。最短で司法試験に合格するには、法学部へまずは進学することです。
法学部といってもピンからキリまであります。レベルの低い大学であればそもそも司法試験を目指す学生がいないので、司法試験向けのカリキュラムさえありません。
司法試験を目指す学生が多く合格者も多いレベルの高い法学部へ進学してください。それが司法試験合格につながる道です。
法科大学院へ進学するのも予備試験合格を目指すのもどちらでもかまいませんが、在学中に予備試験に合格するのが理想です。
仮に、高校生のうちに法学検定に合格して大学受験の願書にそれを書いても加点の材料になるかは疑問です。おそらくならないでしょう。
漢字検定や英検ならまだしも、法学検定は高校生の平素の勉強範囲から外れているからです。
合格するには
試験の種類と難易度
法学検定の受験級は難易度によって以下の3つに別れています。
- ベーシック〈基礎〉コース:法学部2年次程度
- スタンダード〈中級〉コース:標準的な法学部3年次程度
- アドバンスト〈上級〉コース:法曹を目指す等学習の進んでいる法学部3年次および法学部修了程度
合格に必要となる勉強時間の目安は以下の通りです。
- ベーシック〈基礎〉コース:知識ゼロからでも1か月
- スタンダード〈中級〉コース:ベーシックからさらに1か月
- アドバンスト〈上級〉コース:1年以上
合格率は概ね以下の通りです。
- ベーシック〈基礎〉コース:60~65%
- スタンダード〈中級〉コース:50~55%
- アドバンスト〈上級〉コース:15~20%
ベーシックコース、スタンダードコースの難易度は低い
法学検定のベーシックコース、スタンダードコースは、合格するだけであればそんなに難しくはありません。難易度は低めで比較的容易に合格できます。
法律の知識が全くない人でも問題集を1か月間やり込み、解説もしっかり読めば決して難しくはありません。法学部の学生であれば1週間の勉強で合格できます。
本試験では、公式問題集から6~7割は同じ問題が繰り返し出題されます。
そのため丸暗記でもある程度は回答できる可能性は高いです。
ただ、同じといっても選択肢の順番が入れ替わるケースはあります。
残り3~4割は、問題集と同じ問題は出題されませんが、解説の中から文脈を変えたような問題が出題されます。
内容はかなりのボリュームです。難しい内容も含まれているので、ある程度は根拠を理解しなければなりません。
公式問題集は解説も詳しいので、しっかりと読んで理解した上であれば、普通に合格点が取れます。
アドバンストコースは難関
最上位のアドバンストコースは、法科大学院の入学試験でも一定の評価対象になると言われているため格段に難易度は上がります。
ちょっとやそっとじゃ合格できません。
判例・学説等の深い理解に基づいた論理的・体系的な思考が求められます。単に暗記だけでは合格できません。
法科大学院を目指す大学3年生が受験します。
法科大学院既修者試験(法学既修者試験)について
法学検定委員会が2003年から運営・管理をしていた法学既修者試験は、2016年で終了となりました。
さらに、日弁連法務研究財団が運営・管理をしていた法科大学院統一適性試験は、受験者数の慢性的な減少により2019年に廃止。
上記試験に代わって、今後は法学検定アドバンストコースの結果を既修者認定のための参考資料とするようになりました。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・問題集
こちらは公式テキストです。法学検定はどちらかというとマイナーな検定試験なので需要は少なく、他の問題集は出ていません。
公式テキストが唯一の学習手段ともいえます。
試験で全く同じ問題が結構出題されます。事前の知識がある人であれば、このテキストを1回学習しただけで合格できます。
問題、解答、解説が分かりやすい配置になっており、民法・憲法・一般法学などを基本から勉強するのにも使えます。
| 種類 | 評価 |
| テキスト&問題集 |  |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
毎年1回11月下旬頃
お申し込み
9月上旬~10月中旬
受験資格
受験資格の制限は一切なく、どなたでも受験できます。
試験会場
札幌、仙台、東京、愛知、京都、大阪、岡山、愛媛、福岡、沖縄
受験料
- ベーシック〈基礎〉:4,400円
- スタンダード〈中級〉:6,600円
- アドバンスト〈上級〉:9,900円
※2024年4月3日現在の金額です。
試験内容
【ベーシック〈基礎〉コース】計60問120分
- 法学入門、憲法、民法、刑法
【スタンダード〈中級〉コース】計75問150分
- 法学一般、憲法、民法、刑法
- 選択1科目(民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法から1科目を当日選択)
【アドバンスト〈上級〉コース】計55問150分
- 法学基礎論、憲法、民法、刑法
- 民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法から1科目、これに労働法・倒産法・経済法・知的財産法を加えた中からもう1 科目の合計2科目選択
※試験はマークシート方式でおこなわれます。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は法学検定【2025年受験要項】(pdf)をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は法学検定【2025年受験要項】(pdf)をご覧ください。
