ビオトープ管理士とは?難易度や合格率・活かし方について
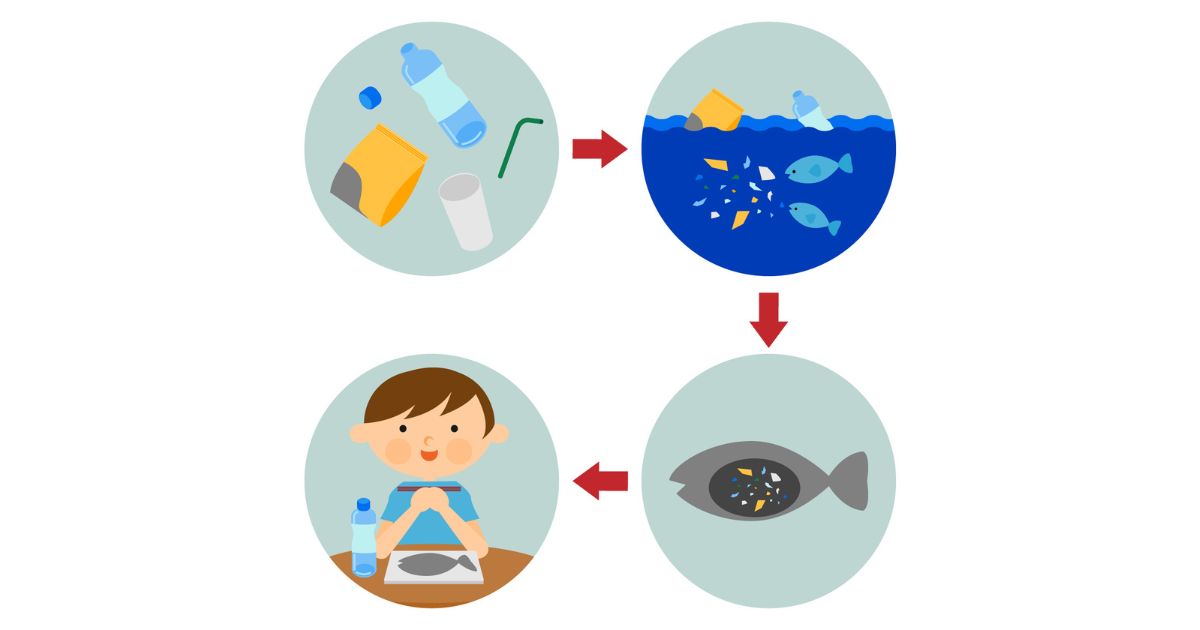
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 普通 | 50% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 2級は誰でも受験可 | ~2万円 | 5か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 2件 |
- 2級についてです。高校、大学レベルの生物の知識が必要です。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2026年1月19日に集計。
ビオトープ管理士は民間資格ですが、国土交通省の登録資格として公共性の高い一面もあります。
ただし、合格しても環境関連の会社への就職や転職は有利になりません。
環境分野の会社へ就職を希望するのであれば、求められるのは環境調査などの実務経験や大学院レベルの知識です。
民間資格は後から取れば十分です。
ビオトープ管理士とは

生態系の保護に関わる検定試験
ビオトープ管理士とは、生態系の保護に関する知識や技能について証明する民間資格です。
試験は、「計画部門」と「施工部門」に分かれており、それぞれの試験に合格すれば「ビオトープ計画管理士」「ビオトープ施行管理士」と名乗ることができます。
また、それぞれの区分は難易度の低い順に2級と1級に分かれています。
2級は誰でも受験できますが、1級は例えば4年生大学卒業後であれば7年以上の実務経験が必要です。
ビオトープとは、地球上の生物が生息する環境を意味する生物学用語です。
英語のバイオトープ(biotope)をドイツ語読みしたビオトープ(独:biotop)が語源です。ビオ(bio)はドイツ語で生命を意味します。
試験は日本生態系協会が主催しています。2級は筆記試験のみですが、1級は筆記試験に加えて記述問題と口述試験があります。
![]() 主催者サイト:ビオトープ管理士 公式サイト|(公財)日本生態系協会
主催者サイト:ビオトープ管理士 公式サイト|(公財)日本生態系協会
本当に役立つ民間資格なのか?

ビオトープに関する求人は皆無
ビオトープ管理士は民間資格です。
資格を有しているだけで就職や転職が有利になるわけではありません。
求人情報を検索しても、ビオトープ管理士を必要とする求人はまず見つかりません。
生態系の保護といっても、民間企業が積極的に参入する分野ではないので需要も非常に小さいです。
一部の資格紹介サイトでは、ビオトープ管理士の合格者は造園会社や土木会社、ハウスメーカー、材料メーカーなどの企業へ就職する際に有利になるなどと紹介していますが、これは少し無責任な表現です。
履歴書に書いてもおそらく評価されません。
自然環境調査を行っている企業であれば就職や転職が有利になる可能性はありますが、そこで求められるのは民間資格よりも環境調査などの実務経験や大学院レベルの知識です。
さらに、そういった環境調査を行う会社は非常に少数です。
環境に関する分野でキャリアアップを目指すのであれば、土木施工管理技士や技術士(環境部門)、公害防止管理者などの国家資格がおすすめです。
技術士(環境部門)は、環境省や国土交通省が発注する環境調査関連の仕事の入札参加の必須資格になっている場合もあります。
土木施工管理技士や技術士は、試験によっては実務経験を問われますが、公害防止管理者であれば問われないので誰でも受験できます。
将来性について徹底研究

国土交通省の登録資格と言っても価値は低い
ビオトープ管理士1級(計画管理士・施工管理士ともに)は、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格」として国土交通省の登録資格として認められています。
ただ、「国土交通省の登録資格」といっても、402もの民間資格が該当しています(令和7年2月14日付け資料)。ビオトープ管理士はそのうちの1つにすぎません。
![]() 参照:公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿(R7.2.14時点)(pdf)
参照:公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿(R7.2.14時点)(pdf)
登録資格とは何かと言うと、該当する資格の有資格者がいれば、公共事業の入札において多少有利になるという制度です。
つまり、ビオトープ管理士がいない業者よりビオトープ管理士がいる業者のほうが公共事業の落札がしやすくなります。
しかし、あくまでも環境に関する事前調査です。
土木工事そのものではないため金額も小さく件数も少ないです。
環境省や一部自治体が実施する環境調査業務の入札参加資格を得られる場合があるという程度です。
このためだけにビオトープ管理士1級を目指すのであれば、メリットはあまり期待できません。
ビオトープ管理士になるには

試験では高度な生物の知識を問われる
ビオトープ管理士の試験は、「計画部門」と「施工部門」のそれぞれにおいて難易度の低い順に2級と1級に区分されています。
合格率は、ともに2級全体が約50%、1級が約32%ほどです。
全ての試験で小論文があるため、しっかりとビオトープについての知識を身に付け、行動理念を学んで対策を立てなければ簡単には合格できません。
特に1級は「発展的な内容」について言及しなければならないのでしっかりとした自分の意見が必要です。
勉強方法としては、日本生態系協会が出している公式テキストがおすすめです。
過去問と類似した形式で出題されるので、公式テキストで過去問を中心に学習すれば、独学でも十分に合格できます。
また、年に1回開かれている2級受験者向けのセミナーに参加するのもいいでしょう。
試験では大学受験、大学教養レベルの生物の知識が求められます。
さらに環境関連の法律知識なども問われるので、範囲は広く、効率よく勉強しなければなりません。
公式サイトにおいて過去3年分の試験問題と解答が公開されているので参考にしてください。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
全試験科目の要点をわかりやすく解説した公式テキストです。2級の過去問題と解答・解説を収録しています。
ビオトープ管理士試験には公式テキストを使用して勉強するのが最も手っ取り早い方法です。これ1冊で試験対策ができます。
ただし、掲載されている過去問が少ないので、公式サイトで公開されている過去問も利用しましょう。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
筆記:9月、口述:12月
お申し込み
6月上旬~8月中旬
受験資格
2級:どなたでも受験できます。
1級:以下のいずれかの該当者
- 4年制大学卒業後、満7年以上の実務経験者
- 短大・専門学校・高等専門学校卒業後、満9年以上の実務経験者
- 高校卒業後、満11年以上の実務経験者
- ビオトープ管理者2級取得後、満7年以上の実務経験者
- 技術士(建設、農業、森林、水産、環境の5部門に限る)・1級土木施工管理技士・造園施工管理技士資格所持者で、資格を取得してからの実務経験が満4年以上の者、ほか
試験会場
- 1級・2級:札幌、仙台、新潟、東京、長野、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島、那覇
- 2級のみ実施:盛岡、金沢、徳島
※キャンパス受験制度やサテライト会場制度もあり
受験料
1級:11,300円(筆記試験合格の再受験:5,100円)
2級:7,200円
試験内容
出題範囲:
【1級】
《択一》50問
- 共通科(生態学、ビオトープ論、環境関連法)
- 専門科目(計画部門または施工部門)
《記述》4題+小論文1題
- 小論文(発展的な内容)
《口述》
- 筆記試験合格者のみ
【2級】
《択一》50問
- 共通科(生態学、ビオトープ論、環境関連法)
- 専門科目(計画部門または施工部門)
《記述》小論文1題
- 小論文
【難易度】
- 1級:経験の豊富な事業の責任者レベル
- 2級:基礎的な知識を有する技術者レベル
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報はビオトープ管理士 公式サイト|『受験の手引き』試験の要綱と受験申込用紙|(公財)日本生態系協会をご覧ください。
試験に関する詳しい情報はビオトープ管理士 公式サイト|『受験の手引き』試験の要綱と受験申込用紙|(公財)日本生態系協会をご覧ください。
