情報検定とは高校生向けの初歩的なIT系民間資格
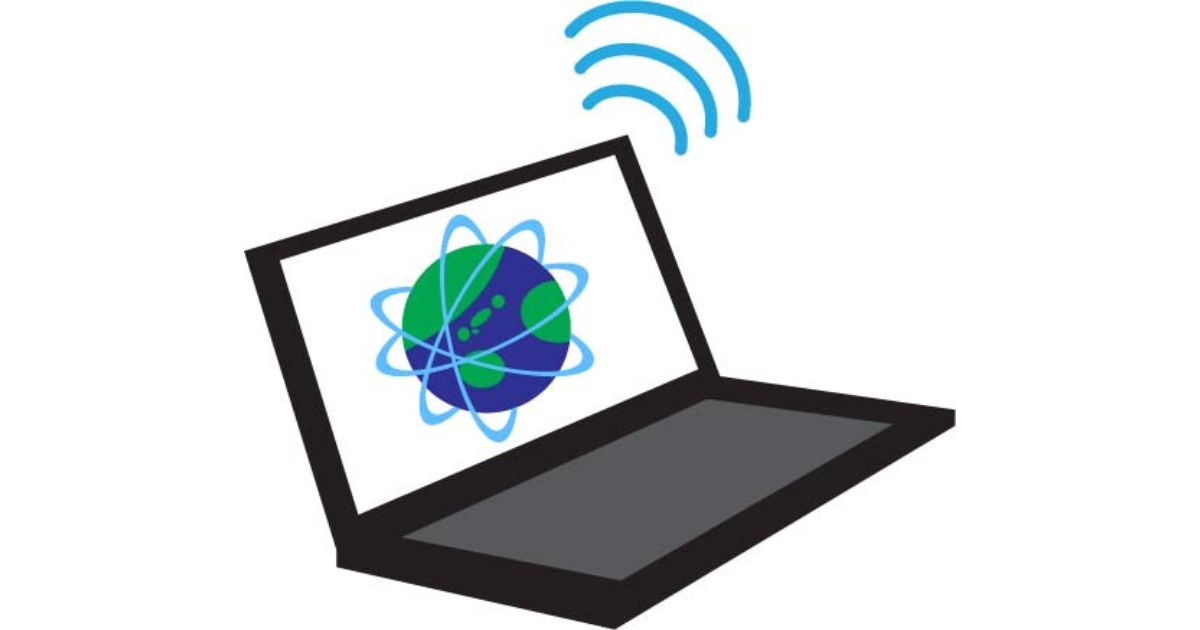
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | 63% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 1か月 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 入試でPR | 0件 |
- 情報活用試験3級についてです。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2026年1月10日に集計。
情報検定検(j検)とは、高校の商業科や情報科の生徒向けの検定試験です。
高校生が新卒で就職する際や、あるいは情報系の大学や専門学校へ進学する際は多少評価される可能性があります。
難易度は低いため初学者でも1か月ほどで合格できます。
そのため大学生や社会人が合格しても就活や転職には活かせません。
情報検定(J検)とは

かつては公的な検定試験
情報検定(J検)とは、情報を扱う人材に必要とされる基礎的なICT能力を評価する民間の検定試験です。
試験は、情報を「創る・使う・伝える」の3分野に分け、それぞれの評価基準を策定して以下の3種類実施しています。
- 情報システム試験
- 情報活用試験
- 情報デザイン試験
情報検定(J検)は、かつて文部科学省認定の情報処理活用能力検定(当時の通称もJ検)として開催されていた試験の後継になります。
情報処理活用能力検定が実施されていた1994年から2006年6月の間までは、文部科学省認定の公的資格という位置づけでした。
しかし、その後「認定」の制度は廃止され、現在は文部科学省後援の民間資格になっています。
高校生向けの民間資格として再スタート
情報処理活用能力検定が廃止になった理由は受験者が極端に減ったからです。
当時は、合格率の上昇などもあって基本情報技術者の国家試験に人気が集中しました。
そのためJ検の存在意義が薄れ、基本情報技術者試験と差別化をはかるという目的で一旦廃止になりました。
かつては社会人が対象だった試験ですが、情報検定(J検)と名称を変更するとともに、現在はどちらかというと高校生(商業科や情報科)・専門学校生などを対象としています。
情報処理活用能力検定を旧J検と呼び、現在のJ検と区別することもあります。
![]() 主催者サイト:情報検定:J検
主催者サイト:情報検定:J検
役に立つ資格なのか?
情報検定検は、高校の商業科や情報科の生徒、あるいは情報系の専門学校(HAL、電子専門学校等)の学生が在学中に受験します。
本来であれば国家資格の基本情報技術者試験くらいは合格したいところですが、能力的に難しい学生は情報検定だけでも取得します。
では、合格すれば高校生や専門学校生の就職が有利になるのかと言えば、もともと簡単な試験なのであまり評価されません。
1級や上級に合格すれば、ひょっとしたら面接担当者の目に止まるかもしれないという程度です。
大学生や社会人の就職・転職にはほとんど役立つことはありません。
もちろん履歴書に書くのは自由ですけど、知名度も低いため書かない方がいいような気がします。
将来性について徹底研究
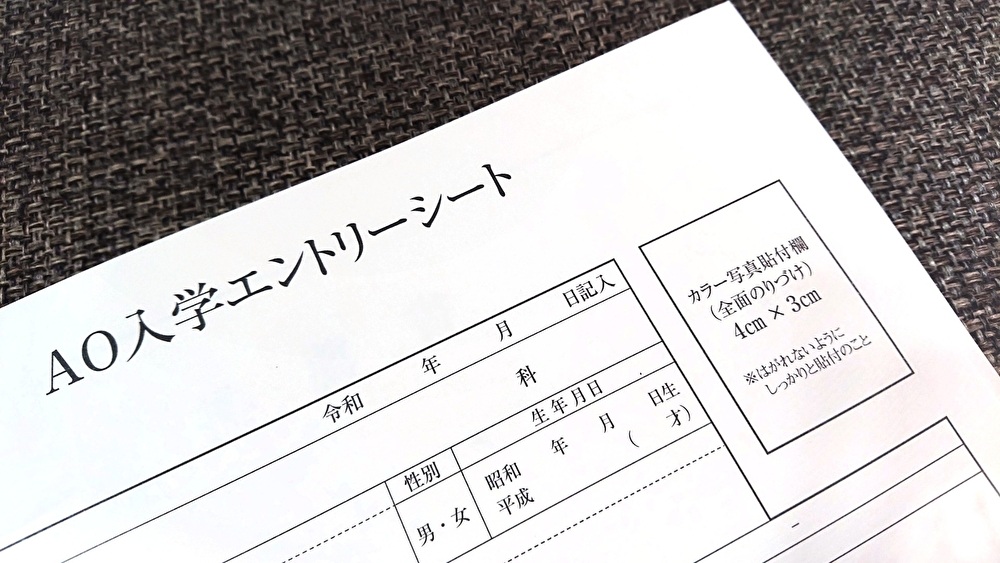
この資格の活かし方
これからIT業界を目指したい、Web関連の仕事につきたいと考えている高校生が、まずは第一歩として学習するにはちょうど良いでしょう。
学習する内容が超初心者レベルです。最も簡単な3級に合格すれば、これから先違う試験を目指すための自信につながるはずです。
合格しても何かに活かせる可能性は低いです。
取得するならITパスポート、最終的には基本情報技術者
情報検定を目指すのであれば、国家資格でもあるITパスポートがおすすめです。情報検定(J検)よりさらに試験の難易度・レベルは高くなります。
そして、さらにその上の基本情報技術者を目指すべきです。情報検定の学習をするのであれば、基本情報技術者試験に進むためのステップと考えましょう。
情報検定は民間試験、ITパスポート・基本情報技術者は国家試験です。その違いは大きいです。
情報処理技術者試験は、社会人でも評価されます。
合格するには

情報検定では、情報を扱う人材に必要とされる能力を以下のとおり3種類に分けて試験を実施しています。それぞれの試験はさらにいくつかの試験科目に分類されます。
- 情報システム試験・・・基本スキル/プログラミングスキル/システムデザインスキル
- 情報活用試験・・・3級/2級/1級
- 情報デザイン試験・・・初級/上級
団体向けに情報活用基礎の試験も実施されますが、これは情報活用試験3級と同等の内容です。
情報検定は制度変更後に大幅に難易度が下がりました。
情報活用試験の1級は難易度は高いのですが、それでもせいぜいITパスポートレベルです。
情報検定の情報活用試験は、数ある情報関係の検定の中でもかなり難易度の低い試験です。
3級であれば初歩、これから情報処理の学習をはじめる人が手始めに受ける試験です。
よほどのことがない限り不合格にはなりません。
2022年の情報活用試験3級の合格率は63.4%です。
情報検定は、いくつかの科目に分かれているため、いずれの試験科目も同日に受験できます。
情報検定の公式サイトには過去問題と解答が掲載されていますので、それを数回学習すれば合格できるでしょう。
仮に市販のテキストを購入したとしても、驚くほど薄いので無理なく学習できるはずです。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
情報検定の試験制度に対応した公式のテキストです。
情報活用3級の試験範囲を網羅しています。こういった検定試験は公式テキストに頼るのが一番確実です。
見開きで印刷されているため、見やすいのが特徴です。講義→確認問題→過去問題の3STEPで構成されています。
知識習得と問題演習があわせてできる1冊です。
| 種類 | 評価 |
| テキスト |
情報検定(新J検)情報活用試験3級に対応した公式テキスト・問題集です。
パソコンの操作・利用と役割・機能、情報の利用、情報モラルなどに関する基礎知識を習得できます。
ただ、掲載されている内容がかなり古く実用的ではありません。
| 種類 | 評価 |
| テキスト&問題集 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
- CBT方式は随時実施
- PBT方式(ペーパー方式)は前期と後期の2回
お申し込み
- CBT方式:随時受付
- PBT方式:手書願書と電子願書により違います。主催者サイトを参照
受験資格
どなたでも受験できます。
試験会場
全国のCBT試験会場、学校・団体が用意した会場
受験料
【情報システム試験】
- 基本スキル:3,500円
- プログラミングスキル:3,000円
- システムデザインスキル:3,000円
【情報活用試験】
- 1級:4,500円
- 2級:4,000円
- 3級:3,000円
【情報デザイン試験】
- 初級:4,000円
- 上級:4,500円
試験内容
情報検定(J検)には下記の3種類の試験があります。
- 情報システム試験
- 情報活用試験
- 情報デザイン試験
それぞれの試験分野等は以下のとおりです。
【情報システム試験】
[基本スキル]
- プログラミングやソフトウェア開発の基盤となる情報の表現・ハードウェア・基本ソフトウェアに関する基礎的知識
[プログラミングスキル]
- 想定処理に対して適切なデータ構造とアルゴリズムを適用できる能力
- 適切なテストケースを作成し、テスト結果の正当性を評価できる能力
[システムデザインスキル]
- システムの開発と、それに必要なネットワーク技術・データベース技術および、セキュリティと標準化に関する知識
【情報活用試験】
[3級]
- 情報化に主体的に対応するための基礎的な知識
- クライアント環境のパソコンの操作・利用と役割・機能、および情報の利用、情報モラルなどに関わる基礎知識
[2級]
- 情報社会の仕組みを理解するための基礎的知識
- クライアント環境のコンピュータと各種機器の役割と機能、環境設定の基礎知識
- ソフトウェアの種類と機能、インタ-ネットおよび情報モラルと情報セキュリティなどの基礎知識
[1級]
- 情報化社会で生活するための実践的能力
- ネットワーク環境にあるコンピュータと各種機器の役割、情報化社会に関わる諸問題および情報セキュリティに対応できる応用知識
【情報デザイン試験】
[初級][上級]
- 情報社会で問題解決をおこなう上での基礎的、実践的能力
- 情報デザインの考え方やモラル
- 情報の収集と整理、分析力
- 問題解決の手順、手法
- 情報構造の考え方、表現の手法
- 情報の伝達、評価とフィードバック
合格基準
【情報システム試験】
基本スキル、プログラミングスキル、システムデザインスキル
各科目:65点以上/100点
【情報活用試験】
1級・2級 :65点以上/100点
3級:70点以上/100点
【情報デザイン試験】
初級・上級:65点以上/100点
主催者情報
![]() 試験内容に関する詳しい案内はJ検の検定実施要項|情報検定:J検をご覧ください。
試験内容に関する詳しい案内はJ検の検定実施要項|情報検定:J検をご覧ください。
