学芸員の資格は役に立たない?博物館などへの就職は狭き門
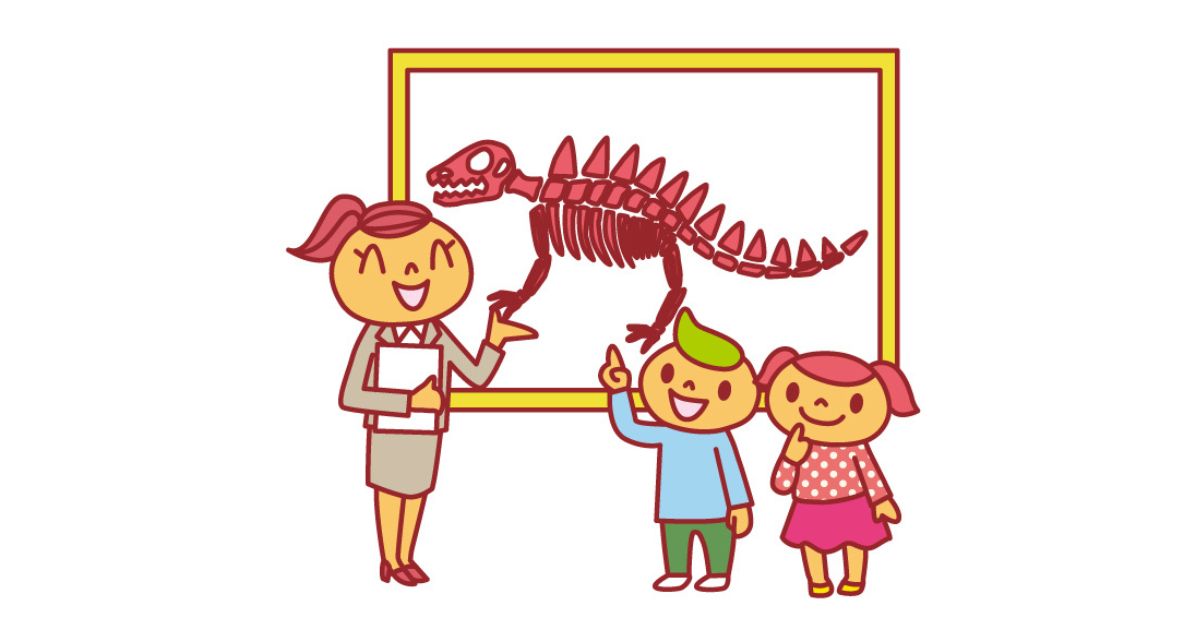
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | — | — |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 学歴その他 | — | 4年以上 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 76件 |
- 難易度、合格率は省略します。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月18日に集計。
学芸員とは、博物館や美術館において、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業を行う専門職です。
もともと「学芸員」という名称の資格があるわけではなく、いわゆる任用資格というものです。博物館等で任用されてはじめて学芸員と名乗れます。
有資格者はかなりの飽和状態なので、ただ取得しただけでは就職や転職が有利になるメリットはほぼないです。
学芸員として就職するには、前提として大学院卒が当たり前となっています。
※学芸員は独学で取れる資格ではありません。
学芸員とは
博物館の専門職員
学芸員とは、博物館法という法律で定められた博物館(美術館・動物園・水族館・植物園・天文台・科学館など)において、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業を行う専門職です。
博物館の施設運営に関わる仕事が中心になりますが、専門知識を活かした研究や調査も行います。
学芸員は、博物館や美術館の内部を案内する役割も担っています。分かりやすく説明するなどのコミュニケーション能力も求められます。
なお、学芸員補は、学芸員の職務を補助する役割を担います。
![]() 参考:学芸員について|文化庁
参考:学芸員について|文化庁
全国に5,738箇所の博物館がある!
博物館や美術館を訪れた経験がある人はきっと多いでしょう。
子ども達には恐竜博物館、昆虫博物館などが人気です。全国の水族館を巡るのが好きだという大人も珍しくありません。静かで落ち着いた雰囲気が大好きだという人もいます。
博物館の数は、少し古いデータですが平成30年10月の調査結果では全国に5,738館あります。
各都道府県あたり120館以上ですから相当な数の博物館が日本には存在します。
そんな博物館の中でも、博物館法第2条で定義された博物館のうち、都道府県教育委員会の審査を受け教育委員会に備える博物館登録原簿に登録された「登録博物館」において必須の専門職が学芸員です。
博物館法上の「登録博物館」には学芸員が必須
博物館の中には、学術的な価値の高い博物館・美術館から、憩いの場とも言える動物園、水族館、科学館など様々な施設があります。
日本における博物館は、博物館法で規定された「登録博物館」、登録を受けていないが登録博物館に相当する施設として指定された「博物館相当施設」、登録または指定を受けていない「博物館類似施設」の三種類に分類されます。
- 登録博物館(914)
- 博物館相当施設(372)
- 博物館類似施設(4,452)
※カッコ内は、平成30年10月調査時点における全国にある施設数です。
![]() 参照:1.博物館の概要|文化庁
参照:1.博物館の概要|文化庁
博物館相当施設とは、博物館法第29条により規定された施設です。
文部科学大臣または都道府県教育委員会の審査を受け、博物館に相当する施設として指定されたものです。
博物館類似施設とは、観光地によくあるような、なんとなく博物館っぽいアミューズメントパークのような施設です。テディベア博物館などです。
前述の通り、博物館法第で定義された博物館のうちの「登録博物館」において必須となるのが学芸員です。
その他の施設は博物館法で定義する博物館ではないため、学芸員はいなくても問題ありません。
役に立つ資格なのか?

学芸員はかなりの飽和状態
学芸員の資格は、大学・短大で学芸員課程の講義を受け、必要とされる単位を履修すれば取得できます。
では、就職や転職に役立つ資格なのかと言えば実はそうでもないようです。
学芸員の資格だけでは就職や転職は有利にはなりません。
司書・司書補と同じく取得してもほとんどの人が仕事で活かしていない、つまり持っているだけの資格だと言われています。
そして、学芸員は既に飽和状態にあります。
古いデータですが、平成30年10月現在で全国の学芸員の数は8,403人です。しかも年々増加傾向です。
一方、学芸員が必要となる登録博物館の数は914施設ですから、飽和状態どころか必要数の10倍近くいることになります。
新たな需要はほとんど無い状態です。
さらには学芸員として任用されていないだけで学芸員になる資格を有する人はその何倍もいるはずです。
就職はかなり狭き門
博物館・美術館では、基本的には大学院を卒業している前提で学芸員を募集します。
国立や県立などの名だたる美術館、博物館で働くには、かなりの専門知識が必要となります。
大学・短大で学芸員取得のためには約30単位必要ですが、3年生か4年生になったら博物館実習があります。
大学院まで進む予定はなく、将来学芸員として働く見込みが薄いとなると実習先を見つけるのが少し難しくなります。また、実習がちょうど就活時期とも重なります。
博物館の落ち着いた雰囲気が好きなので学芸員の資格を取得して就職したい・・・というワケにはいかないようです。
そういった意味では、あまり役立つ資格だとは言えません。
学芸員として就職するのはかなり狭き門です。
将来性について徹底研究
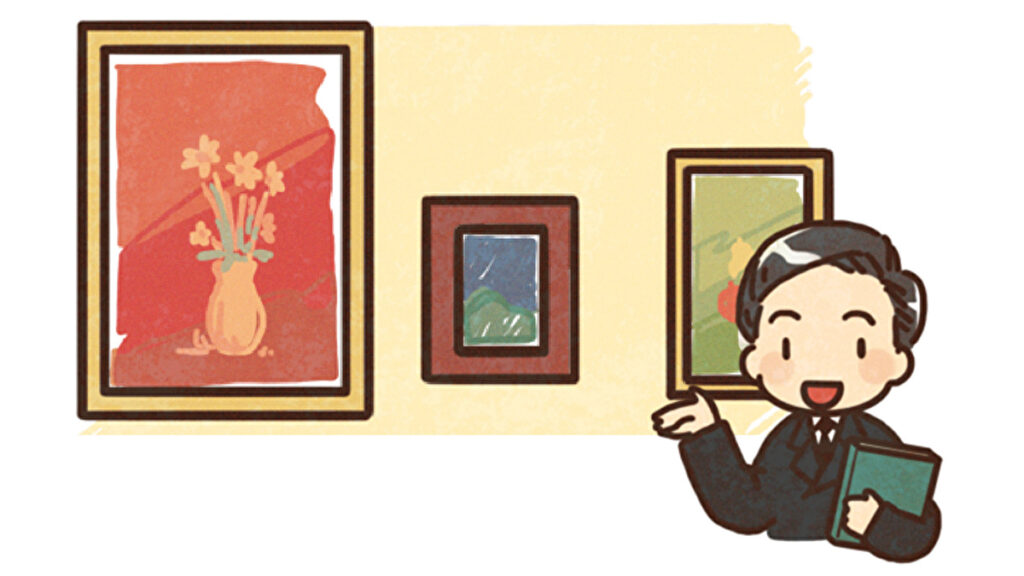
大学院卒じゃないと就職は困難
学芸員として就職するには、まず前提として大学院卒が当たり前となっています。
大学院へ進まなければ学芸員として就職することはほぼ不可能です。
大学院は修士と博士の課程がありますが、学芸員として働くには博士課程修了程度の高度な専門知識がが求められます。
博士課程を修了して、論文・書籍を多数執筆しているとか、その道では有名な研究者でなければ応募すらできません。
つまり、自分自身の専門分野と一致または関連する分野の博物館でなければ採用される見込みはないということです。
採用する博物館側も専門分野を指定します。
例えば、天文に関する学芸員を募集するとなると、昆虫や植物を専門としている人は採用される可能性はほぼないです。
さらには、欠員を補充するための求人がほとんどで、どこの博物館も定期的に職員を採用していません。
博物館が好きで就職したいという程度の理由だけなら取得は考え直した方がよさそうです。
時々、美術検定のような民間資格を持っていれば美術館で働けると考える人がいますが論外です。
パートや契約社員の求人なら少しは見つかるかも
大学院卒でないと学芸員の就職はほぼ不可能だと説明しましたが、実はハローワークインターネットサービスなどで検索すると、少ないながらも学芸員の求人が見つかります。
しかし、多くはパート職員の採用で、フルタイムの場合も契約社員や臨時職員といった採用が目立ちます。
登録博物館以外の小規模な民間の博物館類似施設でも学芸員の求人を出しているところもあります。
自治体が運営する博物館であっても、最近は民間に運営を委託するケースが増えています。
そういった場合、民間の企業で採用されて派遣社員として博物館で働くことになりますが、任期付き非正規雇用となり給料も安定しません。
驚くことに、パートや契約社員、臨時職員という採用であっても大学院卒はほぼ必須となっており、高い専門性が求められます。
学芸員という職種ではなく、受付スタッフとか運営スタッフなどの職種なら大学院卒のスキルは求められないので博物館で働ける可能性は高まります。
公務員として採用後、美術館へ異動というケースも
大学院まで進んで博士課程まで修了していないと学芸員として就職するのは難しいと説明しましたが、他にも学芸員として就職する方法があります。
それは、公務員として採用されて、その後博物館などへ異動する方法です。
もちろん最初から学芸員として採用される場合もありますが、事務職員・技術職員として採用後に学芸員に任用されるケースもあります。
博物館の運営を外部委託する自治体が増えているので希望が叶う可能性は低いかもしれません。何よりも公務員採用試験に合格しなければなりません。
しかし、採用になって、たまたま学芸員の資格を持っていたため同じ自治体が運営する博物館へ実際に異動になった人は少なからずいます。
司書の資格を持っていたために市立図書館へ配属になるケースと同じです。
学芸員の年収は250~400万円ほどだと言われています。しかし公立の博物館で公務員として雇われれば専門職公務員として給料がもらえるので安定します。
まぁ、確実な方法ではないですけど、大学入学後に学芸員と公務員を同時に目指すのもよいと思います。
学芸員になるには
学芸員になるには、原則として博物館法によって定められた受験資格が必要です。
次のいずれかに該当すれば受験資格を取得したことになります。
- 大学・短大で博物館に関する単位を履修した者
- 文部科学省で行う資格認定に合格した者
- 学芸員資格認定試験に合格した者
学芸員養成課程のある大学は現在290校あります。最近は減少傾向です。
![]() 参照:学芸員養成課程開講大学一覧(令和6年4月1日現在)290大学|文化庁
参照:学芸員養成課程開講大学一覧(令和6年4月1日現在)290大学|文化庁
通信制大学でも必要な科目を取れば資格を取得できます。聖徳大学、八洲学園大学など全国に10校ありますが、スクーリングや博物館実習も必修です。
また、大学に2年以上在学し所定の単位を修得して3年以上学芸員補の職にあった場合など学芸員の認定を受けられる方法もあります。
もともと「学芸員」という名称の資格があるわけではなく、いわゆる任用資格というものです。
資格を取得後、博物館等で任用されてはじめて学芸員と名乗れます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
筆者の郷土資料館での資料整理の経験を元に書かれていますが、作業内容自体は限りなく現実に近いです。
今までにない新しいジャンルの漫画です。4コマなので気軽に読めます。博物館の裏側を知りたい人や学芸員を目指している人にはおすすめの一冊です。
ちなみに、夜の作業中の怪談など、学芸員あるある話しが満載です。博物館・資料館の収蔵品整理にまつわる怪談って、どこの館でもあるようです。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
毎年1回12月(試験認定)
毎年1回1月(審査認定)
お申し込み
7月中旬~年8月下旬(ともにほぼ同じ)
受験資格
【試験認定の受験資格】
- 学士の学位を有する者
- 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者で2年以上学芸員補の職にあった者
- 教育職員の普通免許状を有し、2年以上教育職員の職にあった者
- 4年以上学芸員補の職にあった者
- その他文部大臣が同等以上の資格を有すると認めた者
【審査認定の受験資格】
- 修士もしくは博士の学位または専門職学位を有する者であって、2年以上学芸員補の職にあった者
- 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く)に関し2年以上教授、准教授、助教または講師の職にあった者であって、2年以上学芸員補の職にあった者
- 次のいずれかに該当する者であつて都道府県の教育委員会の推薦する者
- 学士の学位を有する者であって、4年以上学芸員補の職にあった者
- 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者であって、6年以上学芸員補の職にあった者
- 大学に入学することのできる者であって、8年以上学芸員補の職にあった者
- その他11年以上学芸員補の職にあった者
- その他文部科学大臣が同等以上の資格を有すると認めた者
試験会場
東京都
受験料
試験認定:1科目の受験につき1,300円
審査認定:3,800円
試験内容
資格取得するには試験認定と審査認定いずれかの方法があります。
■試験認定:筆記試験
【必須科目】
- 生涯学習概論
- 博物館概論
- 博物館経営論
- 博物館資料論
- 博物館資料保存論
- 博物館展示論
- 博物館教育論
- 博物館情報・メディア論
【選択科目】:以下から2科目を選択
- 文化史
- 美術史
- 考古学
- 民俗学
- 自然科学史
- 物理
- 化学
- 生物学
- 地学
■審査認定:面接
学芸員としての意欲、態度および向上心等を確認します。
合格発表
2月
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は学芸員の資格認定について|文化庁をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は学芸員の資格認定について|文化庁をご覧ください。
