年金アドバイザーとは?難易度や合格率・メリット等を解説

| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | やや易 | 60% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 誰でも受験可 | ~1万円 | 2か月 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 知識習得 | 7件 |
- 合格率等は4級についての数字です。3級の合格率は30%ほどです。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年5月12日に集計しました。
年金アドバイザーとは、複雑化する年金制度について基本的な理解を深め、お年寄りに年金の相談や助言・指導に対応するスキルを認定する検定試験です。
3級の合格率は30%ほどです。金融機関に勤める人は持っているととても役立ちます。
ただし、一般の人や学生が取得しても就職や転職が有利になるといったメリットは期待できません。
高い合格率が見込めるおすすめの通信講座
年金アドバイザーとは

年金制度を理解する検定試験
年金アドバイザー検定試験とは、複雑化する年金制度について基本的な理解を深め、主にお年寄りに対して年金の相談や助言・指導に対応するためのスキルを認定する民間資格です。
試験は、銀行業務検定協会が主催しています。窓口業務の一環として顧客からの年金相談に対応する機会の多い金融機関の職員が多く受験します。
実際に、年金アドバイザーは現役銀行員の受験者が目立ちます。
特に年金関連の知識が求められるのは、お客様と接する機会が多い渉外や窓口担当者です。
銀行の中には、新入社員に年金アドバイザー3級の合格を必須としているところもあるようです。
![]() 主催者サイト:検定試験|経済法令研究会
主催者サイト:検定試験|経済法令研究会
度重なる改正で複雑化する年金制度
この先、何歳になったらどれくらいの年金がもらえるのだろうか…、本当に年金がもらえるのだろうか…、若い人なら漠然としてあまり考えたことはないと思いますが、年を重ねるにつれ年金について考える機会は増えてきます。
国民年金、厚生年金といった公的年金に関する問題は奥が深く複雑です。
年金に直接関連する国民年金法・厚生年金保険法などの法律は、度重なる改正やその場しのぎ的な経過措置により例外規定や但し書きでいっぱいです。
年齢も違えば納めた金額、年数も違います。昭和一桁に生まれた人と平成に生まれた人とでは該当する法律の条文もまるで違います。
イレギュラーなケースが多いため、年金に関しては個別の対応が必要になります。人それぞれで100人いれば100のパターンがあるほどです。
一般の国民にとっては複雑でサッパリ内容が分からないような仕組みになっています。
役に立つ資格なのか?
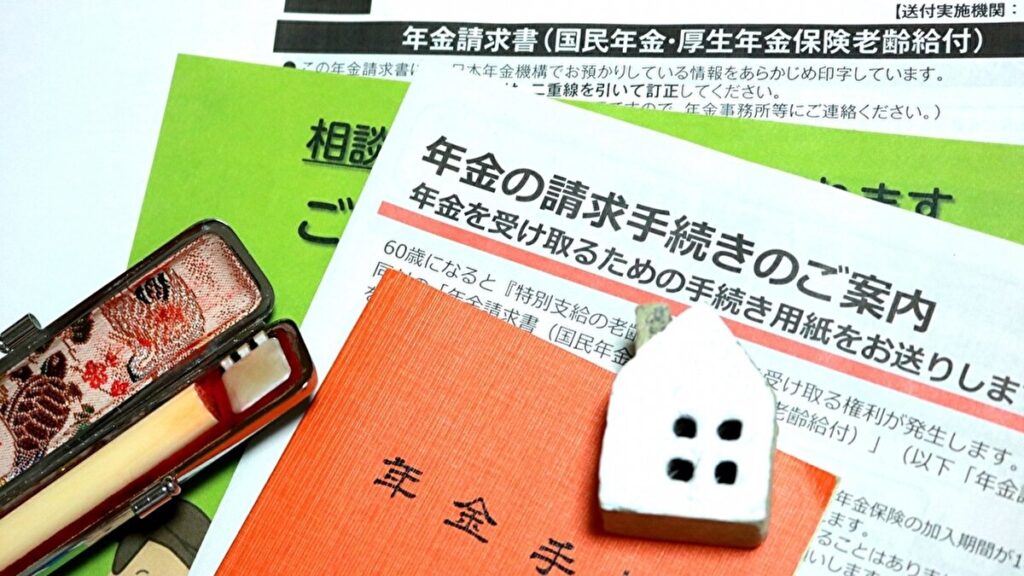
金融機関に勤務していれば知識は役に立つ
年金アドバイザーの資格は、金融機関に勤める人には役立ちます。
実際に、個人のお客から年金の相談を受ける機会は多く、質問に対してさっとアドバイスができればお客からの信頼を得られます。
金融機関の窓口の担当者について、年金アドバイザー3級合格が昇格の条件になっているところもあります。
金融機関に就職を希望する大学生が取得すれば評価の対象になりますが、それは3級以上です。
ただし、あくまでも参考程度です。明らかに就活が有利になるとまでは言えません。
金融機関に転職を希望する社会人にもおすすめですが、やはり転職が有利になるとまでは言えません。履歴書に書いても参考程度です。
銀行などは、基本的に学歴や職歴を重視するからです。
地方銀行などはコネなども・・・
年金検定との違い。どちらがおすすめ?
年金に関する民間資格では、年金検定などがあります。
では、年金アドバイザーと年金検定の違いは何かと言うと・・・
ともに年金の基礎について学ぶ民間資格という点では同じです。内容に違いはほぼありません。どちらが優位というものでもありません。
年金に関する基本的な知識を身に付けたいのであれば、試験対策用のテキストが市販されている年金アドバイザーをおすすめします。
それに、年金アドバイザーの合格者を採用条件とした求人も探せばわずかですが見つかります。
一方、年金検定は、知名度も低く社会的に認められているとは言い難いです。
年金検定は、「資格の学校TAC」が実施しています。
TACの通信講座または通学講座の売り込みが目的のような・・・そんな雰囲気すら感じます。
将来性について徹底研究
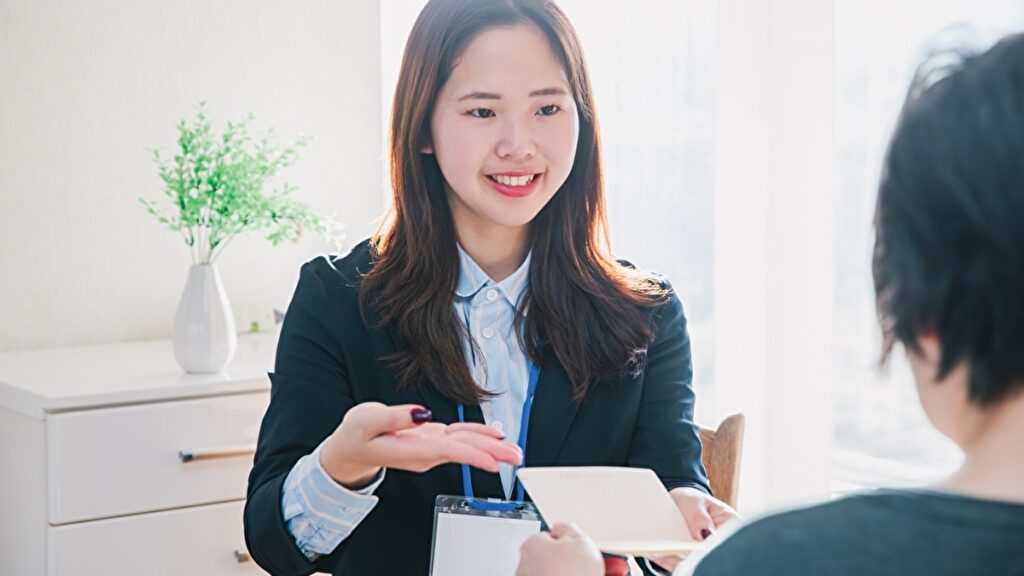
この民間資格の活かし方
年金アドバイザーの試験の学習を通して、年金制度の改革から年金給付の種類とその支給要件、年金額の計算方法まで、日本の社会保障制度の中心ともいえる年金制度について幅広い知識を得ることができます。
金融機関等で年金相談業務に従事する人はもちろんのこと、自己啓発の一環として年金に関する知識を得たい人にもおすすめです。
年金は国が行っている制度だからと安心して任せっぱなしにしてはいけません。
国がやっていることだから間違いはないだろう・・・なんて思ったら大きな間違いで、計算間違いや支給ミスなどは頻繁に発生しています。
年金制度の仕組みを学習して理解するのは、自分の身を守ることにもつながります。
年金アドバイザーにできる業務は非常に限定的
では、年金アドバイザーに合格すれば何ができるのか?
年金アドバイザーと言っても、法律で裏付けのある国家資格ではありません。民間の検定試験にすぎないので、できることは限られています。
年金アドバイザーとして可能な業務は、年金に関する「相談業務」です。
窓口に訪れたお客に対して、年金に関する一般的な事例や法律的な規定を説明します。
では、その相談業務が有料でできるかどうかは法律上少しグレーなところではありますが、おそらく違法でしょう。
有料で年金に関する相談業務ができるのは社会保険労務士に限定されると解されているからです。
さらに、お客の代わりに年金事務所や役所へ出す年金関係の書類を作成したり提出の代理をすることもできません。それは社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士以外はできません。
民間の検定試験では役に立つ機会も少ないです。実用性が高いとまでは言えません。
学習しても3級まで、2級を狙うなら社会保険労務士!
年金アドバイザーの試験には4級から最上位の2級まであります(1級はありません)。
4級は易しいため2か月程度の学習で合格可能です。
一般の人が年金について知識を得るには標準レベルである3級がおすすめです。
2級になると全て記述式の解答になり難易度が上がります。
試験では、実際に支給される年金の額を計算して解答します。
2級を目指すのであれば国家資格でもある社会保険労務士に是非挑戦してみてください。
簡単には合格できませんがより実用的で専門的な学習ができます。
そして何よりも資格の重みが全然違います。
年金アドバイザーとあわせて社会保険労務士を取得すると知識・業務ともに幅が広がります。
顧客からの要望に応えられる機会も増えるでしょう。
合格するには
過去問の勉強で合格できる
年金アドバイザー試験には4級、3級、2級があり、現状1級は実施していません。
最も一般的な3級試験では年金制度の概要、年金給付の種類や支給要件、裁定請求手続き、具体的な年金額の算出方法が問われます。
年金アドバイザー試験は過去問題集だけで合格できます。
3級までは実際に計算する問題も少ないので、内容の理解ができていれば解答できます。
マークシート方式の択一問題で出題パターンはある程度決まっているで、比較的取り組みやすい試験です。
実施される月の受験対策用の問題解説集を繰り返し解いて、出題形式や問題の解き方などに慣れれば合格できるくらいの実力は短期間で身に付きます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ問題集
経済法令研究会から出ている過去問題集です。こちらで学習することをおすすめします。
毎年おなじような問題が出るので過去問題集だけやれば十分合格できます。
※常に最新版として実施される月の受験対策用の問題解説集が発売されますので、自分の受験する月に合わせて購入するよう注意してください。
| 種類 | 評価 |
| 問題集 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
毎年10月下旬と3月上旬、年に2回実施
お申し込み
試験日の約2か月前
受験資格
受験資格の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
試験会場
全国各地
受験料
- 2級:8,250円
- 3級:5,500円
- 4級:4,950円
試験内容
※年金アドバイザー3級の科目構成
五答択一形式(マークシート式)問題が計50問出題されます。
(1)基本知識:五答択一式 30問 (各2点)
(2)技能・応用:事例付五答択一式 10事例 20問 (各2点)
- わが国の社会保険制度とその仕組み
- 年金制度とその仕組み
- 年金給付の種類と支給要件
- 企業年金個人年金の仕組みの要点
- 裁定請求手続きと年金受給者の手続き
- その他
合格基準
満点の60%以上(試験委員会にて最終決定)
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は試験種目一覧|経済法令研究会をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は試験種目一覧|経済法令研究会をご覧ください。
