有機溶剤作業主任者とは講習受講で99%の合格率の国家資格
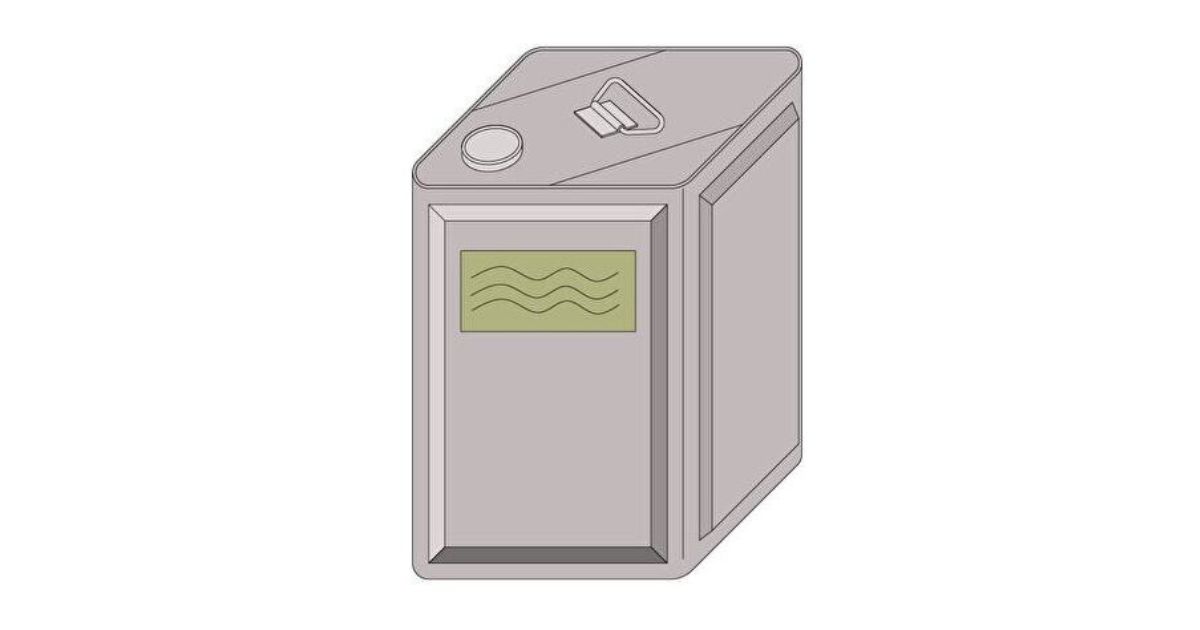
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | 易しい | 99% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 講習受講 | ~2万円 | 2日間 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| スキルアップ | 167件 |
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年8月15日に集計。
有機溶剤作業主任者とは、有機溶剤を取り扱う現場で従業員などの身体に危険が及ばないように指揮・監督する責任者です。
合格率は高く2日間の講習でほぼ全員合格できます。
有機溶剤を用いる現場は多く、需要があり取得するメリットがある国家資格です。
※令和8年を目途に有機溶剤作業主任者を含む化学物質関連の作業主任者制度は廃止すると発表されています(後述)。
有機溶剤作業主任者とは

有機溶剤を正しく使うための責任者
有機溶剤作業主任者とは、有機溶剤を取り扱う現場で、従業員などの身体に危険が及ばないように指揮・監督する責任者です。
従業員が有機溶剤を取り扱う仕事をする際に、現場で作業方法を決めたり作業の指揮をします。
また、保護具が使用されているかどうかの確認、有機溶剤中毒防止措置が適切であるかの確認、機器類の点検なども有機溶剤作業主任者の大切な仕事です。
有機溶剤を製造または取り扱う事業者は、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任して、労働者の作業指揮・その他規則で定められた職務を行わせなければなりません(労働安全衛生法第14条)。
※講習を修了して、職場で「選任」されてはじめて有機溶剤作業主任者と名乗れます。単に修了しただけでは有資格者にすぎません。
![]() 参照:有機溶剤を正しく使いましょう|厚生労働省
参照:有機溶剤を正しく使いましょう|厚生労働省
※有機溶剤を正しく使いましょう(pdf)において詳しく説明しています。
有機溶剤とは
有機溶剤とは、他の物質を溶かすことができる有機化合物のことです。
クロロホルム、アセトン、ベンゼン、エタノール、ガソリンなどが該当します。
これらは水には溶けない油やロウ、樹脂、ゴム、塗料などを溶かすために用いられます。
有機溶剤を用いる現場は多く、様々な職場で溶剤として塗装・洗浄・印刷等の作業に幅広く使用されています。
例えば、自動車や家などの塗装、工場内での機械類の洗浄、印刷業ではインクの拭き取りに使用されたりしています。
さらに、有機溶剤の製造所はもちろんのこと、化学繊維や合成樹脂の工場、医薬品製造、印刷加工、クリーニング業などで幅広く用いられています。
毒性が高く取り扱いには注意が必要
有機溶剤は常温では液体ですが、一般的に揮発性が高いため常温でも蒸発する場合があります。
蒸気(有毒ガス)になると作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
体内に吸収されると中毒症状(吐き気、頭痛)を起こす可能性があります。
有機溶剤を誤って使用すると重大な労働災害につながります。
有機溶剤業務従事者との違い
ちなみに、有機溶剤業務従事者とは、実際に有機溶剤を取り扱う業務に従事している者(作業者)をいいます。
特別(準)教育を受講して修了することで得られますが資格とは違います。有機溶剤中毒に関する予防知識を持たせるための教育です。
中毒を起こす可能性がある仕事に従事しているようであれば受講した方がよいでしょう。
作業主任者はこの教育を受ける必要はありません。
役に立つ資格なのか?

やはり経験が求められる
有機溶剤を取り扱う会社では有機溶剤作業主任者は必要な存在です。
自動車整備工場、塗装作業が伴う工場、化学工場、印刷会社、クリーニング店、医薬品・香料の製造などの現場でこの資格を活かせます。
とは言え、有機溶剤作業主任者の資格は2日間の講習を受講すれば誰でも簡単に取得できます。
有機溶剤を取り扱う職場であれば、現場責任者クラスが1人講習へ行けば足ります。
万が一のために他の従業員にも取らせるかもしれませんが、全員が取得する必要はありません。
そのため、持っていても損はしませんが就職や転職が有利になるというほどでもありません。
採用の決定打になるとまでは言えず、やはり経験が求められます。
有機溶剤を扱う現場の多くは工場で、重量物を扱う機会が多いです。
講習をうけて習得するのであれば、フォークリフトの方がほうが需要があります。
![]() 関連資格:フォークリフト運転技能講習とは
関連資格:フォークリフト運転技能講習とは
就職・転職という面から意味から考えると、有機溶剤作業主任者の需要は少ないです。
将来性について徹底研究
危険物取扱者の資格があるとさらに役立つ
有機溶剤の中には、ガソリンやアセトンのように危険物に指定されるものもあります。
その場合、有機溶剤の保管は有機溶剤作業主任者では行えません。
危険物に指定されている有機溶剤が指定数量以上保管されている場合、貯蔵に関する業務を行うには該当する種類の危険物取扱者の国家資格が必要です。
ただし、危険物取扱者の資格を取得しても有機溶剤作業主任者の仕事は行なえません。
例えば、有機溶剤を安全に使うための指導などはできません。
それは、両者は全く別の資格だからです。
危険物取扱者は自治省の消防法によって規定されていますが、有機溶剤作業主任者は厚生労働省の労働安全衛生法によって規定されています。
有機溶剤を取り扱い、なおかつ貯蔵する事業所であれば、有機溶剤作業主任者と危険取扱者の資格を両方持っているとメリットが大きく役に立ちます。
特定化学物質作業主任者は全く別の資格
特定化学物質を扱う現場では、特定化学物質作業主任者を置かなければなりませんが、有機溶剤作業主任者として選任されても特定化学物質作業主任者にはなれません。
両者は別の資格になるので、改めて取得する必要があります。
特定化学物質作業主任者は、作業者が特定化学物質に汚染されないよう作業方法などを指導したりする資格です。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受講すれば取得でき、四アルキル鉛作業主任者にも選任することができます。
2006年3月31日以前は石綿作業主任者にも選任されることができましたが、現在では石綿作業主任者技能講習を別に受講しなければなりません。
これらは受講資格は特になく2日間の講習で取得できます。
※なお、クロロホルムなどの有機溶剤は発がん性が疑われたため、平成26年11月1日に特定化学物質に移行し特別有機溶剤となりました。特別有機溶剤を用いて作業する場合は、有機溶剤作業主任者技能講習修了者から特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
化学物質関連の作業主任者制度は廃止?
厚生労働省によると、有機溶剤作業主任者と特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者、鉛作業主任者、石綿作業主任者などの化学物質関連の作業主任者制度を、5年後(令和8年)を目途に廃止すると発表しています。
![]() 参照:化学物質規制の見直しについて|令和3年7月19日厚生労働省化学物質対策課(pdf)
参照:化学物質規制の見直しについて|令和3年7月19日厚生労働省化学物質対策課(pdf)
※4ページ参照
いろいろと廃止の噂はありましたが、ほぼ正式に廃止は決まったようです。
合格するには
2日間の講習で取得可能
有機溶剤作業主任者の資格を取得するには、都道府県労働基準協会、登録教習機関などが開催している有機溶剤作業主任者技能講習を受講します。
講習は2日間です。最終日に修了試験が実施され、これに合格すると有機溶剤作業主任者になるためのの資格を得ます。
なお、実技試験などはありません。筆記試験のみです。受講資格の制限などもなく、全くの知識ゼロでも受講できます。
受講料は教材費も含めて、およそ1~1.5万円ほどです。主催者により若干違います。
なお、講習は全国各地で開催されています。4~5月は特に受講希望者が集中するようで、その頃だけ月に3回ほど開催する会場もあります。
ほぼ全員合格できる程度の難易度
計算問題は出題されません。2日間の講習を、居眠りをせずにしっかりと聞いていれば大丈夫です。事前の勉強も必要ないです。
残念ながらマレに落ちる人はいますが、居眠りしていて講義を聴いていない人くらいです。講習の時間に遅刻した人も不合格になる可能性はあります。
講習の途中に、試験に出そうな重要な箇所は講師がアンダーラインを引くよう指示があります。
あるいは講師によっては2日めの講義終了10分くらい前に、出題箇所だけに絞って復習をします。試験は50問で四者択一問題です。
心配であれば、講習は2日間あるので初日は家に帰ってから何度も重要な箇所を確認しましょう。
2日めも講習の合間に休憩時間があるので、その度に10回くらい反復学習しましょう。
仮に修了試験に落ちたとしても、実施団体によっては再試験が行われます。
技能講習は取得させるのが目的です。なんとか全員合格させようと講義中に出題される部分を教えてくれます。それでほぼ99%の合格率なんです。
テキスト・問題集・参考書
おすすめテキスト・基本書
作業主任者になるための技能講習用テキストです。実際に講習を受ける人は購入しなくても大丈夫です。
試験でやたらと出てくる化学物質について、具体的な性質や取り扱う業務、危険性などについて詳しく解説しています。
※Amazonで販売していないようでしたら、中央労働災害防止協会公式サイトより購入してください。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
講習情報
日程・受講資格・内容・その他
開催日
各都道府県で月に数回程度実施
お申し込み
主催者により異なります。
受講資格
原則として誰でも受講できますが、18歳以上に制限している教習機関もあります。
※就業できるのは18歳以上です。
講習会場
各都道府県
受講料
教材費も含めて、およそ1~1.5万円ほどです。主催者により若干違います。
講習の内容
【1日め】
- 健康障害及びその予防措置に関する知識 4時間
- 保護具に関する知識 2時間
【2日め】
- 作業環境の改善方法に関する知識 4時間
- 関係法令 2時間
- 修了試験 1時間
合格基準
全講習科目の所定時間を修了し、修了試験において各科目40%以上、かつ総合で60点以上の得点で合格。
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は各主催者のホームページをご覧ください。
試験に関する詳しい情報は各主催者のホームページをご覧ください。
