終活アドバイザーの民間資格ってどれくらい役に立つの?
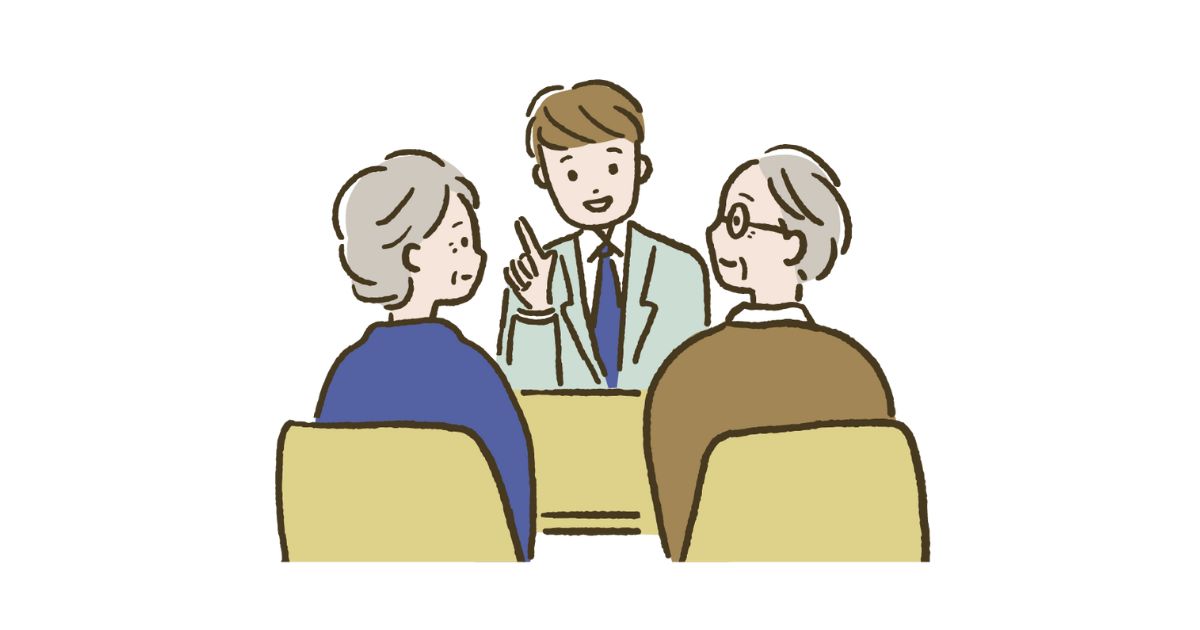
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | — |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 指定講座受講 | ~4万円 | 1か月程度 |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 要再考 | 0件 |  |
- 合格率は非公開ですが添削課題を全て提出すればほぼ全員合格できます。
- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年5月14日に集計。
- 取得に関しては再考をおすすめします。
| 講座受講料 | 39,000円 |
| その他費用 (任意) | 入会金:4,000円 年会費:6,000円 |
- 金額は税込み、2025年8月15日現在です。
終活アドバイザーの民間資格に合格しても、法律的な業務(公的な書類の代理作成・代理申請、相続税に関すること)などは一切できません。
こういった民間資格の通信講座を受講して短期間で合格して・・・それで一体何ができるのか?受講を検討している人はその点を考えてみるといいでしょう。
終活に関する民間資格は多数存在しますが、どれを取得しても特別にできる業務はありません。
終活アドバイザーとは

家族に迷惑をかけないための準備のお手伝い
終活アドバイザーとは、終末期や死後に関わる様々な準備や手続きについてサポートする専門家を目指す民間資格です。
試験の学習を通して終活の基礎知識をはじめ、社会保険制度、財産管理や相続対策、公的制度の仕組み、お葬式、お墓のことなど、幅広い知識を身に付ける狙いがあります。
終活アドバイザーの『終活』とは、自分や遺された家族が困らないよう、そして最期まで自分らしく生きるための、人生の最期に向けた準備活動のことを言います。
![]() 主催者サイト:終活アドバイザー協会|終活の専門家集団NPO法人ら・し・さ の資格認定団体
主催者サイト:終活アドバイザー協会|終活の専門家集団NPO法人ら・し・さ の資格認定団体
終活に関する民間資格が乱立してるけど・・・
こういった終活に関する民間資格は実は多数存在します。
終活カウンセラー、終活ライフプランナー、終活ライフケアアドバイザー、終活ライフコーディネーター、終活ガイド、終活マイスター、終活士、終活診断士・・・
まだまだたくさんあります。
終活アドバイザーと終活カウンセラーの違いは何?そう感じている人はきっと少なうないと思いますが、違いは特にありません。
どれも、民間検定試験ですから、合格したからと言って特別にできる仕事はありません。
役に立つ民間資格なのか?

できることはエンディングノートの作成手伝と相談程度
こういった民間資格について勉強することはもちろん否定しません。
しっかり勉強すれば相続に関する基礎知識くらいは身に付くでしょう。
終活アドバイザーにできることは、エンディングノートの作成の手伝いと終活全般に関わる相談業務です。
他にできることは専門家の紹介です。
ただし、相続に関わる税金などの相談はできません。国民年金や厚生年金等に関して有料で相談にのることもできません。
無資格者でもできる「指導・相談」にお金を払う人がどれくらいいるのか・・・終活アドバイザーの民間資格だけで稼ぐのは難しいと思います。
もちろん、就職や転職が有利になるとは考えない方がいいです。
目指すなら独占業務のある国家資格
終活を意識するお年寄りから受ける相談は、預貯金などの金融資産や不動産の相続、その際に発生する税金、さらには成年後見、死後事務委任など様々です。
こういった専門的な相談となると相続税法、民法、不動産登記法などに関する高度な専門知識と国家資格が必要です。
税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士そして弁護士などであれば知識が業務に役立つでしょう。
相続のスペシャリストを目指したいのであれば、上記のような国家資格が必要です。
例えば、相続税に関する相談などは無料であっても税理士以外はできません。試算などもできません。
相続税の計算と申告については税理士の資格が必要です。司法書士、行政書士であれば相続に関する独占業務があります。
社会保険労務士であれば健康保険・介護保険の資格喪失届提出、年金受給停止手続きの代理申請ができます。
弁護士の資格があれば言わずもがなです。
将来性について徹底研究

終活アドバイザーの求人について
『終活』に関わる全国の求人を調べてみると、約60件ほど見つかりました。
驚くことに、その多くは葬儀場、仏壇・仏具・墓石販売店、葬儀の返礼品販売会社などです。
ただし、ほとんどが「資格不問」という条件です。
最近の葬儀場は、亡くなる前に営業活動をして葬儀の予約を取り付けるための営業活動に一生懸命なようです。
試しに、終活アドバイザー、あるいはその他終活に関する資格所有者が有利になる求人を探してみましたけど、見つかりませんでした。
実際の現場では、民間資格の有無はあまり関係ないようです。
仮に終活アドバイザーの民間資格が必要であれば、社員に取得させればそれで済みます。
外部からわざわざ採用する必要など全くありません。
終活アドバイザーになるには
ユーキャンの通信教育受講が必須
終活アドバイザーを取得するには、ユーキャンが実施する「終活アドバイザー講座」を受講しなければなりません。
内容は、添削課題3回+修了課題(検定試験)です。
試験といっても自宅で課題を解いて提出するだけです。不合格になる方が不思議です。
標準学習期間は4か月(受講開始から8か月まで指導)となっていますが、1か月もあれば十分合格できる程度の難易度です。
なお、合格後の登録料と年会費は任意です。運営団体の特定非営利活動法人ら・し・さに支払います。
入会すると特典があるようですが、詳しくは主催者公式サイトを参照してください。
他の終活系民間の検定試験はどれも概ね指定の講座受講が必須となっています。
中には資格商法的な通信講座もあるので注意してください。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
身近な人が亡くなると、さまざまな手続きを進めなければなりません。
まずは役所関係です。7日以内に死亡届・火葬許可申請書を提出しなければなりません。同時に通夜・葬儀・納骨・・・
さらに、健康保険、介護保険、年金受給停止、公共料金の変更・解約、相続・・・まだまだたくさんあります。
本書は、そのような手続きについての152の質問を取り上げ、第一線の弁護士・税理士・社会保険労務士が本音で回答しています。
エンディングノートなどの生前対策にも対応しています。
縁起でもない・・・という考えも理解できますが、読むと納得できます。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
大人気の終活セミナーに参加した3,000人の受講者の声をもとに作られた「一番わかりやすい」エンディングノートです。
エンディングノート作成のためのノウハウがこの1冊にまとまっています。特に難しくなくスラスラ書けます。
順番に書き込むだけで終活が完成します。「もしも」のときに安心です。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
試験情報
日程・出題内容・合格基準・その他
試験日
随時実施(自宅受験)
お申し込み
随時受付(通信講座の申込み)
受験資格
ユーキャンの指定通信講座受講が条件となっています。
試験会場
在宅受験です。
通信講座受講料
39,000円(税込、一括の場合)
講座(試験)内容
標準学習期間は4か月(添削回数3回 + 修了課題を提出)
- 終活とは
- お金・金融資産・不動産
- 公的医療・公的介護保険、年金
- 高齢期の医療や介護
- お葬式やお墓の知識
- エンディングノートと終活
- 資産や物の整理
- 成年後見制度
- 高齢者施設
- 相続
修了課題「終活アドバイザー検定試験」
※マークシート方式
合格基準
全体の60%以上の正解で合格
※不合格だった場合でも、受講期間内ならいつでも再受験が可能です。
主催者情報
![]() 指定の通信講座に関する詳しい情報は講座のご紹介|終活アドバイザー協会をご覧ください。
指定の通信講座に関する詳しい情報は講座のご紹介|終活アドバイザー協会をご覧ください。
