サービス介助士とは?履歴書に書いても就職には影響ない
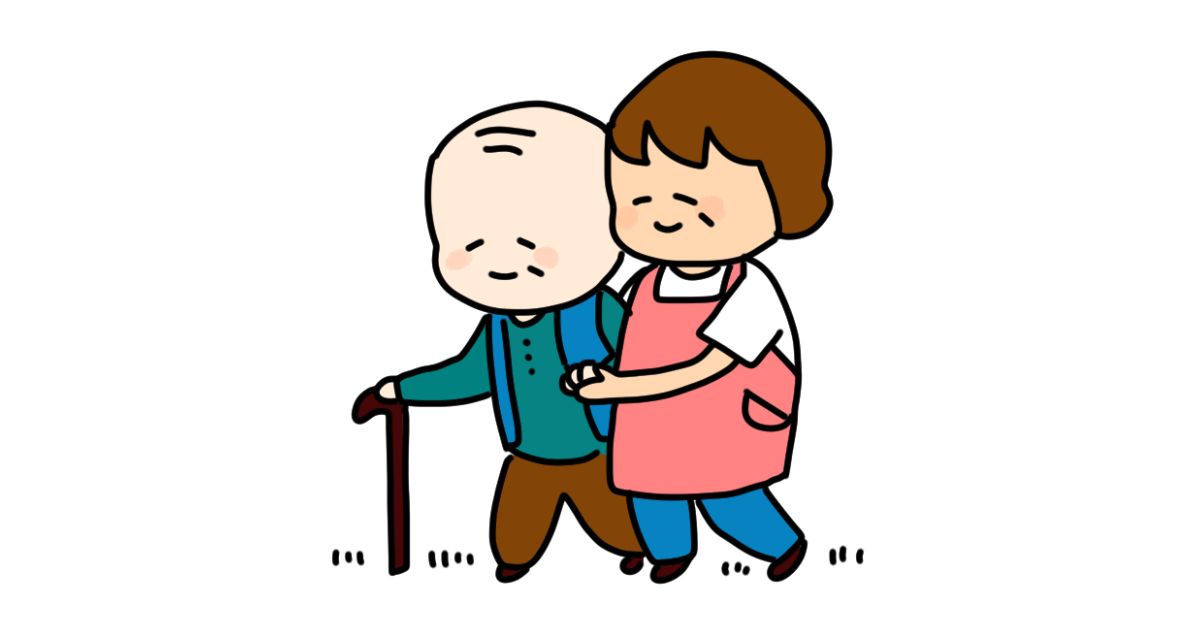
| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 民間資格 | 易しい | 90% |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 指定講座受講 | 5~10万円 | 1週間程度 |
| 活かし方 | 全国求人数 | おすすめ度 |
| 要再考 | 1件 |
- 全国求人数は、ハローワークの求人情報を基に2025年7月14日に集計しました。
- 取得に関しては再考をおすすめします。
| 試験の級 | サービス介助士、サービス介助基礎研修(セミナー)、准サービス介助士 |
| 講座受講料 | サービス介助士:41,800円 サービス介助基礎研修:6,600円 准サービス介助士:22,000円 |
| 受験料 | 上記金額に含まれます。 |
| その他費用 | サービス介助士:更新料1,650円/3年(税込) 他は無し |
※金額は2025年7月現在です。
サービス介助士とは、サービス業の現場において高齢者や身体の不自由な人に対する正しい手助け・介助・サポートの方法を学ぶための民間の検定試験です。
実は、企業のイメージアップ戦略の一環として従業員に取得させるケースが多いようです。
企業のイメージが良くなれば売上向上につながります。就活セミナーに学生が集まりやすくなり、優秀な学生を採用しやすくなります。
では、学生や社会人が取得すれば就活や転職が有利になるのかと言えば、ほぼ影響しないでしょう。
講習受講で90%以上の合格率です。履歴書に書いて採用が有利になるなんてことはありません。
サービス介助士とは

介護の一歩手前の「お手伝い」
サービス介助士とは、主にサービス業の現場において、高齢者や身体の不自由な人に対する正しい手助け・介助・サポートの方法を学ぶための民間の検定試験です。
駅のホームへ向かう階段で、車椅子の人が段差を越えられずに困っていたらどうお手伝いしたらよいのか・・・白い杖を持った人が道に迷っていたらどう声をかければよいのか・・・そういった基本的なお手伝いの方法を講習会を通して学びます。
必要な知識は介護技術ではなく、あくまでも介護の一歩手前のお手伝い、つまり「介助」の知識です。
正しい対処方法や接し方を知っていたら安心してお手伝いができます。
![]() 主催者サイト:サービス介助士|公益財団法人日本ケアフィット共育機構
主催者サイト:サービス介助士|公益財団法人日本ケアフィット共育機構
目的は公共の場での接客・接遇
例えば、サービス介助士の知識を活かせる場は、ホテル、レストラン、駅のホームやバス乗り場、タクシー乗り場、ショッピングセンター、映画館などの公共的な施設です。
介助の方法を知っていれば、障害者の人を不快に感じさせることなく、本来のサービスを健常者と同じように気持ちよく受けてもらえます。
つまり、サービス介助士の本来の目的は、接客・接遇などの「おもてなしの心」を持つことです。
サービス介助士は、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が主催する民間の検定試験で、ケアフィッターとも呼ばれています。
役に立つ資格なのか?

企業のイメージアップ戦略の道具
試験を主催する日本ケアフィット共育機構のホームページを見ると、全国約1000社の企業にサービス介助士が導入されていることがわかります。
![]() 参照:導入実績・受講者の声|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構
参照:導入実績・受講者の声|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構
導入企業一覧を見ると、日本を代表するような名だたる大企業ばかりです。
では、なぜこのような民間資格をこぞって大企業が導入するのでしょうか?理由は簡単です。
サービス介助士の活かし方、それはズバリ「企業のイメージアップ」です。
サービス介助士になると、ブルーのクローバーをデザインしたバッジを胸に付けられます(もちろん有料)。
「お気軽にお声がけください」と印刷されたシールやPOPスタンドお店に掲げてPRできます。
サービス介助士の資格を社員に積極的に取得させている会社も多いようですが、お店や会社にサービス介助士がいることをPRして、イメージアップにつなげるのが一番の目的です。
ネット上で評判がすぐに拡散するこの世の中、障害のある人に対する悪い接客態度が噂として広まれば、店の評判は落ちて客足は遠のきます。
接客業であれば、イメージが向上して店の評判が良くなれば結果として売上げアップにつながります。
さらに、企業のイメージがアップすれば就活セミナーに学生が集まりやすくなり、優秀な学生を採用しやすくなります。
就職や転職には活かせない
介護に関しては、社会福祉士、ケアマネジャー、介護福祉士などの国家資格がいくつか存在します。
一方で、認知症ケア専門士、レクリエーション介護士などの民間の検定試験も数多く存在します。
サービス介助士も法律に基づかない民間資格の1つです。
サービス介助士の学習を通して、高齢者や身体に障害がある人を手伝うときの接客方法やおもてなしの心、介助の技術を学びますが、学習する内容はあくまでも基礎的です。
日本ケアフィット共育機構は、他にも認知症介助士、防災介助士等の民間資格を運営していますが、どれも同じです。
こういった短期間で取得できる民間資格では就職・転職は有利になりません。これといって世間でも評価されません。
稀に、就活を控えてサービス介助士の民間資格を取得する学生がいます。
けれど、こういった民間資格取得のために40,000円以上もするような講習会に参加するのってどうなのかなぁ・・・と個人的には疑問に感じます。
介護業界へ就職・転職を目指すのであれば、介護職員初任者研修や実務者研修、ガイドヘルパー(移動介護従事者)の方がおすすめです。
こちらの方が現場でも役立ちますし将来のステップアップに活かせます。
もちろん就職に直結します。多くの施設では資格手当を支給しています。
ガイドヘルパーの方がよほどおすすめ
個人で高齢者や身体の不自由な人に対する正しいサポート方法を学びたいのであれば、ガイドヘルパー(移動介護従事者)の資格がおすすめです。
ガイドヘルパーは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で定められたれっきとした国家資格です。
そのため就職や転職につながる可能性もあります。
ガイドヘルパーの資格は、3日間ほどの養成講座を受講すれば誰でも取得できます。
※主催する自治体(市区町村)や団体によって介護福祉士や介護職員初任者研修修了者を受講の条件としているのでご注意ください。
養成講座の受講費用も主催者によって違いますが、自治体や社会福祉協議会が開催する講座はかなり安く済みます。
受講の費用は3,000円ぐらいです。民間の団体であれば若干高いです。
ハローワークが募集する公共職業訓練であれば、受講料は無料で教材費のみ自己負担、介護職員初任者研修とガイドヘルパーを合わせて取得できて、しかも就職率90%以上という講座もあるようです。
将来性について徹底研究
鉄道会社への就職が有利になる?
サービス介助士を取得すれば鉄道会社への就職が有利になるのでしょうか?
こんな書き込みをネット上で見かけます。
きっと、駅員や車掌や運転士がサービス介助士のバッジを付けているのを駅で見かけたのでしょう。
結論を申し上げると、この程度の民間資格で就活は有利になりません。
講習を受講すればほぼ合格できます。いつでも誰でも取得できます。
履歴書に書いても評価されません。
鉄道会社は公共性が高く給料も安定してますからね、高校生・大学生にとっては憧れの就職先の1つです。就職したくて藁をもすがる思いなんだと思います。
バリアフリー化の一環として、サービス介助士の存在が認められつつあり、対外的アピールも兼ねて社員に取得させる鉄道会社も多くあります。
東急電鉄のように全社員にサービス介助士取得を義務化している会社もあります。
そんな光景を見ると、サービス介助士をあらかじめ取得して履歴書に書けば就職が有利になるのでは?と思うのは無理もないでしょう。
入社後に取得する手間が省ければ会社としては好都合なはずです。
しかし、繰り返しになりますがサービス介助士の資格を持っているからといって採用は有利にはなりません。
業務上必要となる資格であれば、入社後に会社の負担で大勢の社員をまとめてイッキに取得させます。しかも業務命令という形で。
会社にとっては数万円程度の取得費用が1人分浮いても大して変わりません。
誰でも取得できるよな民間資格よりも、もっと大事のことはいくらでもあります。
出身校や基礎学力、面接結果などです。
事前に取得して履歴書に書いても就職や転職は有利になりません。就活対策としてはあまり意味はありません。
介護業界への就職を目指すなら介護職員初任者研修
サービス介助士とは、駅、ショッピングセンターなど、人が集まる公共的な施設において、高齢者や障害者などを介助するための民間資格です。
介護系によくある民間資格の1つです。こういった検定試験などいくつ持っていてもあまり意味はありません。
介助技術や基礎知識をしっかりと学びたいのであれば、まずは介護職員初任者研修がおすすめです。
受講資格などはないので誰でも受講できます。
介護職員初任者研修を取得した後、経験を積んで介護福祉士やケアマネジャーにステップアップするのがベストでしょう。
合格するには
お金を払えば誰でも短期間で取得可能
サービス介助士になるには、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が開催する講座を受講しなければなりません。試験対策用の市販のテキストなどはありません。
公益財団法人日本ケアフィット共育機構が主催する検定試験は以下の3種類です。
- サービス介助士
- サービス介助基礎研修(セミナー)
- 准サービス介助士
※以前は、3級、準2級、2級の区分でしたが2016年に変更になりました。
取得するための費用と学習内容は以下の通りです(2024年1月現在)。
| サービス介助士 | ¥41,800(自宅学習+実技2日間) |
|---|---|
| サービス介助基礎研修 | ¥6,600(2時間1回のセミナー) |
| 准サービス介助士 | ¥22,000(自宅学習) |
![]() 参考:資格の種類・選び方|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構
参考:資格の種類・選び方|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構
どの種類も難易度は低いので短期間で誰でも取得できます。
8割以上の人がサービス介助士を選んで受験します。サービス介助基礎研修、准サービス介助士は入門級という位置付けです。
サービス介助士の講座であれば自宅学習+実技2日間を受講します。
実技は体が不自由な人の疑似体験と、介護技術のような学習をします。
例えば、歩行介助、車いす操作、おもりや白内障を体感できるグッズを身に着けてコンビニへ買い物にも行きます。
実技は全国各地で開催されていますが、地域によって開催場所が異なりますので、まずは会場へ行けるかが問題です。
自宅学習はさほど難易度は高くなく、数日間集中して学習すれば合格できます。 合格率は90%ほどです。
3年ごとに更新も必要
サービス介助士は3年に1度資格を更新します。
もちろん更新料1,650円(消費税10%込)が必要です。指定の期限内に更新手続きを行わないと資格が失効してしまいます。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
生活場面を中心に介助を必要とする場合の対応方法を、連続写真やイラスト図解で詳しく解説しています。日々の介助や介護に本書はすぐ役立つ内容で、とても素晴らしい本です。
声かけの方法や介助の方法などは、健常者の感覚でおこなうと、逆に混乱や不安をまねく結果になります。介助される側の気持ちを汲み取っていかに行動するかを教えてくれます。
介助ヘルパーから、介護する家族、さらには養成施設の学生にも役立つ内容です。自分のやり方を見直す良いきっかけになります。
| 種類 | 評価 |
| 参考書 |
講習情報
日程・受講資格・内容・その他
開催日
全国各地で随時開催
お申し込み
随時申し込みが可能です。
受講資格
誰でも受講できます。
講習会場
全国各地
受講料
当ページの冒頭をご覧ください。
講習内容
通信教育課程・課題提出、実技教習課程過程、検定試験を経て合格となります。
【通信教育課程・課題提出】
- サービス介助士の基本理念
- ホスピタリティ・マインド
- ノーマライゼーション
- 高齢社会の理解
- 高齢者への理解と介助
- 障がい者への理解と介助
- 障がい者の自立支援
- サービス介助士の接遇
- 関連法規および制度
※テキストで自宅学習の後、課題を提出します。課題は3択問題マークシート方式です。
提出課題は100問中60%以上の正解で合格です。
【実技教習課程】
- オリエンテーション
- ディスカッション(高齢者ってどんな人?)
- 高齢者疑似体験
- ディスカッション(体験の感想など)
- ジェロントロジー(創齢学)とは
- ホスピタリティー・マインド・接遇訓練
- 車いす操作方法・演習・移乗訓練
- 聴覚障がいの方への介助
- 歩行が不自由な方への介助
- 視覚障がいの方への介助・演習
- 盲導犬・聴導犬・介助犬
- ユニバーサルデザイン・共用品
- 車いす操作と手引きの実技チェック
- 総合ロールプレイ
- まとめ
※実技教習は連続した2日間で計12時間です。
ディスカッションでは感想や意見を出し合います。
【検定試験】実技教習2日目の最後に実施します。
問題数:50問(1問2点の100点満点)
試験時間:50分
試験方式:3択問題/マークシート方式
合格基準
70点以上(合格率は8割以上)
主催者情報
![]() 試験に関する詳しい情報は取得の流れ・料金|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構をご覧ください。
試験に関する詳しい情報は取得の流れ・料金|【公式】サービス介助士の公益財団法人日本ケアフィット共育機構をご覧ください。
