児童指導員になるには?資格要件や将来性などについて

| 種類 | 難易度 | 合格率 |
| 国家資格 | — | — |
| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |
| 学歴・資格・経験 | — | — |
| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |
| 就職・転職 | 6,791件 |  |
- 児童指導員任用資格の要件を満たし、就業すると児童指導員と名乗れます。試験などはありません。
- 全国の求人数は、ハローワークの求人情報を基に2025年12月24日に集計しました。
家庭のなんらかの事情で、支援が必要となった子どもに対し、社会で暮らしていくための訓練を保護者に代わって実施するのが児童指導員の仕事です。
児童指導員として働くには資格要件として福祉・介護関係の資格、保育士、幼稚園教諭、教員免許等の国家資格が必要です。
全国的に求人は多く、就業形態としては「正規の職員、従業員」が64.6%と最も高く、正社員としての採用が多い将来性のある国家資格です。
児童指導員とは

活躍の場は児童福祉施設
児童指導員は、家庭の事情で支援が必要な子どもに対し、社会で暮らしていくための訓練を保護者に代わって面倒をみます。
お母さん、お父さんの役割とも言えます。
活躍の場は主に児童福祉施設です。
児童福祉施設とは、例えば児童養護施設、児童発達支援センター、障害児入所施設、放課後等デイサービス、乳児院などです。
施設にいる子ども達は、障害のある児童、保護者のいない児童や虐待されている児童など様々です。
児童指導員は先生として、時に親代わりとして子ども達が将来社会生活を送れるように支援を行います。
子ども達がが将来自立した生活が送れるように成長を助け、社会に順応できるような環境づくりを行う重要な役割を担っています。
基本的に2歳から18歳未満の児童の成長と自立を支援
例えば、児童養護施設とは保護者のいない児童や問題を抱える児童の養育を行い成長と自立を支援するための施設です。
基本的に2歳から18歳未満で、両親の死去で保護者がいない児童、環境不良や虐待などで養護を必要とする子どもが入所します。
子どもたちが健全に成長・自立できるよう一人ひとりに合わせた支援計画をたて、日常生活の支援、社会ルールの習得、学習や遊びなどの支援・指導に当たります。
通常子ども達は学校へ通うので、朝は子どもを学校に送り出し、その後は日誌を記録するなど事務作業を行い、子どもたちが学校から帰ってきたら学年別に勉強の手伝いや身の回りの世話等を行います。
児童発達支援施設や放課後等デイサービス事業所では、児童発達支援管理責任者の指示のもと、個別支援計画や事業所のカリキュラムに基づいて障害のある子どもの支援を行います。
![]() 参考:児童指導員 – 職業詳細|職業情報提供サイト(日本版O-NET)厚生労働省
参考:児童指導員 – 職業詳細|職業情報提供サイト(日本版O-NET)厚生労働省
指導員任用資格が必要、資格試験などはありません
児童指導員とは、子ども達の教育や福祉に携わる職種のひとつであって「児童指導員」という名称の国家資格があるわけではありません。試験制度もありません。
児童指導員の仕事に就くには一定の学歴・職歴(実務経験)を証明するための書類(卒業証明書や実務経験証明書など)が必要となります。
そのため、児童指導員は「任用資格」と呼ばれています。
条件を満たすと児童指導員任用資格があると認められ、児童指導員を配置する事業所に所属している間だけ「児童指導員」と名乗ることができます(次章で詳しく解説)。
児童指導員の場合、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)に定められた、次のいずれかに該当する必要があります。
児童指導員になるには
児童指導員として働くには、いくつかの資格要件(任用資格)のうちいずれかに当てはまらなければなりません。下記がその要件となります。
- 4年制大学や通信制大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学部、学科を卒業している
- 社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得している
- 高校若しくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事している
- 3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定される
- 幼稚園教諭、小中学校、高等学校の教員免許を所有しており、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されている
4年制の大学で社会福祉学、心理学、教育学を修了すれば、自動的に任用資格の条件を満たします。
通信制大学でも大丈夫です。
任用資格を満たした上で、自治体が運営する施設で勤務する場合は公務員試験、民間の社会福祉法人等が運営する施設に勤務する場合は採用試験に合格しなければなりません。
その際には卒業証明書が必要です。事業所によっては成績証明書の提出を求められます。
その後就職して申請を出せば児童指導員として働けます。
高卒・中卒であれば、児童福祉施設で2年以上の実務を積めば任用資格の条件を満たします。
採用後、施設に勤務してはじめて児童指導員と名乗れるようになります。
![]() 参考:児童指導員及び指導員の資格要件等(追加資料2)|厚生労働省
参考:児童指導員及び指導員の資格要件等(追加資料2)|厚生労働省![]() 参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)
参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)
役に立つ資格なのか?

有効求人倍率は3.6倍
児童指導員として求人が多いのは、児童養護施設や乳児院、放課後等デイサービス、児童心理治療施設等です。
例えば、現在日本には1.5万か所以上の放課後等デイサービス事業所、600以上の児童養護施設があります。ほとんどが民間の社会福祉法人です。
![]() 参照: 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況|厚生労働省(pdf)
参照: 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況|厚生労働省(pdf)![]() 参照:社会的養護の施設等について|厚生労働省
参照:社会的養護の施設等について|厚生労働省
求人を探すと、全国各地で児童指導員を募集しているのが分かります。
令和3年度の全国平均の有効求人倍率は3.6倍といいますから、かなりの求人数です。
就業形態としては「正規の職員、従業員」が64.6%と最も高くなっています。
![]() 参照:児童指導員 – 職業詳細|職業情報提供サイト(日本版O-NET)|厚生労働省
参照:児童指導員 – 職業詳細|職業情報提供サイト(日本版O-NET)|厚生労働省
※「労働条件の特徴」を参照。
事業所数が多いワリには求人が少ないのは、定着率が高いのが理由のようです。
退職者が出たら補充するというケースが多いので求人は少ないようです。
他の国家資格所持が条件となっている場合が多い
採用条件を見ると多くの場合、保育士、幼稚園教諭免許、社会福祉士、精神保健福祉士なの国家資格が必須となっています。
理学療法士、公認心理師、看護師の資格が必須となっている施設もあります。
児童福祉施設などに就職した時に、児童指導員になれる資格(任用資格)があるので、それをついでに活かすといった感じです。
児童指導員の任用資格を満たしているからといって決して採用は有利だとは言えないようです。
児童指導員として働きたいのであれば、まずは保育士の資格を取得するのがおすすめです。
子ども達の送迎をするのであれば、当然ですが自動車免許も必要です。
将来性について徹底研究
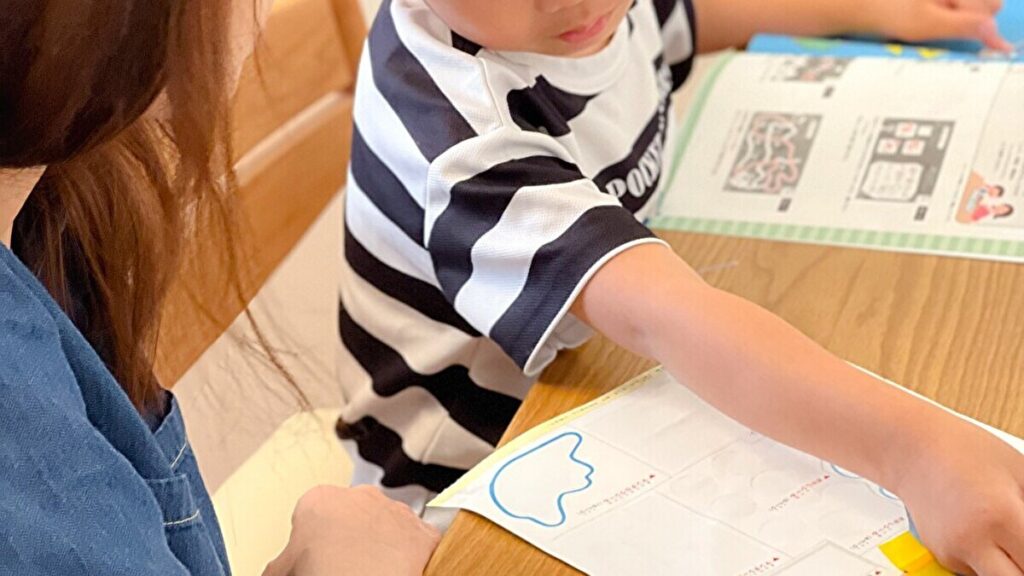
今後も児童指導員の需要は増える
近年、発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、チック症、吃音)と診断される子どもが増えています。
そのため、生活指導の場に限らず、症状にあった治療・教育を行う療育施設などでも児童指導員の需要が増えています。就職・転職先は今後も増えるでしょう。
児童福祉施設へ就職した後、児童指導員として実務経験を積んで、更に研修を受ければ「児童発達支援管理責任者」へステップアップも可能です。
仕事に対する「適正」について
児童福祉施設では、入所する子どもの健全な成長を視野に入れ、生活の様々な場面での支援・指導にあたることから、保護者代わりとしての一面を持つのが特徴です。
子どもの生活と安全を預かる仕事であるため、個々の気持ちに寄り添いながらも優しさや包容力、公平さなどが求められます。
対象となる子ども達の年齢は18歳くらいまでの男女なので思春期は接するのが難しいです。
集団作業やゲームをすると、泣き叫んだり、仲間外れにしたり、殴り合いの喧嘩が発生することも・・・
そんな時でも常に冷静に対応することができる「適正」が求められます。
給料・収入はどれくらい?
児童指導員の収入・給料は、都市部で手取り15~20万円、都市部以外では10~15万円が相場でしょう。パートであれば概ねその地域の最低賃金プラスαです。
就職後も昇給などはあまり望めません。ほぼ無いと考えた方がよさそうです。
「子ども達のために信念を持ってやってるから40歳でも収入は手取り10万ちょっとでも大丈夫!」と思えるくらいならいいかもしれません。
児童養護施設であれば24時間体制で運営されており、宿直も含め交替制で働くのであれば夜勤手当などが加算され給料はアップします。
児童指導員と放課後児童支援員の違い
主に小学生などの児童を相手とした福祉の仕事には、似たような名前の職種として放課後児童支援員があります。
![]() 関連資格:放課後児童支援員とは
関連資格:放課後児童支援員とは
放課後児童支援員の就業先は放課後児童クラブなどの学童保育施設で、仕事などで保護者が日中家にいない子ども達に放課後の「遊び」や「生活の場」を提供します。
ともに必要な資格要件・役割は似ていますが働く場所が違います。
児童指導員の任用資格は、放課後児童支援員の講習を受講する要件と若干の違いはありますがほぼ同じと考えてよいです。
放課後児童支援員の資格があれば、児童指導員としての要件もほぼ満たします。
テキスト・問題集・参考書
おすすめ参考書
学校という教育現場においてよく起こりうるエピソードについて、子どもが「なぜ?」・「なに?」に困っているのか、その原因を解説しています。
「4コマストーリー」→「背景の特性」→「支援と指導のヒント」という流れで構成されていて、とてもわかりやすいです。発達障害や集団に馴染まない生徒に対して、最新の研究をもとに支援する方法を紹介しています。
支援・指導の前に原因や特性を理解をするという視点で読めば、教育、福祉、家庭のの現場で子ども達を支援する際に有効なツールになるはずです。
| 種類 | 評価 |
| 関連書籍 |
